序論:潤沢と欠乏のパラドックス
「東京のスーパーじゃコメが余ってるんでしょ?…分けてよ!」
この叫びは、2024年から2025年にかけて日本を覆ったコメ危機の核心を突いている。それは単なる誤解から生まれたものではなく、深刻なパラドックスを的確に捉えた鋭い観察である。一方では、首都圏の店舗で高価なブランド米が棚に並び続け、他方では、地方の消費者が日々の糧であるはずのコメを求めて奔走し、政府が放出したはずの備蓄米の姿を目にすることすらない。この状況は、一体何を意味するのか。
本稿は、この「令和の米騒動」と称される危機、そしてそれがもたらした二極化が、単純な供給ショックや自然災害の結果ではないことを論証する。むしろそれは、数十年にわたり深く根を張ってきた政策レジーム、すなわち消費者福祉や市場論理、そして真の食料安全保障よりも、生産者の利益と価格維持を優先してきた「農政トライアングル」がもたらした、予測可能かつ不可避な帰結である。今回の危機は、日本の社会的・経済的な分断を新たに創出したのではない。それは、既存の分断を白日の下にさらし、かつてなく先鋭化させたのである。
本報告では、まず危機の解剖から始め、政府介入の失敗を詳述する。次に、その根底にある政策的欠陥を暴き出し、結果として生じた社会的断層を分析する。そして最後に、より強靭で公平なシステムへの道を提言することで、この複雑な問題の全体像を明らかにしていく。
第1章 「令和の米騒動」の解剖学
1.1 価格の噴出:エスカレーションの時系列
2024年から2025年にかけてのコメ価格の高騰は、日本の食卓に前例のない衝撃を与えた。2024年初頭には1キログラムあたり約300円で安定していた価格は、同年8月末には500円を超える水準まで急騰した 1。この動きは、具体的な小売価格データにも鮮明に記録されている。例えば、東京都区部におけるコシヒカリ5キログラムの店頭小売価格は、2023年12月の2,422円から、わずか1年後の2024年12月には4,018円へと、実に1.68倍に跳ね上がった 2。この高騰は2025年に入っても収まらず、高止まりを続けた 3。さらにマクロな視点で見ると、2025年1月にはコメ類の消費者物価指数が対前年同月比で$+70.9%$という驚異的な上昇を記録し、他の主食群から突出していた 3。
この価格の急騰は、近年の歴史において類を見ないものであった。2003年の価格上昇を規模で大きく上回り、社会的な影響においては、初期の供給減の大きさこそ違えど、1993年の「平成の米騒動」に匹敵するものとなった 2。この異常事態は、単一の原因ではなく、複数の要因が連鎖的に作用した結果であった。
1.2 直接的な引き金:完璧な嵐
危機の最初の火種は、2023年の記録的な猛暑であった。この異常気象は、必ずしも収穫「量」の壊滅的な減少を引き起こしたわけではない。事実、2023年産米の作況指数は101と平年並みであった 2。しかし、問題は「質」の著しい低下にあった。特に東日本を中心に、高温障害による「白未熟粒(しろみじゅくりゅう)」などの被害粒が多発したのである 2。
この品質低下が、決定的な帰結をもたらした。それは「精米歩留まりの悪化」である。つまり、同じ量の高品質な精米(白米)を生産するために、より多くの低品質な玄米が必要になるという問題だ 1。専門家の山下一仁氏らの分析によれば、この影響により実質的に約30万トンから40万トンの供給不足が発生したと推定されている 6。これは、目に見えない形での供給ショックであった。
この潜在的な品質問題に火をつけたのが、人的要因であった。2024年8月8日、気象庁が南海トラフ地震に関連する臨時情報を発表した 1。この発表と、メディアによる「コメが消えた」「令和の米騒動」といったセンセーショナルな報道が連日繰り返されたことで、消費者の間に深刻な不安が広がり、全国的なパニック買いと買いだめが発生した 1。スーパーの棚からコメが消える映像が、さらなる買い占めを誘発し、不足は自己実現的な予言となって現実化したのである。
1.3 中核の謎:「消えたコメ」
政府関係者を当惑させたのが、統計上の謎、いわゆる「消えたコメ」問題であった。2024年産の収穫量は前年を上回ったにもかかわらず、JA(農業協同組合)などの集荷業者による集荷量は、予想を大幅に下回ったのである 8。
この現象の背後には、市場参加者の合理的な行動があった。価格高騰を予見した農家や小規模な流通業者は、従来のJAを通じた出荷ルートを回避し、より高い価格で直接販売を行ったり、在庫を手元に保持したりした 8。これは伝統的な意味での「買い占め」や「売り惜しみ」というよりは、不透明なシステムの中での合理的な市場反応であった。
しかし、政府の初期認識は異なっていた。農林水産省は当初、正体不明のブローカーや卸売業者が投機目的でコメを隠匿しているという見解を示した 6。だが、この「消えたコメ」は、秘密の倉庫に隠されていたわけではなかった。それは、JA主導の伝統的な流通システムが機能不全に陥り、農林水産省が市場のシグナルを根本的に読み違えたことで生まれた幻影だったのである。コメは存在から「消えた」のではなく、JAの台帳から「消え」、より高値で取引される代替的な、そして政府にとって可視性の低いルートへと流れていったのだ。
第2章 幻の解決策:なぜ政府備蓄米は食卓に届かなかったのか
2.1 遅きに失した、的を射ない対応
危機が顕在化する中、政府の対応は遅く、その目的も国民の期待とは乖離していた。2024年8月に大阪府知事などから備蓄米放出の要請があったにもかかわらず、農林水産省は当初、「新米が出れば解消する」として介入を拒否した 6。これは、供給不足の深刻さを見誤った致命的な判断ミスであった。
その後、世論の圧力に押されて政府は備蓄米の放出を決定するが、その公式な目的は、驚くべきことに価格の引き下げではなかった。あくまで「流通の円滑化」のため、とされたのである 8。この言葉の選択は、極めて重要である。
この「円滑化」という物語は、政治的な操作であった。農政トライアングル(後述)からの圧力の下、農林水産省は減反政策の根幹である高米価構造を自ら崩すわけにはいかなかった。放出の目的を「詰まった」流通システムを修理するための物流的な措置と位置づけることで、国民の不安に応えているように見せかけつつ、高価格政策そのものは維持するという、矛盾した目的を両立させようとしたのである。しかし、流通の「目詰まり」は作り話に過ぎなかった。真の問題は、政府が公式には認めようとしなかった物理的な供給不足だったのである 7。
2.2 どこにも行き着かない旅:備蓄米の欠陥だらけの流通
政府の介入がパフォーマンスに過ぎなかったことは、その衝撃的な結果によって証明された。最初に放出された備蓄米14万トンのうち、2025年3月末までに小売店に届いたのは、わずか426トン、全体の0.3%に過ぎなかったのである 10。
この背景には、複数の構造的欠陥があった。第一に、物流のボトルネックである。備蓄米は入札を経て、全国の卸売業者に分配されるが、その量の調整や輸送計画に約1ヶ月を要する 12。危機に対応するにはあまりに悠長なシステムであった。
第二に、配分の失敗である。放出されたコメは、JA全農などの大手集荷業者に売却された 11。これらの業者は、当然ながら自社の大口顧客である大手スーパーや外食・中食産業への供給を優先した 13。その結果、地方の中小小売店や、最もコメを必要としている消費者にはほとんど行き渡らなかった。ある卸売業者は600トンの供給を要望したにもかかわらず、実際に割り当てられたのはわずか36トンだったという事例もある 12。
地方の消費者が「備蓄米を一度も見たことがない」と語るのは、誇張ではない。それは、大多数の国民、特に地方在住者にとって文字通りの、経験された現実であった。備蓄米の放出システムは、危機時に全国へ迅速かつ公平に分配されるようには設計されていなかった。それは、平時に予測可能な大量のコメを、中央から地方へと流す既存のチャネルをなぞるだけであり、本質的に中心部を優遇し、周縁部を切り捨てる構造だったのである。
2.3 失敗するように設計された政策か?
さらに、この放出策には、価格を下げないための巧妙な仕掛けが施されていた。売却にあたって付された「買戻し条件付売渡し」という特約である 14。これは、売却したコメを1年以内に同等同量で買い戻すことを義務付けるものであった。この条件は、市場に対して今回の供給増が一時的なものであるという強力なシグナルを送った。卸売業者にしてみれば、いずれ買い戻さなければならないコメの価格を、積極的に下げるインセンティブは働かない。
専門家の山下一仁氏が、これを農林水産省による価格下落を阻止するための「巧妙なカラクリ」だと痛烈に批判したのは、このためである 15。結論として、備蓄米放出は、政策的アリバイ作りのための壮大な茶番であった。それはメディアで報じられ、政府が対策を講じているという印象を与えたが、その制度設計と実行プロセスは、消費者価格への影響を最小限に抑え、高米価という現状を維持することを確実にするものだった。
以下の表は、政府の介入と、消費者が直面した小売価格の現実との間の完全な断絶を視覚的に示している。
|
時期 |
政府の措置 |
全国平均小売価格(5kg) |
専門家・メディアの論評 |
|
2025年3月 |
第1回備蓄米入札:141,796トン売却成立 14 |
4,217円(15週連続で最高値更新)10 |
「備蓄米は小売店に届いていない」との報道 |
|
2025年4月 |
第2回入札実施、毎月10万トンの放出計画を発表 17 |
4,000円台で高止まり。18週ぶりに19円(0.4%)下落 15 |
「JAが市場を支配する限り価格は下がらない」(山下氏)15 |
|
2025年5月以降 |
毎月の放出継続 |
再び35円値上がり 18 |
「備蓄米放出の効果は薄れつつある」(専門家)18 |
この表が示すのは、単なるデータの羅列ではない。それは一つの物語を構築する。放出されたコメの膨大なトン数の横に、頑なに高止まり、あるいは再上昇する小売価格を並べることで、介入が完全に失敗したという強力な視覚的論拠が生まれる。「政府はコメを放出したと言っているのに、なぜ価格はこんなに高いのか?」という国民の素朴な疑問に対し、この表は反論の余地のない答えを突きつけているのである。
第3章 失敗の構造:数十年の政策と名ばかりの市場
3.1 原罪:50年にわたる減反政策
今回の危機の脆弱性をシステムに埋め込んだ根源は、1970年代に始まった減反政策にある。コメの過剰供給を抑制し、価格を支えることを目的に導入されたこの政策は 1、2018年に名目上廃止された後も、実質的に継続されてきた。飼料用米や小麦などへの転作に対する補助金という形で、主食用米の生産は抑制され続けているのである 1。この政策のために、納税者の負担は年間約3,500億円に上る 19。
この減反政策こそが、システムの脆弱性の根本原因である。数十年にわたって生産を人為的に抑制してきたことで 6、日本農業は需給の緩衝能力を完全に失った。2023年の猛暑のような供給ショックが発生した際、それを吸収する余力はシステム内に存在しなかった。この政策は、価格の安定と引き換えに、システムの強靭性を犠牲にしてきたのである。さらに、この政策は技術革新をも阻害した。生産抑制が至上命題であるため、単位面積あたりの収量(単収)を上げるような品種改良はタブー視され、その結果、日本のコメの単収は、かつては同水準であったカリフォルニアや、追い抜いたはずの中国にも後れを取るという事態を招いている 6。
3.2 「農政トライアングル」
この歪んだ政策を維持し、永続させてきたのが、専門家が「農政トライアングル」と呼ぶ、強固な利益共同体である 6。これは、
農林水産省、JA(農業協同組合)、そして自民党の農林族議員の三者が結びついた、共生的かつ自己保存的な関係を指す。
- JAの役割:JAの組織力の基盤は、膨大な数の小規模・兼業・非効率なコメ農家にある 21。減反政策によって維持される高米価が、これらの農家を農地に留め置く。彼らはJAにとって巨大な政治的基盤(組合員)であると同時に、その金融部門であるJAバンク(今やメガバンクに匹敵する)に預金をもたらす重要な顧客でもある 6。
- 政治家の役割:JAによって組織されたこれらの農家は、農林族議員にとって強力な票田となる。議員たちはその見返りとして、農林水産省の予算獲得に尽力し、減反システムを政治的に保護する 6。
- 農林水産省の役割:農林水産省は、このトライアングルを維持するための政策を立案・実行する。その見返りとして、JAは同省官僚の重要な天下り先となっている 6。
このトライアングルこそが、危機を永続させる制度的装置である。その核心的利益は、食料安全保障や消費者福祉ではなく、高米価構造の維持にある。2024年から2025年の危機において下された、一見すると非合理的な決定の数々――不足の否定、見せかけの備蓄米放出、そして「投機筋」への責任転嫁――は、このトライアングルの利益を守るための合理的な行動として理解することができる。
3.3 脈拍のない市場:価格発見の幻想
現在の日本には、競争的で透明性の高いコメ市場は事実上存在しない 6。JAが一貫して反対してきたため、機能的な先物市場も存在しない 6。
価格決定を支配しているのは、「相対取引」と呼ばれる、主に市場を独占するJAと卸売業者との間の不透明な個別交渉である 6。このプロセスにより、JAは事実上、価格をコントロールする力を握っている。
この絶大な市場支配力は、今回の危機へのJAの対応に如実に表れている。農家離れを食い止め、集荷率を回復させるため、JAは2025年産米に対して、収穫の結果に関わらず、例年の倍近い異例の高値の仮払金(概算金)を提示した 6。これは市場原理に基づいた価格シグナルではない。市場を規律し、高価格を翌年以降も固定化させるための、圧倒的な市場支配者によるパワープレイに他ならない。
第4章 社会の断層:誰が日本のコメを食べられるのか?
4.1 広がる亀裂:ブランド信奉者と価格から締め出された人々
今回の危機は、消費者の間に深刻な二極化を生み出した。調査によれば、一部の消費者は慣れ親しんだブランド米を買い続ける一方で、他の多くの消費者はより安価な代替品(ブレンド米など)への移行を余儀なくされたり、消費量そのものを減らしたりしている 23。
この分断は、価格差の拡大によって定量的に裏付けられる。危機が始まる前は200円程度であった銘柄米とその他のコメ(ブレンド米など)の5キログラムあたりの価格差は、危機後には1,100円以上にまで劇的に拡大した 24。
これは、冒頭の「東京のスーパーではコメが余っている」という問いに直接的な答えを与える。その人物が見ているのは、おそらくこれらの高価なブランド米である。一部の富裕層は依然としてそれを購入できるため、棚に残り続ける。一方で、多くの人々にとって「消えてしまった」コメとは、手頃な価格で毎日購入できた、ごく普通のコメなのである。
4.2 逆進的な危機:貧困層への不釣り合いな負担
コメは、支出弾力性が低い「基礎的支出」に分類される必需品である 25。これは、所得が減少しても消費量が大きくは減らないことを意味し、それゆえ価格高騰は低所得者層を最も直撃する。
直接的なデータもこの事実を裏付けている。所得階層にかかわらず、コメの消費量は月間4キログラム弱でほぼ一定である一方、家計支出に占めるコメの割合は低所得者層ほど高くなるため、価格高騰の影響はより深刻になる 26。この価格高騰は、一世帯あたり年間数万円の追加負担になると試算されている 3。
この米価高騰は、強力な逆進性を持つ税金として機能している。それは、最も貧しい消費者から、保護された農業セクターへと富を移転させる。これは偶然の副作用ではない。ある専門家が指摘するように、「消費税以上に逆進的」な高米価政策がもたらした、論理的な帰結なのである 27。
以下の表は、同じ価格上昇が、所得階層によっていかに異なる負担となるかを定量的に示している。
|
年間世帯収入階級 |
年間コメ支出(危機前) |
年間コメ支出(危機ピーク時) |
コメ支出増加額(円) |
総所得に占めるコメ支出増加額の割合 |
|
第I分位(~350万円) |
28,800円 |
50,400円 |
21,600円 |
0.62% |
|
第II分位(~500万円) |
28,800円 |
50,400円 |
21,600円 |
0.43% |
|
第III分位(~650万円) |
28,800円 |
50,400円 |
21,600円 |
0.33% |
|
第IV分位(~850万円) |
28,800円 |
50,400円 |
21,600円 |
0.25% |
|
第V分位(850万円~) |
28,800円 |
50,400円 |
21,600円 |
< 0.25% |
|
注:危機前の価格を5kg 2,400円、ピーク時を5kg 4,200円、月間消費量を5kgと仮定して試算。収入階級は代表値を使用。 |
|
|
|
|
この表は、「逆進的影響」や「二極化」といった抽象的な概念を、具体的な数字に落とし込んでいる。支出の絶対額(増加額)は全階層で同じでも、所得に占める負担の割合は、最も所得の低い階級で最も重くなることが一目瞭然である。これは、この危機が単なる価格の問題ではなく、経済的正義の問題であることを証明している。
4.3 「新しい日本」の縮図:経済停滞の症状としてのコメ二極化
この分析をより広い文脈に位置づける必要がある。コメの二極化は、実質賃金の停滞、格差の拡大、そして中間層を空洞化させてきた「労働市場の二極化」といった、日本のより大きな経済的病理の症状として捉えるべきである 29。
米国の事例は、比較モデルとして示唆に富む。米国では、資産効果に支えられた高所得層が消費を維持する一方で、低所得層はインフレ、高金利、雇用悪化の三重苦に直面し、消費の二極化が進行している 32。
日本でも、これと類似した、しかし日本独自の力学が働いている。今回のコメ危機は、日本社会に深く刻まれた亀裂を明らかにしたストレステストであった。一袋のコメを買う余裕があるかどうかが、このますます二極化する経済における個人の立ち位置を示す、残酷な指標となってしまったのである。
第5章 米蔵の再建:安定的で公平な食の未来への道筋
5.1 旧体制の解体:減反廃止の論拠
改革への道筋は、山下一仁氏のような専門家たちの間で、既にコンセンサスが形成されている 6。その第一歩は、あらゆる形骸化した補助金制度を含め、減反政策を完全かつ最終的に廃止することである。これだけで年間3,500億円の税金が節約され、生産量は国内需要を満たすだけでなく、輸出に回す余力さえ生み出すことができる 19。
5.2 農業のための新しい社会契約:価格支持から直接支払いへ
次に必要なのは、世界中の経済学者が推奨するパラダイムシフトである。すなわち、コメの「価格」を支える政策から、農家の「所得」を直接支える政策への転換だ 6。
そのモデルは明確である。まず、コメの市場価格を競争的な水準まで下落させ、すべての消費者に利益をもたらす。その上で、価格低下によって影響を受ける効率的な専業農家(主業農家)に対してのみ、的を絞った直接的な所得補償(直接支払い)を行う 27。
この政策は、農業の構造改革を強力に促進する。農業所得に依存していない非効率な兼業農家は、コメ作りを続けるインセンティブを失い、その農地を主業農家に貸し出すようになる。これにより、農地が集約され、規模の経済が働き、生産コストの低下と生産性全体の向上が実現する 21。
5.3 食料安全保障の再定義:希少性から豊かさへ
伝統的な、鎖国主義的な日本の食料安全保障観に挑戦する必要がある。真の安全保障とは、山下氏が論じるように、世界市場で競争できる、強靭で効率的かつ生産的な農業セクターを持つことによって達成される 6。
その先には、大胆なビジョンが広がる。日本は1,000万トン以上のコメを生産する潜在能力を持つ。その余剰分を輸出することで、日本は世界の食料安全保障に貢献する主要なプレーヤーとなりうる。そして、シーレーンが寸断されるような真の国家非常事態が発生した際には、この輸出分を国内消費に振り向ければよい。それは、現在の100万トンの備蓄をはるかに凌駕する、事実上の「無料の」国家備蓄として機能するのである 6。
結論:人為的な危機は、人間中心の解決策を求める
本稿で明らかにしてきたように、「令和の米騒動」は偶然の産物ではない。それは、他のすべてを犠牲にして「農政トライアングル」を保護するために設計されたシステムが、設計通りに機能した結果である。二極化、地域間格差、そして見せかけの介入はすべて、この中核的な機能不全の症状に他ならない。
前進への道は、このトライアングルの既得権益を解体する政治的勇気を必要とする。目標は、国全体に奉仕する食料システムを創造すること、すなわち、日本の最も重要な主食であるコメが、経済的不平等と社会的分断の象徴ではなく、手頃な価格の糧であり、国民的誇りの源となることを確実にすることである。
「分けてよ!」という悲痛な叫びに対する真の答えは、東京から最も小さな地方の町に至るまで、すべての人のために十分な価格のコメを保証する、根本的な制度改革以外にあり得ない。
引用文献
- 令和の米騒動 – Wikipedia, 8月 3, 2025にアクセス、 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%A4%E5%92%8C%E3%81%AE%E7%B1%B3%E9%A8%92%E5%8B%95
- 『令和のコメ騒動』(1)コメ高騰の歴史に学ぶ、今後の見通し 食料 …, 8月 3, 2025にアクセス、 https://www.mri.co.jp/knowledge/column/20250128.html
- 【令和の米騒動】2025年最新動向|政府備蓄米放出の効果と今後 – 株式会社エデンレッドジャパン, 8月 3, 2025にアクセス、 https://edenred.jp/article/productivity/220/
- 令和の米騒動が起きた背景と農業の現状~米の価格高騰はなぜ起きた?, 8月 3, 2025にアクセス、 https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=81723?site=nli
- 「令和の米騒動」はなぜ起きたのか 一問一答による考察 | JBpress (ジェイビープレス), 8月 3, 2025にアクセス、 https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/89445
- 令和の米騒動と必要な農政構造改革 山下 一仁(キヤノングローバル …, 8月 3, 2025にアクセス、 https://www.intelligence-nippon.jp/2025/07/17/6062/
- この人に任せればコメ価格は下げられる…農政の専門家が名前をあげるJA農協にメスを入れられる唯一の人物 | キヤノングローバル戦略研究所, 8月 3, 2025にアクセス、 https://cigs.canon/article/20250408_8773.html
- 「消えたコメ」の謎、供給不足の原因は不明のまま 価格高騰が消費者や …, 8月 3, 2025にアクセス、 https://toyokeizai.net/articles/-/864149?display=b
- 食料自給率高める農業政策へ転換を 「今こそ日本の食と農を守ろう」緊急集会での生産者や学者からの提言 | 長周新聞, 8月 3, 2025にアクセス、 https://www.chosyu-journal.jp/shakai/35121
- 【備蓄米どこにいった?】小売店への流通はたった0.3% 放出でも安くならない背景には『コメが安すぎると困る人たち』の存在も?元農水省官僚の見解【解説】(2025年4月21日) – YouTube, 8月 3, 2025にアクセス、 https://www.youtube.com/watch?v=BY8HXYYjFss&pp=0gcJCdgAo7VqN5tD
- 備蓄米放出で新制度=高騰受け、流通安定へ―農水省審議会 – 特集、解説記事, 8月 3, 2025にアクセス、 https://equity.jiji.com/commentaries/2025013100835g
- “見かけない備蓄米”はどこへ?流通が進まないワケを調査 トランプ関税で日本のコメの未来が変わる? – YouTube, 8月 3, 2025にアクセス、 https://www.youtube.com/watch?v=iqJXI1T29lE&pp=0gcJCdgAo7VqN5tD
- 株式会社日本農産情報 トップページ, 8月 3, 2025にアクセス、 https://nousan-j.com/
- 政府備蓄米の買戻し条件付売渡しの入札結果の概要について – 農林水産省, 8月 3, 2025にアクセス、 https://www.maff.go.jp/j/press/nousan/boeki/250314.html
- 残念ながら来年秋まで「5㎏4200円」が続きます…農水省とJA農協がいる限り「コメの値段は下がらない」そのワケ | キヤノングローバル戦略研究所, 8月 3, 2025にアクセス、 https://cigs.canon/article/20250602_8934.html
- 【速報】備蓄米落札結果 江藤農水相が公表 – YouTube, 8月 3, 2025にアクセス、 https://www.youtube.com/watch?v=5Rim1kiyak0
- 農水省、備蓄米流通のルールを変更 迅速に消費者に届ける, 8月 3, 2025にアクセス、 https://news.nissyoku.co.jp/news/sato20250516104510604
- コメ値上がり10週ぶり 備蓄米効果薄れ 今後の価格の見通しは? – ABEMA, 8月 3, 2025にアクセス、 https://abema.tv/video/episode/89-44_s0_p443927
- SCMの観点から令和のコメ騒動を考える1 | 株式会社NX総合研究所, 8月 3, 2025にアクセス、 https://www.nx-soken.co.jp/topics/blog_20250428
- 誰のための農政か – RIETI, 8月 3, 2025にアクセス、 https://www.rieti.go.jp/jp/papers/contribution/yamashita/155.html
- 農業の正しい理解を妨げる者 – キヤノングローバル戦略研究所, 8月 3, 2025にアクセス、 https://cigs.canon/article/20250709_9031.html
- 米価を下げる根本的対策は減反廃止しかない – キヤノングローバル戦略研究所, 8月 3, 2025にアクセス、 https://cigs.canon/article/20250611_8967.html
- 【消費の深層】 高騰するコメに地域で価格差 ブランド銘柄離れの可能性も浮上 – 食品新聞, 8月 3, 2025にアクセス、 https://shokuhin.net/123101/2025/06/15/%E8%BE%B2%E6%B0%B4%E7%95%9C%E7%94%A3%E6%A5%AD/%E7%B1%B3%EF%BD%9B%E3%82%B3%E3%83%A1%EF%BD%9D/
- 店頭のコメ「安くなった実感」届かず…銘柄米とブランド米で広がる価格差 備蓄米の放出後1100円超え=静岡 – 静岡新聞, 8月 3, 2025にアクセス、 https://www.at-s.com/snews/article/ats/1772348.html
- 家計調査 用語の解説 – 総務省統計局, 8月 3, 2025にアクセス、 https://www.stat.go.jp/data/kakei/kaisetsu.html
- 所得階層別にみた食料品価格の高騰の影響-賃金を考慮した価格 …, 8月 3, 2025にアクセス、 https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=81899?site=nli
- 食料・農業・農村基本法の見直し 政策審議会「中間とりまとめ」の矛盾と問題(下), 8月 3, 2025にアクセス、 https://www.rieti.go.jp/jp/special/special_report/193.html
- 農業を国民に取り戻すための6個の提言食料・農業・農村基本法見直しを機に農政を抜本的に正せ, 8月 3, 2025にアクセス、 https://www.rieti.go.jp/jp/papers/contribution/yamashita/133.html
- 技術変化は格差を縮める – 独立行政法人経済産業研究所, 8月 3, 2025にアクセス、 https://www.rieti.go.jp/jp/papers/contribution/kobayashi/46.html
- 労働市場の二極化, 8月 3, 2025にアクセス、 https://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2009/02-03/pdf/073-090.pdf
- 米株価急落で露呈した「二極化経済」の脆弱性、企業収益の偏在と低所得層の“三重苦”, 8月 3, 2025にアクセス、 https://diamond.jp/articles/-/348950
- 米国経済の二極化~家計編~ – みずほリサーチ&テクノロジーズ, 8月 3, 2025にアクセス、 https://www.mizuho-rt.co.jp/publication/2024/pdf/insight-us240708.pdf
- 米国消費の二極化と企業決算 – みずほリサーチ&テクノロジーズ, 8月 3, 2025にアクセス、 https://www.mizuho-rt.co.jp/publication/2024/pdf/insight-us240603.pdf

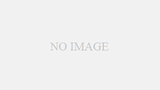
コメント