要旨(Executive Summary)
本レポートは、令和7年(2025年)秋から令和10年(2028年)頃までの日本における食料不足と物価高騰のリスクについて、専門家向けの包括的な未来予測を提示するものである。本分析は、国内生産基盤の構造的脆弱性、国際情勢に起因する外部ショックの増幅、そして国内サプライチェーンを掌握する流通業者の戦略的意図という三つの要因を一体的に分析することを特徴とする。
日本の食料システムは、国内における生産者の高齢化・減少と耕作放棄地の拡大、さらには気候変動への適応の遅れといった構造的脆弱性を抱えている 1。これに、円安の常態化、地政学的リスクの高まり、そして世界的な異常気象の頻発といった外部からの複合的ショックが加わることで、システム全体の耐性が著しく低下している 4。特に、大手卸・小売業者が主導する国内の価格形成メカニズムは、コスト上昇圧力を複雑化させ、品目による価格変動の二極化を加速させる重要な変数として機能している。
本分析では、これらの要因を基に3つの未来シナリオを構築した。
- ベースライン・シナリオ(現状維持・緩慢な悪化): 最も蓋然性が高いシナリオ。食料インフレは年率2~4%で継続し、特に加工食品や外食産業において内容量を減らす「ステルス値上げ(シュリンクフレーション)」が常態化する 5。輸入依存度の高い小麦、油脂、飼料関連品目では、短期的な供給不安が散発的に発生するリスクを抱える。
- 悲観シナリオ(複合危機・パーフェクトストーム): 複数の外部ショックが連鎖する世界。食料インフレ率は年率10%超に急騰し、小麦、大豆、鶏肉などの品目では物理的な供給不足が発生する。これにより政府備蓄の放出が試され、社会不安が高まる可能性がある 8。
- 変革シナリオ(危機をバネにした構造転換): 危機を契機に、政府・民間が抜本的な政策転換に踏み切る世界。短期的には移行コストによる価格上昇が見込まれるものの、中長期的には米の増産と飼料用への転作、スマート農業への投資が進展し、国内供給基盤が強化される方向へ向かう 10。
結論として、予測期間において日本はベースライン・シナリオを辿る可能性が最も高いと分析する。しかし、その安定性は極めて脆弱であり、悲観シナリオへ分岐するリスクは看過できない。政府および関連企業は、国内生産基盤の再構築、サプライチェーンの多元化、そして流通構造の透明性向上といった課題に直ちに着手することが、将来の国民生活と経済の安定にとって不可欠である。
第1部:未来を規定する現在地(2020-2025年)の構造分析
予測期間の未来を展望するにあたり、まずその出発点となる2020年から2025年にかけて日本の食料システムが直面した構造的な問題を、国内要因、国外要因、そして両者をつなぐ流通業者の視点から多角的に解剖する。この期間に顕在化した脆弱性は、将来のリスクを理解する上で不可欠な前提となる。
1.1. 国内供給力の構造的減衰
日本の食料供給の根幹をなす国内農業は、単なる産業の衰退ではなく、国家の安全保障を揺るがすレベルで構造的に弱体化している。その実態は、人的資源の枯渇、土地資源の荒廃、気候変動への不適応、そして政策的な供給制約という四つの側面から浮き彫りになる。
人的・土地的資源の枯渇
国内農業の持続可能性は、その担い手である農業従事者の激減と超高齢化によって、今や風前の灯火である。2020年時点で、農業の根幹をなす基幹的農業従事者のうち、実に70%が65歳以上の高齢者で占められており、その平均年齢は68.4歳に達している 1。農林水産省の推計によれば、この基幹的農業従事者は今後20年間で現在の約120万人から約30万人へと、4分の1にまで急減する見込みである 13。この構造的な問題を補うべき新規就農者の数も伸び悩み、近年では減少に転じるなど、世代交代は全く進んでいない 12。
この人的資源の枯渇と直結するのが、耕作放棄地の拡大である。2020年には、一度農地であったにもかかわらず放置されている「荒廃農地」が28.4万ヘクタール、農家の耕作意思に基づき放棄された「耕作放棄地」は42.3万ヘクタールに達した 1。その最大の原因は、他ならぬ「高齢化・労働力不足」であり、これは食料自給率の低下に直接的な影響を与えている 1。特に、地形的に不利な山間農業地域では耕作放棄地の比率が平地農業地域の倍近くに達しており、問題の深刻さには地域的な偏在も見られる 16。
ここで見過ごされがちなのは、耕作放棄地が単なる「空き地」ではなく、周辺の農業生産に対して能動的に負の影響を与える「リスク源」として機能している点である。耕作が放棄された土地は管理がおろそかになり、病害虫の発生源となる 2。これらの病害虫は隣接する健全な農地へ拡散し、作物の品質低下や収量減を引き起こす。また、耕作放棄地は猪や鹿といった野生動物の格好の隠れ家となり、周辺農地への鳥獣害を深刻化させる 2。これにより、農業を継続している農家は、農薬散布や防護柵設置といった追加的なコスト負担を強いられ、収益性がさらに悪化する。この収益性の悪化が、新たな離農や耕作放棄を誘発するという「負のフィードバックループ」が形成されており、統計上の面積減少が示す以上に、国内の生産基盤は深刻なダメージを受けている。
気候変動と政策の逆機能
こうした国内の構造的脆弱性に追い打ちをかけているのが、気候変動の影響の顕在化と、良かれとした政策の意図せざる副作用である。
気候変動の影響は、もはや将来のリスクではなく、現在の収穫に直接的な打撃を与えている。令和5年(2023年)は日本の観測史上最も平均気温が高い年となり、特に稲作においては、出穂期以降の高温により米粒が白く濁る「白未熟粒」が全国の水田の約5割で確認されるなど、品質と収量の低下が広範囲で発生した 3。このような高温環境に適応するための「高温耐性品種」の開発と普及が急務であるが、その作付割合は令和5年時点で全体の14.7%に留まっており、気候変動のスピードに農業技術の適応が追いついていないのが実情である 3。
さらに、国内の供給能力を自ら縛っているのが、長年にわたり続けられてきた米の生産調整、すなわち「減反政策」である。2024年に発生した米不足とそれに伴う価格高騰は、猛暑による不作という天候要因に加え、この減反政策が根本的な原因であるとの専門家からの強い指摘がある 10。現在、日本の水田の約4割が減反、すなわち主食用米以外の作物への転換や休耕の対象となっており、生産量が人為的に抑制されている 10。この政策は、米価の安定と農家所得の確保を目的としているが、その実態は、米の流通を牛耳るJA(農業協同組合)が米価を高値で維持することで、自らの取扱手数料収入を最大化しようとする組織的利益の追求と密接に結びついている 10。政府が減反に協力する農家に補助金を交付する一方で、JAは農家に対して生産を減らすよう指導し、結果として米の市場価格は高止まりする。例えば、JA全農と卸売業者との取引価格は、60kgあたり2021年産の12,804円から2024年産には22,700円へと急騰した 10。この人為的な供給抑制は、猛暑による不作やインバウンド需要の増加といった比較的小さな需給変動(全体の5%未満と試算)に対してさえ、市場のバッファー(緩衝材)を失わせ、深刻な価格高騰と品薄感を引き起こす構造を生み出している 10。これは、平時の価格安定と有事の供給能力確保という食料安全保障の基本目標と完全に矛盾する「政策の失敗」であり、流通業者の戦略を論じる以前に、生産段階に根深い構造的な価格吊り上げメカニズムが存在することを示している。
表A:主要品目別食料自給率の推移(令和2~4年度、カロリー・生産額ベース)
|
品目 |
基準 |
令和2年度 |
令和3年度 |
令和4年度 |
|
総合食料自給率 |
カロリーベース |
37% |
38% |
38% |
|
|
生産額ベース |
67% |
63% |
58% |
|
米 |
カロリーベース |
97% |
98% |
99% |
|
小麦 |
カロリーベース |
15% |
16% |
17% |
|
大豆 |
カロリーベース |
6% |
7% |
7% |
|
野菜 |
重量ベース |
79% |
79% |
79% |
|
果実 |
重量ベース |
39% |
38% |
34% |
|
肉類 |
重量ベース |
53% |
53% |
53% |
|
牛乳・乳製品 |
生乳換算 |
63% |
63% |
62% |
|
魚介類 |
重量ベース |
57% |
54% |
56% |
|
油脂類 |
重量ベース |
14% |
13% |
14% |
出典: 18 に基づき作成。野菜、果実、肉類、魚介類、油脂類はカロリーベースの公式な時系列データが限定的なため、重量ベースまたは生乳換算ベースで記載。総合食料自給率のカロリーベースと生産額ベースの乖離は、低カロリーだが高単価な野菜や魚介類の国内生産が多い一方、高カロリーな穀物や油脂の多くを輸入に依存する日本の食料供給構造を反映している。
1.2. 増幅される外部ショック
日本の食料システムは、国内の脆弱性に加え、グローバルな経済・地政学リスクに対して極めて脆弱な構造を持つ。特に2020年以降、「円安」「エネルギー高」「地政学リスク」という三つの外部ショックが相互に影響を増幅させ、食料価格を構造的に押し上げる複合的な圧力を生み出している。
円安とエネルギー高の二重苦
2024年には為替レートが1ドル=150円台に突入するなど、円安の長期化・常態化は、輸入に依存する日本の食料供給のアキレス腱を直撃した 5。小麦、大豆、とうもろこし、乳製品といった基礎的な食料・飼料の輸入価格は円安によって自動的に上昇し、国内の食品メーカーや外食産業のコストを圧迫している 5。企業のコスト上昇分を販売価格へ完全に転嫁することは難しく、帝国データバンクの調査によれば、コスト上昇分のうち「1~2割」しか転嫁できていない企業が最も多いのが実情である 25。
これに追い打ちをかけるのが、原油・エネルギー価格の高騰である。原油価格の上昇は、ガソリンや軽油といった輸送コストだけでなく、農業生産そのものにも深刻な影響を及ぼす 4。ハウス栽培で使用される暖房用の重油、トラクターを動かす軽油の価格が上昇する。さらに、原油を原料とするナフサから製造される化学肥料や農薬、農業用ビニールといった生産資材の価格も連動して高騰する 4。政府は燃油価格高騰に対する補填金制度などの支援策を講じているが 27、生産コスト全体の高騰を吸収するには至らず、多くの農家が自助努力の限界に直面している 26。
ここで重要なのは、「円安」と「原油高」が独立したリスクではなく、日本の食料生産コストを二重に締め上げる「悪魔の双子」として機能している点である。日本は原油のほぼ全量を輸入しており、円安はドル建ての原油輸入価格を直接引き上げる。その結果、上昇した原油価格は、国内の農業生産資材の価格を押し上げる(「円安→原油高→生産資材高」の連鎖)。同時に、円安は小麦や大豆といった輸入食料・飼料そのものの価格も直接引き上げる(「円安→輸入価格高」の連鎖)。このメカニズムにより、国内生産品と輸入品が同時に値上がりするという、消費者にとっても生産者にとっても逃げ場のない状況が生まれている。
地政学リスクとサプライチェーンの恒常的不安
かつて一時的なイベントと見なされていた地政学リスクは、今や世界の食料供給における恒常的な不確実性要因となっている。
2022年に始まったロシアによるウクライナ侵攻は、世界の穀物市場を揺るがした。その後、黒海を通じたウクライナの「穀物回廊」は部分的に機能し、2024年には輸出量が回復傾向を見せたが 29、戦争の影響による作付け面積の減少やインフラの破壊は続いており、2025年の収穫量は減少するとの予測もある 31。ウクライナ情勢は、世界の穀物需給をタイト化させる構造的な要因として継続している。
中東情勢の緊迫化も、食料安全保障に直接的な脅威となる。世界のエネルギー輸送の大動脈であるホルムズ海峡の封鎖や航行妨害といったリスクは、原油価格を高騰させるだけでなく、アジア・欧州間のコンテナ輸送コスト全体を押し上げ、食料を含むあらゆる物資のサプライチェーンを混乱させる 6。
こうした特定の紛争に加え、コロナ禍以降、世界はサプライチェーンの脆弱性を繰り返し経験してきた。世界的なコンテナ不足、港湾の混雑、自然災害や各国の突発的な輸出規制(例:ベトナムの米輸出一時停止)などにより、海上運賃は高騰し、物流の遅延が常態化した 8。
さらに、気候変動は、もはや「異常」気象ではなく、世界の主要穀倉地帯を毎年脅かす「常態」となりつつある。米国中西部では熱波や干ばつがトウモロコシや大豆の収量を脅かし 35、オーストラリアでは大規模な干ばつが小麦生産に壊滅的な打撃を与えるリスクが常に存在する 37。これらのリスクは、特定の年の「イベントリスク」から、世界の食料需給を構造的に引き締める要因へとその性質を変えつつある。世界銀行などの国際機関は、短期的な穀物価格の下落を予測しつつも、低所得国における食料不安の深刻化を警告しており 39、世界の需給バランスが極めて脆弱な状態にあることを示唆している。この「構造的タイト化」は、日本のような食料輸入大国にとって、平時であっても高値での調達を強いられ、少しの需給ショックで価格が急騰しやすいという、恒常的なリスク環境を意味する。
表B:食料価格に影響を与える主要経済指標の推移(2020~2025年)
|
指標 |
2020年 |
2021年 |
2022年 |
2023年 |
2024年 |
2025年(予測) |
|
為替レート (円/ドル、年平均) |
106.7 |
109.8 |
131.5 |
140.5 |
150.0 (推定) |
145-160 |
|
WTI原油価格 (ドル/バレル、年平均) |
39.2 |
68.1 |
94.9 |
77.6 |
80.0 (推定) |
80-100 |
|
FAO食料価格指数 (2014-16=100) |
98.1 |
125.7 |
143.7 |
124.0 |
120.4 (推定) |
115-125 |
|
消費者物価指数 (食料、前年比) |
+0.7% |
-0.1% |
+2.8% |
+7.5% |
+5.0% (推定) |
+2-4% |
出典: 4 及び各種経済統計データに基づき作成。2024年以降は推定値及び予測値。為替レートと原油価格の上昇が、数四半期遅れてFAO食料価格指数と国内の消費者物価指数(食料)に波及する傾向が見て取れる。
1.3. 流通業者のジレンマと戦略
生産者や海外要因によってもたらされたコスト上昇圧力が、最終的にどのような形で消費者価格に反映されるかを決定するのは、国内の巨大なサプライチェーンを掌握する大手卸・商社・小売業者の「思惑」と戦略的行動である。彼らは、「コスト上昇」と「消費者の節約志向」という二つのジレンマに挟まれながら、各々の利益最大化ロジックに基づき、日本の食料価格形成に絶大な影響力を行使している。
大手卸・商社の戦略:マージン確保とサプライチェーン支配
三菱食品や国分グループ本社といった大手食品卸は、物流費や人件費の増加という逆風の中、2023年度、2024年度と増収増益を確保している 42。これは、単にコストを吸収しているだけでなく、それを上回る価格転嫁と取引量の増加を実現していることを意味する。彼らの戦略は明確である。国分グループは経営方針の中で「価格改定による卸マージンの確保」を基本政策の一つとして明確に掲げており 45、コスト上昇分を小売業や食品メーカーに転嫁する強い意志を示している。
その一方で、彼らはコスト吸収努力も怠ってはいない。三菱食品は基幹システム(MILAI)の刷新に約100億円を投じ 46、国分グループはデジタル人材の育成や生成AIの活用を進めるなど 47、DX(デジタルトランスフォーメーション)を通じた業務効率化を加速させている。また、両社ともに物流子会社の設立や業界統一パレットの推進といった物流効率化にも注力している 45。しかし、こうした「持続可能な物流」の構築は、一面では業界全体の効率化に貢献するが、他面では卸が主導する物流システムへの依存度を高め、センターフィーなどの形でメーカー側のコスト負担を増大させる側面も持つ。結果として、卸のサプライチェーンにおける支配力が強化され、コスト負担がメーカーに転嫁される構造が温存・強化される可能性がある。
さらに、大手商社(例:丸紅)は、グローバルな規模でサプライチェーンの川上から川下までを支配する戦略を採る 48。米国の農業資材販売会社やブラジルの肥料会社を傘下に収め、生産資材の供給網をグローバルに押さえる 49。国内では穀物サイロを保有し、製油・飼料メーカーへ出資する。川上でのリスクヘッジと収益機会の最大化を図りながら、川下の食品流通にも深く関与することで、市場全体に対する影響力を確保している。
大手小売の戦略:PB強化と二極化による主導権争い
イオンやセブン&アイ・ホールディングスといった大手小売業者は、物価高に苦しむ消費者の節約志向を捉えることを最優先課題としている。その最大の武器が、PB(プライベートブランド)である。イオンは、低価格帯PBである「トップバリュ ベストプライス」において、2025年に過去最大規模となる75品目の値下げを断行した 50。海外の製造委託先を3年かけて新規開拓し、直輸入によって中間コストを徹底的に圧縮するなど、PBの価格競争力を極限まで高めようとしている 50。2025年度には約500アイテムのPB新商品・リニューアルを予定しており、この戦略をさらに加速させる方針だ 50。
このPB強化戦略は、NB(ナショナルブランド)を製造する食品メーカーに対して強烈な価格引き下げ圧力として機能する。小売業者は、低価格PBで集客力を高め、その交渉力をテコにしてNBメーカーからの仕入れ価格を引き下げようとする。
一方で、小売業者は単なる低価格競争に陥っているわけではない。セブン&アイは、高付加価値な「セブンプレミアム」ブランドや、出来立ての総菜・ベーカリーといった商品群を強化する一方で、低価格帯の「うれしい値!」商品を展開するなど、価格帯の異なる商品を揃えることで多様な顧客層を取り込む「二極化戦略」を推進している 53。
この大手小売による「PB強化」と、大手卸による「マージン確保」の動きは、日本の食品産業の構造に重大な影響を及ぼす。両者の戦略が衝突する中で、その圧力は、交渉力の弱い中堅・中小の食品メーカーに集中することになる。小売からはPBとの競争を理由に値下げを要求され、卸からは原材料・物流コストの上昇を理由に値上げを要求されるという「板挟み」の状態に陥るのである。この力学は、体力の乏しいメーカーの淘汰を促し、日本の食品市場が「巨大メーカーのNB」と「巨大小売のPB」に寡占化されていく未来を示唆している。これは消費者の選択肢の減少や、食文化の多様性の喪失といった、より深刻な「産業の空洞化」リスクを内包している。
表C:主要食品流通企業の戦略比較
|
企業名 |
事業領域 |
コスト上昇への対応策 |
サプライチェーン戦略 |
収益性(2023-24年度) |
|
三菱食品 |
卸売 |
・価格改定によるマージン確保 ・DX、物流効率化への投資 |
・三菱商事との連携強化 ・物流子会社設立 |
増収増益 42 |
|
国分グループ本社 |
卸売 |
・価格改定によるマージン確保 ・DX、生成AI活用 |
・国産原料活用 ・海外からの直接調達 |
増収増益、売上高2兆円突破 43 |
|
丸紅 |
総合商社 |
・グローバルなリスク分散 ・先物取引等でのヘッジ |
・川上(農業資材)から川下まで垂直統合 ・海外での生産・製造拠点保有 |
食料・アグリ事業は安定収益源 48 |
|
イオン |
小売 |
・低価格PB「ベストプライス」の徹底強化・値下げ ・直輸入、海外サプライヤー開拓 |
・PB商品の垂直統合的サプライチェーン構築 ・ディスカウントストア業態の拡大 |
PB戦略が奏功し、客数増に貢献 50 |
|
セブン&アイ |
小売 |
・PB「セブンプレミアム」の二極化戦略 ・高付加価値商品と低価格帯の併用 |
・グループ内での食品開発・供給体制 ・CVS事業とのシナジー |
グループ全体で増収増益 53 |
出典: 42 及び各社決算資料に基づき作成。
第2部:日本の食料安全保障の未来シナリオ(2025年秋~2028年)
第1部の構造分析を踏まえ、予測期間である2025年秋から2028年にかけて、日本の食料安全保障が直面しうる三つの異なる未来像をシナリオとして構築する。各シナリオにおいて、食料不足と物価高騰が品目別にどのような様相を呈するかを具体的に予測する。
2.1. シナリオA:現状維持・緩慢な悪化(ベースライン・シナリオ)
シナリオの定義:
本シナリオは、外部環境(為替、地政学リスク、気候)と国内政策(農業構造、減反政策)に劇的な変化がなく、2020年から2025年にかけて見られたトレンドが今後も継続するという想定に基づいている。これは、最も蓋然性が高いと考えられる未来像である。
前提条件:
- 経済: 為替レートは1ドル=140円~160円のレンジで不安定に推移。原油価格は1バレル=80ドル~100ドルで高止まりする。これらを受け、消費者物価指数(食料)は年率2~4%のペースで上昇を続ける 7。
- 国際情勢: ウクライナ紛争は低強度で継続し、同国の穀物輸出は不安定ながらも維持される 29。中東地域では散発的な緊張が続くものの、ホルムズ海峡の完全封鎖といった破局的な事態には至らない 6。
- 気候: 世界の主要穀倉地帯では毎年のように干ばつや洪水といった異常気象が発生するが、世界全体の穀物生産を壊滅させるような大規模災害は回避される 35。国内では、夏の猛暑が常態化し、米の品質低下や野菜の生育不良が頻発する 3。
- 国内政策: 食料安全保障強化に向けた政策は継続されるが、予算規模は限定的であり、減反政策の廃止といった生産構造の抜本的な改革には踏み込めない 11。農業従事者の高齢化と減少トレンドは継続する 13。
品目別予測と流通業者の動向:
- 米: 減反政策が継続されるため、国内の需給バランスは常にタイトな状況で推移する。夏の猛暑や台風被害があった年には、2024年と同様の価格高騰リスクを常に抱えることになる 10。外食・中食産業では、コスト削減のため、より安価な古米や複数産地のブレンド米、一部では輸入米の利用がさらに拡大する。
- 小麦・パン・麺類: 輸入小麦価格の高止まりが継続し、政府による売渡価格も高水準で維持される。製粉・製パン・製麺メーカーは、コスト上昇分を製品価格へ継続的に転嫁せざるを得ない。消費者の節約志向に対応するため、イオンの「早ゆでスパゲッティ」のような低価格PB商品が市場シェアを拡大する 50。一方で、付加価値の高い国産小麦を使用したパンやパスタは、品質を重視する層向けに価格がさらに上昇し、市場の二極化が一層鮮明になる。
- 肉類・乳製品: 輸入飼料穀物(とうもろこし等)の価格と円安の影響が生産コストを構造的に押し上げる。国内の牛肉自給率は微増傾向を維持するものの 18、安価なブラジル産鶏肉や米国・カナダ産豚肉への輸入依存構造に変化はない 58。食品メーカーは、価格を据え置きつつ内容量を減らす「シュリンクフレーション」を事実上の標準的な値上げ手法として継続する。大手小売は、集客の目玉としてPBの加工肉(ハム、ソーセージ)や牛乳を戦略的な価格で提供し、NBメーカーとの価格競争を仕掛ける。
- 水産物: 燃油価格の高騰が漁船の操業コストを圧迫し、円安が輸入水産物(ノルウェー産サーモン、ベトナム・インド産エビ等)の仕入れ価格を押し上げる。国内漁業の生産量は高齢化により減少傾向が続き、供給は先細りとなる。大手商社(丸紅など)が海外で展開する陸上養殖事業からの輸入品が、安定供給可能な食材としてスーパーの棚での存在感を増す 48。
- 野菜: 国内自給率が比較的高いため 60、価格は天候要因による短期的な変動が主な動きとなる。ただし、農業用資材の高騰 4 や物流2024年問題に起因する輸送費の上昇 45 が、価格のベースラインを全体的に押し上げる。調理の手間を省きたい共働き世帯や、人手不足に悩む外食産業からの需要増を背景に、カット野菜や冷凍野菜市場は着実に成長を続ける。
- 油脂類・加工食品: 日本が輸入に9割以上依存する大豆や菜種を主原料とするため、食用油の価格は高止まりが続く 20。マヨネーズ、ドレッシング、冷凍食品、菓子類といった加工食品は、油脂や小麦粉、砂糖といった複数の輸入原料コスト上昇の影響を複合的に受けるため、値上げが最も頻繁かつ広範に行われる分野となる。消費者の価格感度が最も高い分野でもあり、PB商品へのシフトが最も顕著に進むと予測される。
2.2. シナリオB:複合危機・パーフェクトストーム(悲観シナリオ)
シナリオの定義:
本シナリオは、想定される複数の重大なリスクが同時多発的に、あるいは連鎖的に発生し、日本の食料供給システムが機能不全の瀬戸際に立たされる世界である。これは、低確率ではあるものの、発生した場合の影響が極めて甚大となる最悪のケースを想定している。
前提条件:
- 経済: 米国の金融政策の急激な転換や国際的な金融不安を背景に、安全資産への逃避が起こり、逆に日本円が投機的な売りを浴びて急落(1ドル=180円以上)。世界経済は深刻なスタグフレーションに陥り、原油価格は1バレル=150ドル以上に高騰する。
- 国際情勢: 中東での地域紛争が全面戦争に拡大し、イランがホルムズ海峡を数週間にわたり封鎖する 6。同時に、中国による台湾への軍事的圧力が極度に高まり、台湾海峡や南シナ海のシーレーンが航行不能となる。これを受け、ロシアやインドといった主要食料輸出国が、自国の食料安全保障を優先し、穀物等の輸出を全面的に禁止する措置を発動する 8。
- 気候: 強力なラニーニャ現象の発生により、北米の穀倉地帯(小麦、大豆、とうもろこし)と南米(大豆、とうもろこし)で歴史的な大規模干ばつが同時に発生し、世界の穀物生産量が激減する 35。日本国内でも、スーパー台風の上陸や線状降水帯による豪雨が広範囲の農地に壊滅的な被害をもたらす。
- 国内政策: 突発的かつ複合的な危機に対し、政府の対応が後手に回る。食料の安定供給に関する基本法に基づく緊急事態宣言が発令されるが、政府備蓄の放出 61 は市場のパニック的な買い占めを抑制できず、すぐに枯渇の危機に瀕する。
品目別予測と流通業者の動向:
- 小麦・パン・麺類: 北米からの輸入が物理的に途絶し、深刻な供給不足が発生する。政府備蓄(約2.3ヶ月分)が放出されるが、需要を到底賄いきれず、数週間でパン、パスタ、うどん、ラーメンといった小麦製品が小売店の棚から完全に姿を消す。価格は数倍に急騰し、一部では闇市場での取引も横行する。米粉への代替需要が殺到し、米の需給も圧迫する。
- 油脂類・飼料穀物: 大豆、とうもろこしの輸入がストップし、食用油の供給は危機的状況に陥る。政府は家庭用食用油の購入を制限する措置(事実上の配給制)を検討せざるを得なくなる。飼料の供給が途絶したことで、国内の畜産業は壊滅的な打撃を受ける。
- 肉類・乳製品: 飼料不足と価格の異常高騰により、数ヶ月のうちに多くの養鶏・養豚農家が廃業に追い込まれる。鶏卵、鶏肉、豚肉の市場供給は激減し、価格は庶民の手の届かない水準まで跳ね上がる。牛乳の生産も大幅に減少し、学校給食の提供も困難になる。牛肉はごく一部の富裕層しか口にできない超高級品となる。
- 米: 小麦からの代替需要が殺到することで、国内の需給は極度に逼迫する。長年の減反政策によって国内の供給余力が削がれていたことが裏目に出て、政府が緊急増産を指示しても、収穫までには時間がかかり、当面の危機を救うことはできない。コメ不足を巡る社会不安が高まり、一部で暴動が発生するリスクも否定できない。
- 流通業者の動向: グローバルなサプライチェーンが寸断され、従来のビジネスモデルは完全に崩壊する。大手小売業者は、限られた在庫をPB商品として高値で販売し、自社の生き残りを図る。物流網は燃料不足とドライバー不足で麻痺し、特に地方や離島への食料供給が途絶する「フードデザート」問題が全国で深刻化する 13。買い占めや奪い合いが頻発し、店舗の治安維持が困難になる。
2.3. シナリオC:危機をバネにした構造転換(変革シナリオ)
シナリオの定義:
本シナリオは、シナリオBのような破局には至らないものの、ベースラインシナリオを超える深刻な危機感を社会全体が共有した結果、政府と民間が一体となって食料安全保障の抜本的な構造改革に踏み切る世界である。危機が変革の触媒として機能する、希望を含んだ未来像である。
前提条件:
- 経済・国際情勢: ベースラインシナリオと悲観シナリオの中間程度の危機が発生。例えば、円安が一時的に1ドル=170円台に達し、アジア地域での局地的な紛争によって物流が数週間混乱する。これにより、輸入食料の価格が急騰し、国民生活に明確な打撃が与えられる。
- 国内政策: この危機を受け、「食料は海外から安く買えばよい」という長年の常識が完全に崩壊。強い世論を背景に、政権は食料安全保障を国家存立の基盤と位置づけ、歴史的な政策転換を決断する。
- 減反政策の完全廃止と水田フル活用: 米の生産調整を完全に廃止し、国内での最大限の増産を奨励する。余剰分は政府が買い上げ、輸出、飼料用、加工用、そして平時の倍以上の規模での備蓄に回すという、専門家が提言してきた政策(10)を実践する。
- 食料安保特区の創設と大規模投資: 耕作放棄地の再生や、スマート農業技術(ドローン、自動運転トラクター等)の導入に対する規制を大幅に緩和し、集中的な財政支援を行う 11。
- 国産資源循環の推進: 飼料用米や食品残渣を利用したエコフィード、下水汚泥など国内の未利用資源を活用した肥料生産を国策として強力に推進する。
- 民間企業の動向: 政府の明確な方針転換を長期的なビジネスチャンスと捉え、大手総合商社や食品メーカーが国内農業への大規模投資を本格化させる。具体的には、大規模な農業生産法人への出資、天候に左右されない植物工場、細胞培養による代替タンパク質、そして陸上養殖といった次世代の食料生産技術への投資が急加速する 48。
品目別予測と流通業者の動向:
- 米: 減反廃止により、国内の米生産量は大幅に増加する。短期的には生産者の所得を補償するための財政コストが発生するが、中長期的には米価は需給緩和によって安定し、国民の主食が手頃な価格で確保される。生産された米の一部は飼料用米として畜産業に供給され、生産コストの削減に貢献する。
- 小麦: 政府の支援を受け、国産小麦の生産が飛躍的に増加。自給率は現在の17%から30%程度まで向上する。パンや麺類において、「安全・安心な国産プレミアム」市場が確立され、輸入小麦との棲み分けが進む。
- 肉類・乳製品: 飼料用米や国産エコフィードの利用が拡大することで、生産コストの外部環境(為替、国際相場)への依存度が低下し、価格の安定性が高まる。鶏肉や豚肉の自給率も緩やかに上昇に転じる。
- 流通業者の動向: これまでの「安価な輸入品をいかに効率よく調達・販売するか」というビジネスモデルから、「安定した国内生産基盤にいかに投資し、付加価値をつけて販売するか」という新たなビジネスモデルへの戦略転換(パラダイムシフト)が起こる。大手卸や小売が生産者と長期的な栽培・買取契約を結ぶ「契約農業」モデルが主流となり、生産・流通・販売が一体となったサプライチェーンが構築される。生産から消費までのデータ連携が進み、需給予測の精度が向上し、食品ロスも削減される。
第3部:シナリオの比較分析と自己検証
3.1. 未来の分岐点
第2部で提示した三つのシナリオは、それぞれ異なる未来像を描き出す。どの未来が現実となるかは、いくつかの重要な「分岐点(クリティカル・ジャンクチャー)」に左右される。ここでは、各シナリオを客観的な指標で比較し、未来を決定づける要因を特定する。
表D:3シナリオの定性的・定量的比較(2025-2028年予測)
|
比較軸 |
シナリオA:現状維持・緩慢な悪化 |
シナリオB:複合危機・パーフェクトストーム |
シナリオC:危機をバネにした構造転換 |
|
食料CPI上昇率 (年平均) |
2~4% |
10%超 |
4~6% (短期) → 1~2% (中期) |
|
主要品目自給率 (小麦) |
15~18% (横ばい) |
測定不能 (輸入途絶) |
25~30% (上昇) |
|
政府備蓄の役割 |
平時の価格安定機能 |
緊急時の配給機能 (枯渇リスク) |
戦略的バッファー機能 (増強) |
|
円/ドルレート (予測レンジ) |
140~160円 |
180円超 |
130~150円 (中期的安定) |
|
サプライチェーンの脆弱性 |
高い (脆弱性が放置される) |
極めて高い (寸断される) |
低下 (国内回帰・多元化が進む) |
|
食料アクセス問題 |
都市部で緩やかに進行 |
全国で深刻化 |
改善 (国内生産・物流が強化) |
|
政府の政策対応 |
対症療法的・小規模 |
後手・機能不全 |
抜本的・構造改革的 |
|
流通業者のビジネスモデル |
PB強化・二極化・コスト転嫁 |
機能停止・サバイバル |
国内生産投資・契約農業 |
この比較から、未来を左右する最も重要な分岐点は、以下の二つであることが明らかになる。
- 外部ショックの規模と連鎖: シナリオAとシナリオBを分かつ最大の要因は、海外で発生する経済危機、地政学的紛争、異常気象といった外部ショックが、単発で終わるか、あるいは複合的に連鎖して「パーフェクトストーム」となるかである。特に、為替レートの急激な変動(円の暴落)と主要シーレーンの機能不全は、日本の食料供給システムを麻痺させるトリガーとなりうる。
- 国内の政策的決断: シナリオAとシナリオCを分かつのは、危機に対する国内の政治的・社会的な反応である。特に、食料安全保障上のリスクと農家所得維持との間で長年揺れ動いてきた**「米の減反政策」の存廃**は、日本の農業構造を根本から変えうる、象徴的かつ実質的な分岐点となる。危機感が醸成され、この「聖域」に踏み込む政治的決断がなされるかどうかが、緩慢な悪化を続けるか、構造転換への道を歩むかを決定づける。
3.2. 分析の脆弱性評価(自己批判的アプローチ)
本レポートの分析は、入手可能なデータと論理的推論に基づいているが、未来予測に絶対はなく、常に不確実性を内包する。分析の信頼性を高めるため、本分析が依拠する前提条件の脆弱性や、見落としている可能性のある変数を自己批判的に検証する。
- 前提条件の妥当性に関する問い: 本分析は、予測期間を通じて「円安基調」が継続することを主要な前提としている。しかし、日本銀行の金融政策の急転換や、米国の深刻な景気後退によって、予測に反して急激な「円高」に振れる可能性はないだろうか。その場合、輸入食料や生産資材の価格は下落し、物価高騰圧力は緩和される。しかし、それは同時に国内のデフレ圧力の再燃を意味し、農産物価格の下落を通じて国内生産者の経営を圧迫するという、全く異なる種類の問題を引き起こす可能性がある。この円高シナリオへの考察が本分析では手薄である。
- 因果関係の見落としに関する問い: 本分析では、流通業者の戦略的意図を重要な変数として分析した。しかし、その対極にいる消費者の行動変容が需給バランスに与える影響を過小評価していないだろうか。例えば、食料危機への意識の高まりから、各家庭での食料備蓄がブームとなれば、短期的に需要が急増し、品薄に拍車をかける可能性がある。逆に、健康志向や節約志向から、より質素な食生活(例:肉食を減らし、野菜や豆類中心へ)へのシフトが起これば、輸入飼料穀物への依存度が低下し、需給緩和に繋がるかもしれない。こうした消費者の能動的な変化は、本分析のモデルに十分に組み込まれていない。
- ワイルドカード(予測不能な大変数)の存在に関する問い:
- 技術的ブレークスルー: 細胞培養肉やゲノム編集技術、あるいは垂直農法といった革新的な農業技術が、予測期間中に想定をはるかに超えるスピードで低コスト化し、社会実装される可能性はないか。もし実現すれば、土地や気候への依存を断ち切り、食料供給のパラダイムを根本から変える可能性がある。
- 地政学的好転: 予測が困難なポジティブなサプライズとして、ロシア・ウクライナの電撃的な停戦合意や、米中対立の劇的な緩和といった、地政学リスクが急速に解消される可能性はゼロではない。
- これらのワイルドカードは、本分析の前提を覆し、全く異なる未来をもたらす可能性がある。
- 分析バイアスの問い: 本レポートは、マクロなデータと構造的な問題を重視するあまり、現場レベルでのレジリエンス(回復力)を過小評価しているのではないか。例えば、個々の農家や中小企業が、創意工夫によって新たな販路を開拓したり、地域内で資源を循環させる小規模なネットワークを構築したりといった、ボトムアップの強靭化の動きを見過ごしている可能性がある。分析の視点が、やや悲観論に偏っている可能性は否定できない。
第4部:結論と専門家による検証項目
4.1. 総合的結論
本分析を通じて得られた総合的な結論は以下の通りである。
予測期間(2025年秋~2028年)、日本は**シナリオA(現状維持・緩慢な悪化)**をたどる可能性が最も高い。食料価格は高止まりを続け、国民の生活防衛意識は一層高まる。この消費者動向に対応するため、大手流通・小売業者は低価格PBの強化と高付加価値品の二極化戦略をさらに推し進め、その結果としてNBを主力とする中堅・中小食品メーカー間の経営格差は拡大するだろう。
しかし、このシナリオAは極めて脆弱な均衡の上に成り立っている。国内の生産基盤の弱体化が続く中で、世界的な気候変動の激化や地政学的リスクの増大といった外部からのショックに対する耐性は著しく低下している。そのため、日本は常に**シナリオB(複合危機・パーフェクトストーム)**へと転落するリスクと隣り合わせの状態にあると言える。
**シナリオC(危機をバネにした構造転換)**への移行は、食料安全保障を国家の最優先課題とする強い政治的リーダーシップと、痛みを伴う改革を許容する国民的な合意形成が不可欠である。しかし、現状ではその機運は十分に高まっているとは言い難い。深刻な危機が現実のものとなるまで、減反政策の見直しといった抜本的な改革は先送りされ続ける可能性が高い。
したがって、日本は今後数年間、食料を巡る「静かなる危機」の中を、綱渡りの状態で進んでいくことになるだろう。
4.2. 専門家向けチェックリスト
本レポートの妥当性と信頼性を検証する際に、他の専門家が用いるべき論点(チェックリスト)を以下に提示する。
- データと前提の検証
- 本分析が依拠する食料自給率 23、消費者物価指数 63、企業決算 42 等の基礎データは最新であり、その解釈は適切か?
- 各シナリオで設定された前提条件(為替、原油価格、地政学リスク等)は、他の主要なマクロ経済予測と比較して、妥当な範囲内に設定されているか?
- 因果モデルの検証
- 「円安・原油高 → 生産資材高 → 国内生産コスト増」という因果連鎖の感応度(インパクトの大きさ)は、どの程度と見積もるべきか?より定量的な分析は可能か?
- 「小売PB強化 vs 卸マージン確保 → メーカーへの圧力」という流通構造の力学分析は、業界の実態を正確に反映しているか?大手メーカーの交渉力や、業態(コンビニエンスストア、スーパーマーケット、ディスカウントストア)による戦略の違いは十分に考慮されているか?
- 政策評価の検証
- 政府が打ち出している食料安全保障強化策 11 の実効性に関する本レポートの評価は、客観的か?あるいは悲観的・楽観的に偏りすぎていないか?予算配分の詳細な分析に基づいた、より精緻な評価は必要ないか?
- 米の減反政策に対する評価 10 は、食料安全保障という単一の視点に偏っており、農村社会の維持や国土・環境保全といった農業の多面的機能に関する考察を見落としていないか?
- 分析の死角の検証
- 「食の外部化」(中食・外食への依存)の進展が、家庭内での食料備蓄の量や、消費者の価格感度に与える影響は分析されているか?
- 食品ロス削減に向けた技術や社会システムの進展が、実質的な供給量を増やし、需給緩和に与えるポジティブな影響は考慮されているか?
- 労働市場の変化、特に特定技能などの在留資格による外国人材の受け入れ拡大が、人手不足が深刻な農業や食品加工業の生産性に与える影響は、十分に織り込まれているか?
引用文献
- 農地の現状 – アグリウェブ, 8月 3, 2025にアクセス、 https://www.agriweb.jp/knowledge/1229.html
- 農家の高齢化と耕作放棄地増加はなぜ問題?農業や地域に還元するアンスリーファームの活動も紹介, 8月 3, 2025にアクセス、 https://anthreefarm.co.jp/archives/348
- 令和5年 地球温暖化影響調査レポート – 農林水産省, 8月 3, 2025にアクセス、 https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/ondanka/attach/pdf/index-154.pdf
- 燃料や肥料、農業資材の原料となる原油価格が高騰!原油高が農業に与える影響。, 8月 3, 2025にアクセス、 https://www.kaku-ichi.co.jp/media/tips/column/impact-of-high-crude-oil-prices-on-agriculture
- 2025年の食品業界はどうなる?円安&物価上昇の衝撃と生き残る企業の戦略とは, 8月 3, 2025にアクセス、 https://food-town.jp/customer/news/detail/483
- 【2025年】中東の地政学リスクが世界経済と企業戦略を直撃する構図 | 貿易ドットコム, 8月 3, 2025にアクセス、 https://boueki.standage.co.jp/geopolitical-risk-in-the-middle-east/
- 統計局ホームページ/消費者物価指数(CPI) 全国(最新の月次結果の概要), 8月 3, 2025にアクセス、 https://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/tsuki/index-z.html
- 新型コロナウィルス感染拡大に伴うサプライチェーンへの影響とその対応策 – 財務省, 8月 3, 2025にアクセス、 https://www.mof.go.jp/pri/publication/research_paper_staff_report/staff06.pdf
- リスクの高まり:イラン紛争がサプライチェーンに連鎖的に及ぼす影響 | project44, 8月 3, 2025にアクセス、 https://www.project44.com/ja/supply-chain-insights/escalating-risks-the-ripple-effect-of-the-iran-conflict-on-supply-chains/
- 食料安全保障に矛盾する米政策 – キヤノングローバル戦略研究所, 8月 3, 2025にアクセス、 https://cigs.canon/article/20241212_8506.html
- 2025年の日本の農業はどうなる? 「令和7年度農水概算要求」に見るスマート農業の役割, 8月 3, 2025にアクセス、 https://smartagri-jp.com/agriculture/9652
- 日本の農業の課題とは?現状と解決へのアプローチ [2025] – Asana, 8月 3, 2025にアクセス、 https://asana.com/ja/resources/challenges-faced-by-japanese-agriculture
- 農林水産 – 財務省, 8月 3, 2025にアクセス、 https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20241111/01.pdf
- 10年後の農業はどうなる? 経営者が取り組むべき課題と日本が描く農業の未来像, 8月 3, 2025にアクセス、 https://minorasu.basf.co.jp/80431
- 眠っている耕作放棄地がお金を生む?問題点から解決策までご紹介 – 自然電力, 8月 3, 2025にアクセス、 https://shizenenergy.net/re-plus/column/agriculture/abandoned_farmland/
- 耕作放棄地の現状と課題 – 農林水産省, 8月 3, 2025にアクセス、 https://www.maff.go.jp/j/study/nouti_seisaku/senmon_04/pdf/data6.pdf
- 温暖化による気候変動・大規模自然災害の増加 – 環境省, 8月 3, 2025にアクセス、 https://chushikoku.env.go.jp/content/000081244.pdf
- 令和4年度食料需給表・食料自給率について – 農畜産業振興機構, 8月 3, 2025にアクセス、 https://www.alic.go.jp/joho-c/joho05_002917.html
- 2020年度食料自給率は過去最低水準、新型コロナの影響か? – Sakanadia(サカナディア), 8月 3, 2025にアクセス、 https://sakanadia.jp/torikumi/jikyuritsu_2020/
- 日本の食料自給率|現状のリスクと取るべき対策とは, 8月 3, 2025にアクセス、 https://www.cherpa.co.jp/column/foodself-sufficiency-rate/
- 【農林水産省】「令和5年度食料自給率・食料自給力指標」および「令和5年度食料需給表」を公表, 8月 3, 2025にアクセス、 https://www.dietitian.or.jp/trends/2024/376.html
- 【農林水産省】「令和4年度食料自給率・食料自給力指標」および「令和4年度食料需給表」を公表, 8月 3, 2025にアクセス、 https://www.dietitian.or.jp/trends/2023/302.html
- 食料需給表:農林水産省, 8月 3, 2025にアクセス、 https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/fbs/index.html
- 【2025年】円安はいつまで?これからの見通しやデメリットなどをわかりやすく解説 – 伊予銀行, 8月 3, 2025にアクセス、 https://www.iyobank.co.jp/sp/iyomemo/entry/20220628.html
- 円安基調の影響、コスト上昇と価格転嫁に関する アンケート調査, 8月 3, 2025にアクセス、 https://www.tsukubabank.co.jp/corporate/info/monthlyreport/pdf/2024/11/202411_06.pdf
- 生産資材高騰等に関する意見書 世界的な穀物需給の逼迫, 8月 3, 2025にアクセス、 http://www.city.nayoro.lg.jp/assembly/ii35kh000000curb-att/ii35kh000000cvvz.pdf
- 農業分野における燃油・資材価格高騰への対応について – 埼玉県, 8月 3, 2025にアクセス、 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0903/koutou.html
- 令和7年度 原油価格・物価高騰等対策【特設ページ】 – ひなたMAFiN, 8月 3, 2025にアクセス、 https://hinatamafin.pref.miyazaki.lg.jp/soshiki/noseikikakuka/bukkakoutou/2644.html
- 混迷するウクライナの農業と農業ビジネス – 農林水産省, 8月 3, 2025にアクセス、 https://www.maff.go.jp/primaff/about/kenkyuin/attach/pdf/2025_goto_1.pdf
- 3年ぶりに輸出が増加、穀物や鉱石などが寄与(ウクライナ) – ジェトロ, 8月 3, 2025にアクセス、 https://www.jetro.go.jp/biznews/2025/03/a6aea351f3126fec.html
- 食料供給の危機…ウクライナ産穀物の輸出合意をロシアが停止 小麦など価格高騰で「日本の食卓」への影響は?【サンデーモーニング】|TBS NEWS DIG – YouTube, 8月 3, 2025にアクセス、 https://www.youtube.com/watch?v=dXSYbpprwFY
- 戦争と天候がウクライナの収穫を脅かし、2025年には大幅な減少が予想される – Gazeta Express, 8月 3, 2025にアクセス、 https://www.gazetaexpress.com/ja/lufta-dhe-moti-kercenojne-te-korrat-ne-ukraine-pritet-renie-e-ndjeshme-ne-2025/
- コロナ禍や災害でサプライチェーンが混乱(フィリピン) | アジアのサプライチェーンをめぐる事業環境, 8月 3, 2025にアクセス、 https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/special/2022/1101/957a89545feaec52.html
- ASEANでの新型コロナ禍を振り返る(後編)サプライチェーン寸断・停滞の影響を再認識、リスク分散・低減に向け対応へ – ジェトロ, 8月 3, 2025にアクセス、 https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/special/2020/0901/d4fb00237115fc57.html
- 米国の大豆生産への気候変動の影響(1), 8月 3, 2025にアクセス、 https://www.sugiyama-c-i-l.or.jp/topics/climate_change/climate_change_03.html
- 米国トウモロコシの作柄は気温上昇により例年に比べやや不良 – 農畜産業振興機構, 8月 3, 2025にアクセス、 https://www.alic.go.jp/chosa-c/joho01_000450.html
- 温暖化がもたらす深刻な将来影響 – 食料 中緯度から高緯度の地域では、地域の平均気温が, 8月 3, 2025にアクセス、 https://www.env.go.jp/earth/ondanka/stop2008/12-13.pdf
- 資料4 オーストラリアにおける干ばつの状況について, 8月 3, 2025にアクセス、 https://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0426pdf/ks042611.pdf
- 一次産品価格の下落が貿易摩擦によるインフレリスクを緩和する可能性 – World Bank, 8月 3, 2025にアクセス、 https://www.worldbank.org/ja/news/press-release/2025/04/29/commodity-markets-outlook-april-2025-press-release
- 世界銀行による食料安全保障2025見通し | 世界の飢餓ニュース – ハンガーゼロ, 8月 3, 2025にアクセス、 https://www.hungerzero.jp/news/2025/20250204_00627.html
- 2020年基準 消費者物価指数 全国 2025年(令和7年)6月分 – 総務省統計局, 8月 3, 2025にアクセス、 https://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/tsuki/pdf/zenkoku.pdf
- 三菱食品(株)【7451】:決算情報 – Yahoo!ファイナンス, 8月 3, 2025にアクセス、 https://finance.yahoo.co.jp/quote/7451.T/financials
- 国分グループ本社「2024年連結決算、連続増収増益」 – フードボイス, 8月 3, 2025にアクセス、 https://fv1.jp/97029/
- 【速報】国分グループ本社、23年度決算で初の売上高2兆円 経常利益率1%超え, 8月 3, 2025にアクセス、 https://news.nissyoku.co.jp/flash/1000450
- 国分グループ、2024 年度の経営結果と2025 年度の経営方針, 8月 3, 2025にアクセス、 https://www.kokubu.co.jp/uploads/e069aa3c20d5d2c277da31f756b9147e88742920.pdf
- 三菱食品株式会社 2025年3月期 第2四半期決算 … – Cloudfront.net, 8月 3, 2025にアクセス、 https://d2nyjryheal9w7.cloudfront.net/672c5ad142f074ed1dcf118c/2025%E5%B9%B4%EF%BC%93%E6%9C%88%E6%9C%9F%E3%80%80%E7%AC%AC%EF%BC%92%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E3%80%80%E6%B1%BA%E7%AE%97%E8%AA%AC%E6%98%8E%E8%B3%87%E6%96%99.pdf
- 国分グループ本社 決算/24年度売上高2兆1573億円、過去最高を更新 | 流通ニュース, 8月 3, 2025にアクセス、 https://www.ryutsuu.biz/accounts/r022716.html
- 食料・アグリ部門 | 事業紹介 | 丸紅株式会社 – Marubeni, 8月 3, 2025にアクセス、 https://www.marubeni.com/jp/business/food_agri/
- できないことは、みんなでやろう。 – 米国、ブラジルで展開するアグリ事業, 8月 3, 2025にアクセス、 https://www.marubeni-recruit.com/business/project02.html
- イオン/PB「トップバリュ」75品目を値下げ、4/9から | 流通ニュース, 8月 3, 2025にアクセス、 https://www.ryutsuu.biz/commodity/r20250402004.html
- 物価高に逆行…75品目で”値下げ” あえて行うイオン戦略 売り上げ好調のPB商品とは – YouTube, 8月 3, 2025にアクセス、 https://www.youtube.com/watch?v=DW1iYT0gNpU
- イオン 価格政策を推進し客数増目指す 「トップバリュ」徹底的に強化 – 食品新聞, 8月 3, 2025にアクセス、 https://shokuhin.net/119579/2025/04/14/ryutu/kouri/
- 2024年度 決算説明資料 – セブン&アイ・ホールディングス, 8月 3, 2025にアクセス、 https://www.7andi.com/ir/file/library/ks/pdf/2025_0409ks_01.pdf
- 2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結), 8月 3, 2025にアクセス、 https://finance-frontend-pc-dist.west.edge.storage-yahoo.jp/disclosure/20250508/20250508534879.pdf
- (株)セブン&アイ・ホールディングス【3382】:株価・株式情報 – Yahoo!ファイナンス, 8月 3, 2025にアクセス、 https://finance.yahoo.co.jp/quote/3382.T
- 【農林水産省に聞く】農業分野における気候変動の影響の実態と、これからの付き合い方, 8月 3, 2025にアクセス、 https://agri.mynavi.jp/2025_05_10_308405/
- 食料安全保障強化と農業の持続的発展へ構造転換注力:2025年度予算、農林水産省関係, 8月 3, 2025にアクセス、 https://www.policynews.jp/ministries_and_agencies/2025/budget_2025_maff.html
- 2月の鶏肉および豚肉輸出が前年同月比で増加(ブラジル) | ビジネス短信 – ジェトロ, 8月 3, 2025にアクセス、 https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/03/35aee66c51067cff.html
- ブラジルの鶏肉生産・輸出動向 – 農畜産業振興機構, 8月 3, 2025にアクセス、 https://www.alic.go.jp/content/000144738.pdf
- 【2024年最新】令和4年度の日本の食料自給率が発表! – ロスゼロ, 8月 3, 2025にアクセス、 https://losszero.jp/blogs/column/col_149
- 食料安全保障について – 農林水産省, 8月 3, 2025にアクセス、 https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/anpo/
- 日本の食料安全保障 -食料安定供給の確保に向けて – 参議院常任委員会調査室・特別調査室, 8月 3, 2025にアクセス、 https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2023pdf/20231101083.pdf
- 経済統計を利用できるサイトへのリンク集, 8月 3, 2025にアクセス、 http://web.tku.ac.jp/~nakamura/toukeia/links.html
- 2024年度決算説明資料 – セブン&アイ・ホールディングス, 8月 3, 2025にアクセス、 https://www.7andi.com/ir/file/library/ks/pdf/2025_0409ks_02.pdf

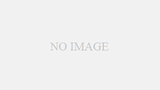
コメント