1. エグゼクティブサマリー
本レポートは、2024年以降の日本における米価格高騰の多角的要因を、供給、需要、市場構造、国際情勢の各側面から詳細に分析し、具体的な数値データに基づいた知見を提供する。主要な結論として、2023年産米の異常気象による供給ショックと品質低下が起点となり、長年の減反政策による供給の脆弱性、農業生産コストの高騰、一時的な需要増加、そして流通市場の不透明性が複合的に作用し、価格高騰を増幅させたことを指摘する。
2024年以降の米価格高騰の概況として、2024年産米の「相対取引価格」は1993年の「平成の米騒動」時の年平均価格を上回る25,927円/60kgに達し、高止まりしている状況が確認されている 1。小売価格においても、「コシヒカリ5kg」の2024年12月の店頭小売価格(東京都区部)は4,018円と、前年同月(2,422円)比で1.68倍に高騰するなど、消費者に直接的な影響を与えている 2。この価格上昇は、消費者物価指数(CPI)においても顕著な寄与を示し、2025年6月には米類だけでCPI総合を+0.61%ポイント押し上げ、年間10,673円もの家計負担増につながっている 3。
主要な要因としては、まず2023年産の記録的な猛暑による不作と品質低下が挙げられる。これにより、民間在庫が歴史的低水準にまで減少した 5。次に、肥料や燃料費などの農業生産資材の継続的な高騰が生産コストを押し上げ、米価上昇の構造的要因となっている 1。さらに、新型コロナウイルス感染症の収束に伴う外食需要やインバウンド(訪日客)の急増、他食料品との相対的な割安感、そして災害警戒や品薄報道による一時的な備蓄需要や買い占め行動が、限られた供給量に対する需要圧力を急増させた 5。加えて、米流通の構造的課題、特に「自由化による不可視化」と投機的行動が価格上昇に拍車をかけた 10。世界最大の米輸出国であるインドの輸出規制も、国際市場を通じて間接的に国内価格に影響を与えている 13。
今後の見通しとしては、2024年産米の予想収穫量は679.2万トンと2023年産を18.2万トン上回る見込みであり、作況指数も101(平年並み)と回復基調にある 1。これにより、民間在庫は回復に向かうと予測されている 18。しかし、生産コストの高止まりや市場心理の慣性から、根本的な価格下落は期待できない状況である 6。中長期的には、気候変動適応型農業への転換、生産コスト上昇への対策、流通構造の透明化、政府備蓄米の柔軟な運用、そして新たな米需要創出に向けた政策的支援が不可欠である。これらの複合的な課題に対処することで、日本の食料安全保障と持続可能な米生産の未来を確保することが可能となる。
2. はじめに
本レポートの背景と重要性
2024年以降、日本国内で米の価格が著しく高騰し、消費者、農家、食品産業全体に広範な影響を及ぼしている。この現象は単一の要因によるものではなく、複数の複雑な要素が絡み合って発生しており、その本質を理解するためには多角的な視点からの詳細な分析が不可欠である。米は日本人の主食であり、その価格変動は国民生活に直接的な影響を与えるため、この問題の包括的な分析は喫緊の課題となっている。本レポートは、この課題に対し、専門家レベルの知見と具体的な数値データに基づいた包括的な分析を提供するものである。
2024年以降の米価格高騰が日本社会に与える影響
米価格の高騰は、まず家庭の食費負担増大という形で消費者に直接影響を及ぼしている 4。特に低所得世帯にとっては、生活必需品である米の価格上昇は家計を圧迫し、他の消費を抑制せざるを得ない状況を生み出している。これは社会的な公平性の観点からも懸念される事態である。また、外食産業や食品加工業においては、業務用米の価格上昇がコスト増に直結し、価格転嫁や経営圧迫を引き起こしている 5。これにより、外食料金の値上げや加工食品の価格上昇が進み、最終的に消費者の財布を圧迫する連鎖が生じている。
農家にとっては、米価の上昇が直接的な利益となるとは限らず、生産コストの増加や需要の変動が大きなリスクとなっている 5。肥料や燃料などの農業生産資材の価格高騰は、農家の経営を困難にし、持続可能な農業の維持にも警鐘を鳴らしている。中小規模の農家にとっては、倒産の危機が現実のものとなっているとの指摘もある 5。さらに、食料安全保障の観点からも、国内主要食料の価格不安定化は重要な課題であり、自給率の維持と安定供給の確保に向けた政策的対応が求められている。
分析のスコープとアプローチ
本レポートでは、2024年から現在までの期間に焦点を当て、米価格高騰の要因を「供給サイド」「需要サイド」「市場構造と流通」「国際市場の動向」の四つの主要な側面から分析する。各要因については、農林水産省、総務省などの公的機関が発表する統計データや、各種研究機関、報道機関が提供する最新の数値データを最大限に活用し、その因果関係や相互作用を深く掘り下げる。これにより、多角的な視点から米価格高騰の複雑なメカニズムを解明し、今後の政策立案や市場戦略に資する知見を提供することを目指す。
3. 2024年以降の米価格動向の概観
3.1. 相対取引価格の推移と歴史的比較
2024年以降、日本における米の相対取引価格は顕著な高騰を示している。2024年産米の「相対取引価格」は60kgあたり25,927円に達したと報告されている 1。この価格は、2024年12月の24,665円をさらに上回る水準である 1。この価格水準を歴史的に比較すると、調査手法は異なるものの、1993年に発生した「平成の米騒動」時の年平均価格を上回ったとされている 1。
米の相対取引価格は、JAなどの集荷団体が農家に支払う「概算金」(仮払金)に、保管、運送、検査費用などの流通経費を加えたもので構成される 19。この概算金は、国の政策や政治的配慮によって決定される側面があり、市場の需要と供給のバランスだけで完全に決定されるわけではない 19。しかし、近年の光熱動力費が2020年平均と比べて1.3倍、肥料代が1.4倍に上昇するなど、生産コストの増加が概算金の上昇に影響を与え、結果として相対取引価格の高止まりにつながっている 1。
2024年産米の相対取引価格が「平成の米騒動」時の水準を超えたという事実は、今回の米価高騰が単なる一時的な需給の変動ではなく、歴史的に見ても極めて深刻な事態であることを示唆している。これは、需給バランスの崩壊だけでなく、生産コストの構造的上昇が背景にあることを強く示唆するものである。相対取引価格は精米前の玄米の価格であり、その後の小売価格の動向を予測する上で重要な先行指標となる 19。この価格の高止まりは、小売価格も当面高水準で推移する可能性が高いことを示している 1。
Table 3.1.1: 主要年次における米の相対取引価格推移(2020年~2024年)
|
年次 |
相対取引価格(円/60kg) |
前年比(%) |
備考 |
|
2020 |
N/A |
N/A |
光熱動力費、肥料代の基準年 |
|
2023 |
N/A |
N/A |
2024年12月価格:24,665円 1 |
|
2024 |
25,927 |
N/A |
「平成の米騒動」年平均価格を上回る 1 |
注記: 提供された情報に基づき、具体的な年次ごとの相対取引価格の連続データは限られているため、一部はN/Aとしている。2024年産米の価格は、2024年12月の価格をさらに上回る最新のデータである。
3.2. 店頭小売価格の動向と消費者への影響
相対取引価格の高騰は、消費者が直接購入する店頭小売価格にも明確に転嫁されている。総務省「小売物価統計調査」によると、「コシヒカリ5kg」の2024年12月の店頭小売価格(東京都区部)は4,018円であった 2。これは前年同月の2,422円と比較して1.68倍という大幅な上昇である 2。
主要銘柄の価格上昇は広範囲に及んでいる。食品スーパーのPOSデータでは、3年ほど前まで1kgあたり400円を切っていた茨城コシヒカリや北海道ななつぼしが、現在では1kgあたり700円以上(5kgで3,500円以上)まで相場が上昇している 20。この価格上昇は、精米過程での目減り(玄米1kgが精米で約0.9kgになるため、精米1kgあたりの価格は玄米価格より高くなる)や、加工賃、流通経費、粗利が上乗せされることによって形成される 21。2022年のデータでは、精米1kgあたりの卸売コストが35.1円、小売コストが55.8円とされており、これに物価上昇が加味されている 21。
相対取引価格の上昇が直接的に店頭小売価格に転嫁されていることは、消費者の購買力に大きな打撃を与えていることを明確に示している。特に、コシヒカリのような主要銘柄での1.68倍という価格上昇は、米が日常的な消費財であるため、家計への影響が広範かつ継続的であることを意味する。米の消費量は価格弾力性が低いとされ、価格が上がっても消費量が大きく減少しにくい特性があるため、価格転嫁が比較的容易に進みやすい市場構造がある 22。しかし、今回の高騰は消費者の「買い控え」や「代替品への移行」を促す水準に達している可能性があり、長期的な米離れを加速させるリスクを内包している 23。
Table 3.2.1: 主要銘柄米の店頭小売価格推移(2023年~2024年)
|
年月 |
銘柄/単位 |
小売価格(円) |
前年同月比(%) |
|
2023年12月 |
コシヒカリ5kg |
2,422 |
N/A |
|
2024年12月 |
コシヒカリ5kg |
4,018 |
+68.4 |
|
現在 |
茨城コシヒカリ1kg |
700以上 |
N/A |
|
現在 |
北海道ななつぼし1kg |
700以上 |
N/A |
注記: コシヒカリ5kgのデータは東京都区部における店頭小売価格 2。茨城コシヒカリ、北海道ななつぼしのデータはPOSデータに基づく1kgあたりの相場 20。
3.3. 消費者物価指数(CPI)への寄与と家計負担
米類の価格上昇は、個別の家計問題に留まらず、日本全体のインフレ圧力の重要な構成要素となっている。2025年6月の消費者物価指数(CPI)を見ると、米類の価格は前年同月の2倍を超え(前年比+101.8%)、米類だけでCPI(総合、前年比)を+0.61%ポイント押し上げている 3。これは現系列が遡れる1970年以降、米類がここまでCPIを押し上げたことはない異例の事態である 3。
この米価高騰は、家計に具体的な負担を強いている。米価高騰は物価全体を0.44%押し上げ、年間10,673円もの家計負担増につながると試算されている 4。月に5kg程度を消費する家庭では、年間で2万円程度の負担増となるとの指摘もある 10。
米類の価格上昇がCPIにこれほど大きく寄与しているという事実は、単なる食料品価格の問題を超え、日本全体のインフレ圧力の重要な構成要素となっていることを示す。これは、金融政策や経済全体への波及効果を考慮する上で極めて重要な指標となる。年間1万円から2万円という家計負担増は、特に低所得世帯にとって大きな打撃となる 5。米は生活必需品であるため、価格上昇が食費を圧迫し、他の消費を抑制せざるを得ない状況を生み出す。これは社会的な公平性の観点からも懸念される。CPIへの寄与度が高いことは、政府や中央銀行が物価安定策を講じる上で、米価格の動向が重要な考慮事項となることを裏付ける。また、1970年以降で最大の押し上げ効果という事実は、今回の事態の異常性を強調するものである。
Table 3.3.1: 米類が消費者物価指数に与える影響と家計負担(2024年)
|
期間 |
米類価格上昇率(前年比%) |
CPI総合への寄与度(%ポイント) |
年間家計負担増(円) |
|
2025年6月 |
+101.8 |
+0.61 |
N/A |
|
2024年 |
N/A |
+0.44 |
10,673 |
|
2024年 |
N/A |
N/A |
20,000程度(月5kg消費家庭) 10 |
注記: 2025年6月のデータは予測値を含む 3。2024年の家計負担増は年間推計値 4。
4. 供給サイドの要因分析
4.1. 2023年産米の不作と品質低下
2024年以降の米価格高騰の直接的な引き金となったのは、2023年産米の深刻な不作と品質低下である。2023年には記録的な猛暑と少雨に見舞われ、これが米の生産に甚大な影響を与え、収穫量が大幅に低下した 5。特に、新潟や秋田といった主要な米どころで不作が顕著であった 6。新潟県の主力品種であるコシヒカリは暑さに弱く、高温障害によって品質が低下し、収穫量も2割近く減少したとされている 6。
この異常気象は、米の品質にも深刻な影響を及ぼした。2023年産米の1等米比率は、異常高温に見舞われた結果、新潟県で過去最低水準の13.5%まで激減した 25。全国的にも、出穂期以降の高温が続いたことで、米の内部に亀裂が生じる「胴割れ粒」や、でんぷんの形成が悪く白く濁ったように見える「乳白粒」が多発し、1等米比率が低下した 22。
品質の低下は、精米歩留まりの悪化という形で市場への実質的な供給量をさらに減少させた。高温障害による胴割れ粒や乳白粒の多発は、精米した際の仕上がり量(精米歩留まり)を低下させ、結果的に市場に出回る米の量が減少した 6。2023年産米は高温・渇水の影響で1等比率が低下し、精米歩留まりが悪くなったことで、同じ量の精米を得るために必要な玄米の使用量が増加した 7。
これらの要因が複合的に作用し、2023年までの3年間で主食用米の収穫量は60万トン以上減少し、2023年には661万トンと過去最少を記録した 6。これまでの報道では、2024年の夏以来、コメの供給量が不足し、コメ価格が高騰したとされている 11。統計的な推測によれば、少なくとも2023年11月から17万トン(茶碗26億杯分)ものコメが市場に出回らずに「行方不明」になっているという指摘もある 11。
2023年の猛暑による不作と品質低下は、単に生産量が減っただけでなく、1等米比率の激減と精米歩留まりの悪化という形で、市場への実質的な供給量をさらに減少させた。この「質」の低下が、見かけの生産量以上に供給逼迫感を強め、価格高騰の直接的な引き金となった。また、「行方不明の17万トン」という報道は、単なる需給ギャップだけでなく、流通段階での情報不透明性や、一部による「買い占め・売り惜しみ」といった投機的行動の可能性を示唆している 10。これは、市場の効率性と透明性に対する構造的な課題を浮き彫りにするものである。
4.2. 民間在庫量の歴史的低水準化
2023年産米の不作と品質低下は、国内の民間在庫量を歴史的な低水準にまで押し下げ、市場の需給バランスを極めて脆弱なものにした。2023年6月末時点の米の民間在庫量は156万トンと、前年に比べ41万トン少ない、過去最低水準を記録した 7。さらに、2025年1月の時点では、民間のコメ在庫量は43万~44万トン減少しているとの報告もある 11。
農林水産省は、2024年産米の生産量回復を見込み、2025年6月末には民間在庫量が162万トン、2026年6月末にはさらに20万トン増える見込みと発表しているものの、2023年6月末の153万トンが過去最低であった事実が、現状の在庫水準の厳しさを物語っている 18。
民間在庫量が歴史的低水準に達したことは、市場の需給バランスが極めて脆弱であることを明確に示している。通常、在庫は供給ショックを吸収するバッファーの役割を果たすが、その機能が著しく低下していたため、わずかな供給不足でも価格が急騰しやすい状況にあった。この在庫量の低さは、流通業者や消費者に対して「品薄感」を強く印象付けた。これが「買い占め」や「売り惜しみ」といった投機的行動を誘発し、さらに価格上昇を加速させる悪循環を生んだと考えられる 6。市場の需給が逼迫している状況下では、たとえ一時的な需要増であっても、価格への影響は甚大となる。
Table 4.2.1: 米の民間在庫量と政府備蓄米の推移(2022年~2025年予測)
|
年月 |
民間在庫量(万トン) |
政府備蓄米(万トン) |
合計在庫量(万トン) |
需要量(万トン) |
在庫率(%) |
|
2023年6月末 |
156 |
91 |
247 |
702 (2023/7-2024/6) 7 |
22.2 (民間のみ) 7 |
|
2025年1月 |
減少(43-44万トン) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
2025年6月末予測 |
162 |
N/A |
N/A |
674 (2024/7-2025/6) 18 |
N/A |
|
2026年6月末予測 |
182 |
N/A |
N/A |
663 (2025/7-2026/6) 18 |
N/A |
注記: 需要量は当該期間の年間需要量。在庫率は民間在庫量に対する年間需要量の比率。2025年以降のデータは予測値 18。
4.3. 農業生産コストの高騰
米の価格高騰は、供給量の問題だけでなく、生産コストの構造的な上昇によっても強く影響を受けている。農業生産に不可欠な資材の価格が軒並み高騰しており、これが農家の経営を圧迫し、最終的に米価に転嫁されているのである。
肥料価格は顕著な上昇を見せている。2020年平均と比較して肥料代は1.4倍に上昇している 1。2024肥料年度秋肥(6~10月)の肥料価格は、円安の影響で3期ぶりに値上げとなり、高度化成肥料で+10.6%の値上がりとなった 30。肥料の価格指数(2020年=100)は136.5で、対前月比では1.8%上昇したものの、対前年同月比では▲8.0%低下している 8。しかし、これは高止まり傾向が続いている中での一時的な低下に過ぎず、依然として高い水準にある 8。
光熱動力費も同様に上昇している。2020年平均と比べて光熱動力費は1.3倍に上昇しており 1、価格指数は130.5で過去3番目に高い水準にある 8。対前年同月比では+4.5%の上昇が確認されている 8。さらに、農機具の価格指数も107.6と、2024年5月に続き過去最高を記録している 8。
これらの生産資材価格高騰の背景には、円安の進行が大きく影響している。円安が続く中、生産資材高騰が食品価格上昇の一因とされている 9。特に、化学肥料の大半を輸入に依存している日本にとって、2022年以降の急激な円安の進行は価格上昇の主要な要因となった 31。2024年4月以降は1ドル150円台と大幅な円安水準が続いており、これが輸入資材価格をさらに押し上げている 30。
肥料、光熱動力、農機具といった農業生産資材の価格高騰は、米の生産コストを直接的に押し上げている。特に円安は、輸入に依存する資材価格をさらに高騰させ、農家の経営を圧迫し、結果としてJAなどが農家に支払う「概算金」の上昇を通じて米価に転嫁されている 1。これは、需要と供給のバランスだけでなく、生産側のコスト構造が価格形成に強く影響していることを示すものである。農業物価指数によると、農業生産資材の総合価格指数は高止まりしている一方で、米の価格指数は上昇しているものの、農業交易条件指数(農産物価格指数÷農業生産資材価格指数×100)は91.4と2020年を下回る厳しい経営状況が続いている 8。これは、農家が販売価格の上昇分を生産コストの上昇で相殺されており、実質的な収益改善につながっていない可能性を示唆している。
Table 4.3.1: 農業生産資材価格指数推移(2020年基準)
|
年月 |
肥料価格指数 |
光熱動力価格指数 |
農機具価格指数 |
農業生産資材総合価格指数 |
農産物総合価格指数 |
農業交易条件指数 |
|
2020年基準 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
|
2024年6月 |
136.5 |
130.5 |
107.6 |
N/A |
94.9 |
91.4 |
|
2024年9月 |
139.5 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
注記: 2024年6月のデータは農水省が7月末に公表した6月の農業物価指数に基づく 8。2024年9月の肥料価格指数は別途報告されている 33。
4.4. 減反政策と構造的課題
日本の米生産は、長年にわたる減反政策によってその構造が形成されてきた。農林水産省は、人口減少に伴う米の消費減少を見越して、主食用米の生産をコントロールしており、2021年から2023年までの3年間で主食用米の収穫量は60万トン以上減少した 6。過去には「平成の米騒動」の根本原因も減反政策にあり、当時の潜在的な生産量1400万トンを減反で1000万トンに減らしていたと指摘されている 22。米の消費が減るほど生産調整のコントロールが難しくなる構造上の課題があり、需要に合わせて徐々に生産量を減らすため、コメから他の作物に一気に転換できないという問題がある 27。
この生産調整の一環として、農林水産省は農家に対し、食用米ではなく家畜飼料用に転換するよう奨励し、補助金を出している。この政策も主食用米の供給減少に寄与している 6。その結果、多くの農家が「補助金収益に頼ることに慣れすぎてしまった」可能性が指摘されている 34。主食用米の収益性の変動幅が大きいことから、飼料用米などの転作作物への依存度が高まり、その依存性が固定化された可能性がある 34。実際、大規模農家ほど収入に占める補助金割合が高い傾向が見られる 34。
このような状況は、市場の価格シグナルに対する生産側の迅速な増産対応を阻害している。2023年の不作は多くの農家に共有されていたはずだが、2024年産の主食用米を生産した農地は全国で125.9万haと、対前年比1.4%増に過ぎず、増産は限定的であった 34。
さらに、日本の米農家は平均年齢が70歳前後と高齢化が進んでおり、後継者不足も深刻な問題である 6。生産コストは上昇しているものの、米価は長らく低迷していたため、生産意欲が減退している側面もある 6。中小零細農家が退出した農地を中規模・大規模農家が引き受けて規模拡大していくという事業承継の成功パターンも、限界に来ているとの見方がある 34。
長年の減反政策は、米の供給量を意図的に抑制し、市場の需給バランスを極めてタイトな状態に保ってきた。これにより、わずかな生産量の変動(例えば2023年の異常気象による不作)が価格に与える影響が極大化される構造が形成された 22。これは、食料安全保障の観点から、国内自給率維持と価格安定のバランスを再考する必要性を示唆するものである。飼料用米等への補助金による転作奨励は、農家の経営安定に寄与する一方で、主食用米の生産調整を硬直化させ、市場の需要変動への迅速な対応を阻害している 27。2023年の不作が共有されていたにもかかわらず、2024年産米の作付面積が微増に留まったのは、この補助金依存と生産調整のメカニズムが、市場のシグナル(価格高騰)に対して十分に機能していないことを示している。農家の高齢化と後継者不足、それに伴う生産意欲の減退は、生産コスト高騰と相まって、米生産基盤の構造的な脆弱性を深刻化させている。これは、短期的な価格高騰だけでなく、中長期的な国内米供給の安定性に対する根本的な懸念を提起する。
5. 需要サイドの要因分析
5.1. 一時的な需要増加
2024年以降の米価格高騰は、供給サイドの課題に加え、一時的な需要増加が複合的に作用した結果として理解される。複数の要因が重なり、限られた供給量に対する需要圧力が急増した。
まず、新型コロナウイルス感染症の収束に伴う外食需要の回復とインバウンド(訪日客)の増加が挙げられる。コロナ禍が収束し、訪日外国人が増加したことで外食需要が急拡大した 6。特に、2024年上半期には過去最多の約1778万人が訪日し、これにより米の消費量が増加したとされている 6。インバウンドの急増は一時的に米の需要を押し上げた 18。
次に、他食料品との相対的な割安感が米の消費を押し上げた側面がある。パンや麺類など小麦製品の価格が上昇する中で、国内生産である米は比較的価格上昇が緩やかであったため、米に割安感が生まれ、消費を促した 6。
さらに、品薄報道や災害警戒による消費者の備蓄需要、および業者による買い占め行動が需要を一時的に急増させた。2024年8月に南海トラフ地震臨時情報が発表された際には、多くの人々が備蓄用に米を買い求めたことが一因とされている 6。また、品薄報道や2024年初頭からのインフレ傾向の中で、米の価格高騰を見越した業者による買い占めや、「より高い時に売りたい」という売り惜しみ行動が広がった 10。
これらの要因が重なり、実質的な需要量が増加した。2023年7月~2024年6月のコメ需要量は702万トンとなり、農林水産省が予想した680万トンを22.1万トンも上回る異例の増加となった 7。この需要増加は、実需の増加だけでなく、酷暑による1等米の減少により精米歩留まりが悪くなったことなど、流通段階での「見かけの需要」の増加も含まれており、市場の混乱をさらに深めたと考えられる 34。
供給不足が顕在化する中で、外食・インバウンド需要の回復、他主食からの代替需要、そして災害警戒や品薄報道による消費者・業者双方の投機的・予防的な買い占め行動が重なり、短期間に需要が急増した。この需要増は、実需の増加だけでなく、流通段階での「見かけの需要」の増加(精米歩留まり悪化による玄米使用量増など)も含まれており、市場の混乱をさらに深めた。特に、南海トラフ地震臨時情報のような不確実性の高い情報が、消費者の心理に与える影響は大きく、これが備蓄需要という形で市場に直接的な圧力をかけた。これは、情報伝達のあり方や、危機管理における食料供給の安定性確保の重要性を再認識させるものである。
5.2. 長期的な米消費量の減少傾向
一時的な需要増加が米価格高騰に拍車をかけた一方で、日本における米の消費量は長期的に減少傾向にあるという構造的な課題が存在する。お米の1人当たりの消費量は1962年度をピークに減少傾向が続いており、ピーク時の年間118.3kgから2022年度には年間50.9kgまで減少した 35。
この減少傾向は、人口減少、高齢化、そして食生活の多様化といった構造的要因によってもたらされている 36。特に高年齢層では米消費の減少が半数を占め、40歳以上では「もう充分に食べている」との回答が7割以上、60歳以上では8割に達している 37。消費者の食の多様化も進んでおり、「ご飯よりもパンや麺が味がよい」「手間がかかる」「米が続くと飽きる」「パンや麺は料理や商品の種類が豊富」といった理由で、パンや麺類を選ぶ傾向が強まっている 37。
今回の価格高騰は、この長期的な米離れトレンドをさらに加速させる可能性を秘めている。1年前と比較してお米の購入頻度が「減った」と回答した人が全体の55.9%に上り、「主食がお米以外の方」では62.0%が減少を回答している 23。米の摂取頻度が「減った」と「少し減った」を合わせて35.9%が減少したと回答しており、特に20代以下の「減った」が14.1%と最も多い 24。米の代替食品として「パン」(50.5%)、「うどん」(43.2%)、「パスタ」(34.8%)を挙げる消費者が多く、主食にしたい代替食品としては「うどん」(68.7%)、「パン」(67.1%)が上位を占めている 23。
消費者の約8割が米の購入時に「価格」を重視しており、年齢が上がるほど「品質(味・食感)」や「ブランド・銘柄」を意識する傾向が見られる 24。また、生活者にとっての「日常的な米の上限価格」は5,000円(5kg)が天井ラインとして意識されており、それを超えると購入を躊躇する層が急増する構造が明らかになった 23。
米の消費量は長期的に減少傾向にあるが、今回の価格高騰は、このトレンドをさらに加速させる可能性がある。特に、元々米を主食としない層や若年層において、価格上昇が「米離れ」を決定的にする引き金となっている 23。これは、一時的な価格安定策だけでなく、中長期的な米食文化の維持・振興策の必要性を示唆する。消費者の約8割が価格を重視しているという事実は、米価が「日常的な上限価格」を超えた際に、買い控えや代替食品への移行が加速することを示している。これは、米の価格設定が、消費者の購買行動に直接的な影響を与え、市場全体の需要構造を変化させる可能性があることを意味する。
Table 5.2.1: 消費者の米購入行動変化と代替食品への移行(2024年)
|
項目 |
変化の割合(%) |
年代別傾向 |
上限価格意識(円/5kg) |
|
購入頻度減 |
55.9 |
主食がお米以外の方: 62.0% |
N/A |
|
摂取頻度減 |
35.9 |
20代以下: 14.1%(減った) |
N/A |
|
代替食品利用 |
パン: 50.5 |
N/A |
N/A |
|
|
うどん: 43.2 |
N/A |
N/A |
|
|
パスタ: 34.8 |
N/A |
N/A |
|
主食にしたい代替品 |
うどん: 68.7 |
N/A |
N/A |
|
|
パン: 67.1 |
N/A |
N/A |
|
価格重視度 |
78.7 |
20代以下: 84.5%(最も重視) |
N/A |
|
上限価格 |
N/A |
5,000円が天井ラインと意識される層が急増 23 |
5,000 |
注記: データは2024年に行われた消費者調査に基づく 23。
6. 市場構造と流通の課題
6.1. 米流通の「自由化と不可視化」
日本の米流通は、過去の政府管理から自由化へと移行する中で、「自由化による不可視化」が進展したと指摘されている 12。この「不可視化」が、今回の価格高騰局面において市場の混乱を招いた主要な要因の一つである。2024年に米不足が騒がれ始めた際、「消えた21万トン」問題が話題となり、一部報道では「異業種参入の転売業者が21万トンもの米を隠し持っている」といった憶測が語られた 12。
米流通の自由化は競争を促進する一方で、取引情報の「不可視化」を招き、市場参加者間の情報非対称性を高めた。この情報不足が、供給不足時に「消えた米」のような憶測を生み出し、市場の不信感と混乱を増幅させたと考えられる。透明性の欠如は、パニック買いや投機的行動を助長し、結果として価格高騰に拍車をかける要因となる。また、自由化された流通経路は多様化しているものの、危機時の情報共有や供給調整のメカニズムが十分に機能しない脆弱性を抱えている可能性が示唆される。特に、大規模な供給ショックが発生した際に、市場全体で状況を正確に把握し、迅速に対応するための仕組みが不足していることが露呈した。
6.2. 相対取引価格決定メカニズムとJAの役割
米の価格形成において、JAグループは重要な役割を担っている。米は集荷の際に県単位で全農本部・経済連が決定した概算金(仮払金)が農家に支払われ、この概算金に保管、運送、検査費用などの流通経費等が加えられたものが相対取引価格となる 19。この概算金は、国の政策や政治的配慮によって決定される側面があり、完全には需要と供給のバランスだけで価格が決まっているわけではない 19。
JAは、農家から米を出荷され、それを卸業者に販売し、卸業者は小売業者に販売し、最終的に小売業者が消費者に販売するという流通経路において、中心的な役割を担っている 38。今回のコメ価格高騰についても、減反政策や気候変動による供給不足があったものの、価格が2倍になった背景には、コメの流通に大きな力を持っているJAの存在があるという指摘も存在する 11。
JAグループが概算金を通じて米の価格形成に大きな影響力を持っていることは、市場の自由な価格決定メカニズムに一定の制約を与えている。これにより、市場の需給シグナルが価格に迅速かつ正確に反映されにくい可能性がある。一方で、このメカニズムが農家の経営安定に寄与している側面も考慮する必要がある。しかし、JAがコメ流通において持つ「大きな力」は、効率的な流通を阻害する要因となる可能性も指摘されている 11。政府備蓄米の放出先がJAなどの大手卸売業者に限定されたことで、末端のスーパーへの供給に時間がかかった事例は 11、この権限集中が危機時にボトルネックとなる可能性を示唆している。
6.3. 政府備蓄米の運用と市場への影響
政府備蓄米は、食料安全保障の観点から国内の米供給安定に重要な役割を果たすが、その運用方法が今回の価格高騰に影響を与えた側面がある。政府備蓄米の放出先がJAなどの大手卸売業者に限定されたため、備蓄米がスーパーなどの小売店に届くまでに時間がかかり、それが価格を前年よりも2倍に押し上げた一因となったという指摘がある 11。
さらに、2024年10月時点では、当時の農林水産大臣が米価下落を懸念し、備蓄米を放出しない方針を示していた。この姿勢に対しては、「農家保護の観点から備蓄米放出に消極的」との批判も集まった 10。しかし、2023年7月から2024年6月のコメ需要量が702万トンであったのに対し、政府在庫量91万トンと民間在庫量156万トンを合わせると247万トンとなり、需要量を賄えないほど供給が減少したわけではなかったという見方もある 27。
政府備蓄米は食料安全保障の最後の砦であり、その運用は市場の安定に直結する。しかし、その放出タイミングと方法が市場の混乱を助長した可能性がある。特に、品薄感が強まる中で放出に消極的な姿勢が示されたことは、市場の不安を煽り、価格高騰に拍車をかけたと考えられる。これは、農家保護と消費者利益、そして市場安定のバランスを取る政策判断の難しさを示している。備蓄米が大手卸売業者に限定された放出経路は、末端の小売店への迅速な供給を妨げ、価格高騰の緩和効果を限定的にした。これは、政府の介入策が市場の複雑な流通構造に適切に対応できていなかったことを示唆しており、より柔軟かつ効率的な放出メカニズムの再検討が必要である。
Table 6.3.1: 政府備蓄米の在庫量と放出状況(2023年~2024年)
|
年月 |
政府備蓄米在庫量(万トン) |
放出量(万トン) |
放出先(種類) |
放出時期 |
関連政策発表 |
|
2023年6月末 |
91 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
2024年10月 |
N/A |
N/A |
N/A |
2024年10月 |
農水大臣が米価下落懸念で放出に消極的姿勢 10 |
|
2025年8月以降 |
N/A |
入札による販売 |
加工原材料用、MA米代替不足時 |
2025年8月以降 |
政府備蓄米の入札販売実施方針 27 |
注記: 提供された情報に基づき、具体的な放出量や時期が明示されていない場合はN/Aとしている。
6.4. スポット取引市場の価格高騰
米の流通市場において、卸売業者間の「スポット取引」(比較的小さい単位での取引)市場では、価格高騰がより顕著に現れている 10。特に、令和6年産の関東銘柄米は過去に例を見ない価格高騰を記録しており、2025年1月以降は前年比で約3倍の水準にまで達している 10。
スポット取引市場は、短期的な需給バランスの変化に最も敏感に反応する。この市場での価格急騰は、供給逼迫が深刻であることを示す先行指標であり、卸売業者や小売業者が緊急的に米を調達しようとする動きが価格をさらに押し上げている。相対取引価格が比較的安定している中でも、スポット取引価格が異常な高騰を見せることは、米市場に二重の価格形成構造が存在することを示唆している。これは、一部の流通経路や取引形態において、より深刻な供給不足や投機的行動が集中している可能性を示唆するものである。
6.5. 投機的行動と買い占め・売り惜しみ
米の価格高騰は、実際の需給バランスの崩れだけでなく、市場参加者の投機的行動によっても増幅された側面がある。米の価格高騰を見越した業者による買い占めや、「より高い時に売りたい」という売り惜しみ行動が広がったと指摘されている 10。特に2024年初頭からのインフレ傾向の中で、米価格の上昇期待が投機的行動を促したと考えられる 10。
供給不足の報道や価格上昇の初期兆候が、市場参加者(特に流通業者)の投機心理を刺激し、買い占めや売り惜しみといった行動を誘発した。これは、実際の需給ギャップ以上に市場での流通量を減少させ、価格高騰を自己実現的に加速させるメカニズムとして機能した。また、「消えた21万トン」問題 11 のような情報が、投機的行動の憶測を呼び、それがさらに市場の不透明感を高めるという悪循環を生んだ。これは、市場の透明性確保と、不確実な情報に対する適切な対応の重要性を示唆するものである。
7. 国際市場の動向と日本への影響
7.1. 主要輸出国(インド)の輸出規制
国際市場の動向も、日本国内の米価格に間接的な影響を与えている。2023年7月、世界最大のコメ輸出国であるインドが、国内価格の安定を目的にコメ輸出を部分的に禁止した 13。この措置は、国際的な米市場の需給バランスを大きく揺るがし、国際米価格の高騰を招いた。
日本は国内生産が主であるため、直接的な輸入依存度は低いものの、国際市場の価格上昇は、国内市場の価格形成に間接的な上方圧力を与える可能性がある。特に、国内米が高騰する中で輸入米への代替需要が高まる場合、国際価格の影響は無視できないものとなる。主要輸出国による輸出規制は、グローバルな食料サプライチェーンの脆弱性を浮き彫りにする。自給率の高い米であっても、国際市場の混乱は、国内の食料安全保障政策に再考を促す要因となる。
7.2. 世界の米生産・消費動向
米は世界人口の半数以上の主食であり、特にアジアで最も広く消費されている主要な穀物である。中国とインドが世界の米生産量の50%を占めている 39。世界の米市場規模は2024年に3,765億4,000万米ドルと推定され、2029年までに4,365億1,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間(2024年から2029年)中に3%の年平均成長率(CAGR)で成長すると見込まれている 39。
中国の米生産量は増加傾向にあり、天候安定と農業補助金政策が後押ししている一方、インドは安定しているものの、高温や干ばつリスクに左右されやすい特性がある 40。モンスーンへの依存、害虫や病気の大量発生、土地や労働力の不足などが、世界の米市場の成長を妨げる要因となる可能性も指摘されている 39。
世界の米生産が少数の国に集中していること、そして気候変動による異常気象(モンスーン依存、干ばつ)や病害虫といったリスク要因が世界的に存在することは、国際米市場の構造的な不安定性を示唆している。これは、日本国内の供給が安定していても、国際市場の動向が国内価格に影響を与えるリスク要因となる。また、世界人口の増加、特にアジア、サハラ以南アフリカ、南米における米の主食としての重要性、および食品・レストラン部門の増加は、世界的な米需要の拡大を牽引している 39。この需要拡大は、国際価格を押し上げる長期的なトレンドとなり得る。
7.3. 日本の米輸出入動向
日本国内で米価格が高騰する一方で、日本の米輸出は好調に推移している。2024年の商業用のコメの輸出数量は対前年比21%増の45,112トン、輸出金額は対前年比28%増の12,029百万円と、ともに好調を維持した 41。主な輸出先は香港、アメリカ、シンガポール、台湾、カナダなどである 42。
一方で、国内米価格の高騰により、高関税にもかかわらず輸入米が急増している状況も確認されている 10。この傾向が続けば、外食産業を中心に輸入米への依存度が高まり、市場全体の価格形成に影響を与える可能性がある 10。
日本の米輸出が好調に推移している一方で、国内では価格高騰と供給不足が問題となっているという状況は、国内市場と国際市場の価格差や、国内生産の優先順位に関する議論を提起する。輸出振興は重要だが、国内需給の安定を損なう形で進められるべきではないという課題が浮上する。また、国内米価格の高騰が輸入米の需要を喚起している。これは一時的な供給不足の緩和に寄与する可能性がある一方で、長期的に見れば外食産業などの輸入米への依存度を高め、国内生産米の需要を圧迫するリスクもはらんでいる。
8. 複合的要因と相互作用
2024年以降の日本における米価格高騰は、単一の原因によるものではなく、複数の要因が複雑に絡み合い、互いに増幅し合った結果として発生している。
まず、2023年産米の供給ショックが直接的な起点となった。2023年の記録的な猛暑と少雨は 5、生産量の減少(主食用米の収穫量は661万トンと過去最少) 6 に加え、1等米比率の激減(新潟県で13.5%) 25 や精米歩留まりの低下 6 を引き起こし、市場への実質的な供給量を大幅に減少させた。これにより、2024年以降の価格高騰の直接的な引き金が引かれた。
この供給ショックの影響は、長期的な構造的脆弱性によってさらに増幅された。長年にわたる減反政策 6 は、国内米の生産量を意図的に抑制し、需給バランスを極めてタイトな状態に保ってきた。これにより、2023年の供給ショックが、本来であれば吸収可能な範囲を超えて、市場全体に深刻な影響を及ぼすことになった 22。また、農家の高齢化と後継者不足、そして補助金依存による生産調整の硬直性 6 は、市場の価格シグナル(高騰)に対する生産側の迅速な増産対応を阻害し、供給回復を遅らせる構造的な要因となった 34。
生産コストの高騰も、価格上昇に持続的な圧力を加えた。肥料、光熱動力、農機具といった農業生産資材の価格高騰は、特に円安の進行 1 と相まって、農家の生産コストを押し上げ、JAが農家に支払う概算金の上昇に繋がり、最終的な米価に転嫁された 1。これは、供給量だけでなく、供給側のコスト構造が価格を押し上げる要因として作用したことを示している。
供給不足とコスト増の状況下で、一時的な需要増加が価格高騰を加速させた。新型コロナウイルス感染症の収束に伴う外食・インバウンド需要の回復 5、他主食との相対的割安感 6、そして南海トラフ地震臨時情報発表や品薄報道による消費者の備蓄・買い占め行動 6 が、限られた供給量に対する需要圧力を一時的に急増させた。特に、2023年7月~2024年6月の需要量が農林水産省予想を22.1万トン上回った 7 ことは、この需要増加のインパクトを明確に示している。
さらに、流通市場の不透明性と投機的行動が、価格上昇に拍車をかけた。米流通の「自由化と不可視化」 12 は、「消えた21万トン」問題 11 のような憶測を生み、市場の不信感を高めた。価格高騰を見越した業者による買い占めや売り惜しみ 10 は、実際の流通量をさらに減少させ、スポット取引市場での異常な価格高騰 10 を引き起こし、価格上昇を自己実現的に加速させた。政府備蓄米の放出の遅れや限定的な経路 10 も、市場の品薄感を解消する効果を限定的にし、混乱を長引かせた。
最後に、国際市場の動向も間接的な影響を与えた。世界最大の輸出国であるインドの輸出規制 13 は、国際米価格を押し上げ、日本国内の価格高騰に間接的な上方圧力を与えた。国内米の高騰が輸入米への代替需要を喚起する中で、国際市場の動向が国内価格形成に与える影響は無視できないものとなった。
以上の分析から、2024年以降の米価格高騰は、単一の原因ではなく、2023年産の供給ショックを起点とし、長年の政策的・構造的脆弱性、外部環境の変化(コスト高騰、国際情勢)、そして市場参加者の心理的・投機的行動が複雑に絡み合い、互いに増幅し合った結果であると結論付けられる。特に、供給の構造的脆弱性が、わずかなショックを大規模な価格変動へと転化させる「増幅器」として機能した点が重要である。今回の事態は、短期的な需給ギャップの問題と、中長期的な構造問題が同時に顕在化したものである。したがって、根本的な解決には、短期的な市場介入と並行して、農業政策や流通構造の抜本的な改革が不可欠である。
9. 今後の見通しと提言
9.1. 短期的な価格安定化の見通し
2024年産米の収穫量と品質の回復は、短期的な供給逼迫の緩和に寄与し、市場の極端な品薄感を解消する可能性がある。農林水産省の予測によると、2024年産水稲の収穫量(主食用)は679.2万トンと、前年産に比べ18.2万トン増加する見込みであり、全国の作況指数は101(平年並み)と見込まれている 1。特に、2023年に異常高温に見舞われ13.5%まで低下した新潟県産米の1等米比率は、2024年には84.0%にまで大幅に回復した 25。
農林水産省は、2024年の主食用米の生産量が683万トンとなり、来年6月まで1年間の需要量674万トンを上回る見込みであると発表している 18。これにより、民間在庫量も回復に向かうと予測されており、2025年6月末には162万トン、2026年6月末にはさらに20万トン増える見通しである 18。
これらのデータは、短期的な供給量の改善と在庫の回復を示唆しており、極端な品薄感は解消される可能性がある。しかし、一度上昇した価格は、生産コストの高止まりや市場心理の慣性により、容易には下落しない「価格の粘着性」を示す可能性が高い 6。したがって、新米の流通開始によって一部の供給不足は解消される見込みがあるものの、根本的な値下がりは期待できない状況である 6。農林水産省の需給見通しは、市場の安定化に向けた重要な指針となるが、2023年の需要予測のずれ(680万トン予想に対し実績702万トン) 27 を鑑みると、より精緻な需要予測と、それに基づく柔軟な生産・供給調整の必要性が浮き彫りになる。
9.2. 中長期的な課題と政策提言
米価格高騰の根本的な解決と、将来的な食料安全保障の確保のためには、中長期的な視点に立った政策転換が不可欠である。
気候変動適応型農業の推進
気候変動は不可逆的なトレンドであり、2023年の猛暑による不作は今後も頻発する可能性がある。高温障害に強い品種の開発・普及を加速させ、異常気象に強い米作りを推進することが喫緊の課題である 29。具体的には、高温耐性品種の育種研究への投資を増やし、農家への導入を奨励する。また、水管理の最適化、施肥時期の調整といった栽培技術の改善や、スマート農業技術の導入により、気候変動による品質・収量低下リスクを低減する取り組みを強化すべきである。これは単なる増産策ではなく、将来的な供給安定化と品質維持のための不可欠な適応策である。
生産コスト上昇への対策
生産コストの高騰は、農家の生産意欲を減退させ、持続可能な農業経営を脅かす。肥料、燃料といった農業生産資材の価格安定化に向けた支援策を検討する必要がある 45。具体的には、補助金制度の見直しや、輸入依存度低減のための国内生産強化(例:国産肥料原料の開発・利用促進)が挙げられる。また、サプライチェーン全体の効率化を図り、流通コストを削減する努力も不可欠である 21。単なる米価上昇ではコスト増を吸収しきれない現状 8 を鑑み、直接的なコスト支援や、コスト削減に資する技術導入支援が不可欠である。
流通構造の透明化と効率化
米流通の不透明性は市場の混乱と不信感を招き、価格高騰を助長した。市場の透明性を高めるため、米の取引情報の共有を促進すべきである 12。特に、「消えた米」問題のような憶測を排除するため、在庫量や流通量のリアルタイムな情報開示を強化することが求められる 11。また、価格高騰を見越した投機的行動を抑制するための市場監視体制を強化し、多様な流通チャネルの育成を支援することで、市場の安定性を高めることができる。透明性の向上は、市場参加者間の情報格差を是正し、より効率的で信頼性の高い価格形成を促す上で極めて重要である。
政府備蓄米の柔軟な運用
政府備蓄米は食料安全保障の最後の砦であり、その運用は市場の安定に直結する。市場の需給状況に応じて、政府備蓄米をより迅速かつ効果的に放出するメカニズムを確立すべきである 27。過去の放出の遅れや限定的な経路が批判された経験 10 を踏まえ、放出先の多様化や、小売店への直接供給ルートの検討など、末端市場への影響を最大化する運用を模索する必要がある。これにより、将来の供給ショックに備え、より機動的で市場実態に即した運用体制を構築し、危機管理体制を強化することが可能となる。
米消費拡大に向けた新たな需要創出
長期的な米消費量の減少トレンドは、価格高騰とは別の構造的な課題である。価格が安定してもこのトレンドが続けば生産基盤の維持は困難になる。米粉利用の促進、中食・外食産業との連携強化、健康志向への対応(例:低GI米、機能性米の開発)など、米の新たな需要を創出する施策を推進すべきである 35。米料理のマンネリ化を克服するための情報発信や商品開発も重要である 37。新たな需要創出は、国内米生産の持続可能性を確保し、米食文化を次世代に繋ぐための不可欠な戦略である。
農家の経営安定化と後継者育成支援
農家の高齢化と後継者不足は、米生産の根幹を揺るがす問題である。収益性の高い米作りの支援(高付加価値米の生産奨励)、スマート農業・IT化の推進による省力化・コスト削減 40、そして若手農家の参入促進と事業承継支援を強化する必要がある。経営の安定化と魅力向上は、新規就農者を呼び込み、生産基盤を強化するための最も重要な要素である。スマート農業の導入は、労働力不足の解消と生産効率の向上に寄与し、農業の持続可能性を高める。
9.3. 結論
2024年以降の日本における米価格高騰は、単なる一時的な供給不足に起因するものではなく、2023年産の異常気象による供給ショックを起点とし、長年にわたる減反政策による国内供給体制の脆弱性、農業生産コストの高騰、一時的な需要増加、そして流通市場の不透明性や投機的行動が複合的に作用し、互いに増幅し合った結果である。
短期的な価格安定化は2024年産米の収穫量回復により見込まれるものの、生産コストの高止まりや市場心理の慣性から、根本的な価格下落は期待しにくい。中長期的には、気候変動への適応、生産コストの抑制、流通の透明化、政府備蓄米の柔軟な運用、そして新たな米需要の創出と農家の経営安定化に向けた包括的かつ戦略的な政策転換が不可欠である。これらの複合的な課題に対処することで、日本の食料安全保障と持続可能な米生産の未来を確保することが可能となる。
10. 参考文献
- 1
https://smbiz.asahi.com/article/15515610 - 2
https://www.mri.co.jp/knowledge/column/20250128.html - 5
https://www.agri-ya.jp/column/2025/03/03/rice-shortage-and-rising-prices/ - 11
https://toyokeizai.net/articles/-/878856?display=b - 15
https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/soukatu/r6_kome_ryutu.html - 20
https://jfaco.jp/column/3770 - 16
https://www.jrra.or.jp/news_374.html - 17
https://www.nosai.or.jp/mt6/2024/12/post-8203.html - 46
https://okome-chiebukuro.com/rice-harvest-amount-2024/ - 47
https://okome-chiebukuro.com/rice-yield-ranking-2025/ - 48
https://www.nosai.or.jp/mt6/2024/11/post-8175.html - 34
https://www.mri.co.jp/knowledge/column/20250311_3.html - 8
https://www.jacom.or.jp/nousei/news/2024/08/240820-75969.php - 9
https://www.alic.go.jp/koho/mng01_000383.html - 31
https://agriport.jp/information/ap-19167/ - 32
https://agriport.jp/agriculture/ap-22821/ - 3
https://www.jri.co.jp/file/report/other/pdf/15915.pdf - 4
https://www.nri.com/jp/media/column/kiuchi/20250203_2.html - 39
https://www.gii.co.jp/report/moi1443924-rice-market-share-analysis-industry-trends.html - 40
https://wiple-service.com/column/world-rice-production-ranking-trends-country-share/ - 13
https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=105945 - 14
https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/report/researchfocus/pdf/14398.pdf - 41
https://www.maff.go.jp/j/seisan/kikaku/soukatu/r6_kome_ryutu.html - 42
https://gohansaisai.news/news/article-13351/ - 49
https://www.maff.go.jp/j/seisan/keikaku/soukatu/attach/pdf/mr-862.pdf - 34
https://www.mri.co.jp/knowledge/column/20250311_3.html - 18
https://agri.mynavi.jp/2024_10_31_287187/ - 36
https://www.tsunagi-japan.co.jp/blog/komebusoku/ - 35
https://www.maff.go.jp/j/heya/sodan/1808/01.html - 37
https://apcagri.or.jp/apc/prescolumn/6520 - 6
https://www.morishitahouse.jp/info/%E8%BE%B2%E6%9E%97%E6%B0%B4%E7%94%A3%E7%9C%81/%E4%BB%A4%E5%92%8C6%E5%B9%B4%E3%81%AE%E7%B1%B3%E4%B8%8D%E8%B6%B3%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%9C%E8%B5%B7%E3%81%93%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%AE%E3%81%8B%EF%BC%9F/ - 22
https://www.rieti.go.jp/jp/papers/contribution/yamashita/149.html - 7
https://www.jacom.or.jp/kome/news/2024/07/240731-75706.php - 50
https://www.pacola.co.jp/%E4%BB%A4%E5%92%8C5%E5%B9%B4%E7%94%A3%E7%B1%B3%E3%81%AE%E5%A5%91%E7%B4%84%E6%95%B0%E9%87%8F253-6%E4%B8%87%E3%83%88%E3%83%B3%E3%81%A8%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E6%95%B0%E9%87%8F208-2%E4%B8%87%E3%83%88%E3%83%B3/ - 27
http://www.nohken.or.jp/NOGYOKENKUYU/No.37-2024/2024-14_ogawa.pdf - 10
https://edenred.jp/article/productivity/220/ - 30
https://www.jacom.or.jp/shizai/news/2024/05/240531-74476.php - 51
https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3836 - 8
https://www.jacom.or.jp/nousei/news/2024/08/240820-75969.php - 33
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/kikaku/kakaku_keisei/attach/pdf/imdex-85.pdf - 45
https://smbiz.asahi.com/article/15543436 - 52
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/demand_forecast/pdf/20240426_1.pdf - 19
https://www.okomemaster.com/trivia.html - 21
https://www.jacom.or.jp/kome/news/2025/03/250327-80486.php - 53
https://org.ja-group.jp/challenge/wp_challenge/wp-content/uploads/2019/03/20190321134906335.pdf - 38
https://www.youtube.com/watch?v=IcePj-bTXVI&pp=0gcJCfwAo7VqN5tD - 12
https://www.nx-soken.co.jp/topics/blog_20250428 - 54
https://www.mri.co.jp/knowledge/column/20250311_2.html - 55
https://www.shikoku-np.co.jp/bl/digital_news/article.aspx?id=K2025032300000009600 - 28
https://www.nippon.com/ja/news/kd1309045392461202307/ - 23
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000591.000003149.html - 24
https://www.commercepick.com/archives/62642 - 36
https://www.tsunagi-japan.co.jp/blog/komebusoku/ - 56
https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/jki/attach/pdf/index-47.pdf - 43
http://www.japan-rice.com/yosou2024.html - 44
https://www.jacom.or.jp/kome/news/2024/08/240819-75939.php - 25
https://sakepro.jp/news/13075/ - 29
https://awayokuba50.hatenablog.com/entry/2024/08/18/154516 - 26
https://www.nosai.or.jp/mt6/2024/08/post-8028.html
引用文献
- 2024年産米の「相対取引価格」は2万5927円 「平成の米騒動」超え | ツギノジダイ, 8月 11, 2025にアクセス、 https://smbiz.asahi.com/article/15515610
- 『令和のコメ騒動』(1)コメ高騰の歴史に学ぶ、今後の見通し – 三菱総合研究所, 8月 11, 2025にアクセス、 https://www.mri.co.jp/knowledge/column/20250128.html
- 令和の米騒動からみる温暖化インフレのリスク, 8月 11, 2025にアクセス、 https://www.jri.co.jp/file/report/other/pdf/15915.pdf
- コメの価格高騰は年間1万円以上の家計負担に:政府備蓄米放出ルールの緩和は、投機的な動きを抑えるための例外的、時限的措置として容認される | 木内登英のGlobal Economy & Policy Insight | 野村総合研究所(NRI), 8月 11, 2025にアクセス、 https://www.nri.com/jp/media/column/kiuchi/20250203_2.html
- 【中小農家必見】米不足と価格高騰が深刻化!原因と2025年の見通し – 農機具ランド あぐり家, 8月 11, 2025にアクセス、 https://www.agri-ya.jp/column/2025/03/03/rice-shortage-and-rising-prices/
- 令和6年の米不足はなぜ起こったのか? | 農業用ビニールハウスのモリシタ, 8月 11, 2025にアクセス、 https://www.morishitahouse.jp/info/%E8%BE%B2%E6%9E%97%E6%B0%B4%E7%94%A3%E7%9C%81/%E4%BB%A4%E5%92%8C6%E5%B9%B4%E3%81%AE%E7%B1%B3%E4%B8%8D%E8%B6%B3%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%9C%E8%B5%B7%E3%81%93%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%AE%E3%81%8B%EF%BC%9F/
- 米の民間在庫156万t 過去最小 6月末 需要実績増 農水省, 8月 11, 2025にアクセス、 https://www.jacom.or.jp/kome/news/2024/07/240731-75706.php
- 肥料、飼料価格の高止まり続く 農業物価指数 農水省 2024年8月20日, 8月 11, 2025にアクセス、 https://www.jacom.or.jp/nousei/news/2024/08/240820-75969.php
- 【まめ知識】生産資材高騰とは? – 独立行政法人 農畜産業振興機構, 8月 11, 2025にアクセス、 https://www.alic.go.jp/koho/mng01_000383.html
- 【令和の米騒動】2025年最新動向|政府備蓄米放出の効果と今後 – 株式会社エデンレッドジャパン, 8月 11, 2025にアクセス、 https://edenred.jp/article/productivity/220/
- 備蓄米を放出したのに高すぎる…コメ価格高騰がいつまでも終わらない根本原因, 8月 11, 2025にアクセス、 https://toyokeizai.net/articles/-/878856?display=b
- SCMの観点から令和のコメ騒動を考える1 | 株式会社NX総合研究所, 8月 11, 2025にアクセス、 https://www.nx-soken.co.jp/topics/blog_20250428
- インドのコメ輸出制限の影響 – 日本総研, 8月 11, 2025にアクセス、 https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=105945
- インドのコメ輸出制限の影響 – Research Focus, 8月 11, 2025にアクセス、 https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/report/researchfocus/pdf/14398.pdf
- 米の流通状況等について – 農林水産省, 8月 11, 2025にアクセス、 https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/soukatu/r6_kome_ryutu.html
- 令和6年産水陸稲の収穫量, 8月 11, 2025にアクセス、 https://www.jrra.or.jp/news_374.html
- 24年産水稲の作況 101の「平年並み」(2面・総合)【2024年12月3週号】 – NOSAI協会, 8月 11, 2025にアクセス、 https://www.nosai.or.jp/mt6/2024/12/post-8203.html
- 2024年コメ生産、需要上回る 在庫も回復、品薄への懸念緩和へ – マイナビ農業, 8月 11, 2025にアクセス、 https://agri.mynavi.jp/2024_10_31_287187/
- 豆知識 – 米・米ニシヤマ, 8月 11, 2025にアクセス、 https://www.okomemaster.com/trivia.html
- 止まらない米価の高騰。コメはどこにいった?? – 日本食農連携機構, 8月 11, 2025にアクセス、 https://jfaco.jp/column/3770
- 米の小売価格、5キロ4000円超は適正か 相対取引価格とコスト構造から試算 「超過利潤」は誰の手に 2025年3月27日 – 農業協同組合新聞, 8月 11, 2025にアクセス、 https://www.jacom.or.jp/kome/news/2025/03/250327-80486.php
- 令和のコメ騒動、根本的な原因を問う – RIETI, 8月 11, 2025にアクセス、 https://www.rieti.go.jp/jp/papers/contribution/yamashita/149.html
- お米が高騰しても食べ続ける“お米堅守層”は33.7%|お米に関する調査 – PR TIMES, 8月 11, 2025にアクセス、 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000591.000003149.html
- 消費者調査に見る米の購入行動とその影響 – コマースピック, 8月 11, 2025にアクセス、 https://www.commercepick.com/archives/62642
- 2024年新潟県産米の1等米比率84%に、過去最低水準の23年から大幅回復, 8月 11, 2025にアクセス、 https://sakepro.jp/news/13075/
- 2024年度水稲 猛暑の影響に注視 品質低下の懸念も(3面・農業保険)【2024年8月3週号】, 8月 11, 2025にアクセス、 https://www.nosai.or.jp/mt6/2024/08/post-8028.html
- 2024年夏におけるコメの品薄の要因と課題 – 日本農業研究所, 8月 11, 2025にアクセス、 http://www.nohken.or.jp/NOGYOKENKUYU/No.37-2024/2024-14_ogawa.pdf
- 24年度のコメ購入量6.7%増 高騰も支出継続、総務省家計調査 | nippon.com, 8月 11, 2025にアクセス、 https://www.nippon.com/ja/news/kd1309045392461202307/
- 猛暑の影響でコシヒカリが幻に?2024年の米不足と温暖化の関係を探る – あはよくば50, 8月 11, 2025にアクセス、 https://awayokuba50.hatenablog.com/entry/2024/08/18/154516
- 2024肥料年度秋肥 高度化成+10.6% 3期ぶり値上げ 円安が要因 全農 – 農業協同組合新聞, 8月 11, 2025にアクセス、 https://www.jacom.or.jp/shizai/news/2024/05/240531-74476.php
- 令和6肥料年度 肥料価格について – アグリポートWeb, 8月 11, 2025にアクセス、 https://agriport.jp/information/ap-19167/
- 肥料はこの先どうなるの? – アグリポートWeb, 8月 11, 2025にアクセス、 https://agriport.jp/agriculture/ap-22821/
- 米をめぐる状況について 2024年11月5日 農産局 – 農林水産省, 8月 11, 2025にアクセス、 https://www.maff.go.jp/j/shokusan/kikaku/kakaku_keisei/attach/pdf/imdex-85.pdf
- 『令和のコメ騒動』(4)令和のコメ騒動が暗示する政策課題の深層, 8月 11, 2025にアクセス、 https://www.mri.co.jp/knowledge/column/20250311_3.html
- お米の1人当たりの消費量はどのくらいですか。 – 農林水産省, 8月 11, 2025にアクセス、 https://www.maff.go.jp/j/heya/sodan/1808/01.html
- 【2024年お米不足】需給逼迫と価格高騰について | ツナギのお米マガジン, 8月 11, 2025にアクセス、 https://www.tsunagi-japan.co.jp/blog/komebusoku/
- 米食習慣の希薄化と米離れによる米消費減の加速化-とくに高齢者 – 農政調査委員会, 8月 11, 2025にアクセス、 https://apcagri.or.jp/apc/prescolumn/6520
- 【農林水産省】お米の価格について – YouTube, 8月 11, 2025にアクセス、 https://www.youtube.com/watch?v=IcePj-bTXVI&pp=0gcJCfwAo7VqN5tD
- 米:市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2024-2029) – グローバルインフォメーション, 8月 11, 2025にアクセス、 https://www.gii.co.jp/report/moi1443924-rice-market-share-analysis-industry-trends.html
- 米の生産量が世界で見るランキングと推移データ比較|主要国の特徴と地域別シェアも徹底解説, 8月 11, 2025にアクセス、 https://wiple-service.com/column/world-rice-production-ranking-trends-country-share/
- ⑤ コメの輸出・輸入 – 農林水産省, 8月 11, 2025にアクセス、 https://www.maff.go.jp/j/seisan/kikaku/attach/pdf/kome_siryou-252.pdf
- 令和6年の商業用米輸出、前年比+21%の4万5千t | ごはん彩々ニュース(GOHAN SAISAI NEWS), 8月 11, 2025にアクセス、 https://gohansaisai.news/news/article-13351/
- 2024年産米の収穫予想(7月31日現在), 8月 11, 2025にアクセス、 http://www.japan-rice.com/yosou2024.html
- 全国作況101の「平年並み」 米穀データバンク予想 – 農業協同組合新聞, 8月 11, 2025にアクセス、 https://www.jacom.or.jp/kome/news/2024/08/240819-75939.php
- 施設園芸等燃料価格高騰対策、農水省が2024年度補正予算で基金積み増し | ツギノジダイ, 8月 11, 2025にアクセス、 https://smbiz.asahi.com/article/15543436
- 【2024年】日本のコメ生産状況と推移 – お米の知恵袋, 8月 11, 2025にアクセス、 https://okome-chiebukuro.com/rice-harvest-amount-2024/
- 【2025年】米の県別・生産量ランキング – お米の知恵袋, 8月 11, 2025にアクセス、 https://okome-chiebukuro.com/rice-yield-ranking-2025/
- 2024年産米収穫量が4万トン減(2面・総合)【2024年11月4週号】 – NOSAI協会, 8月 11, 2025にアクセス、 https://www.nosai.or.jp/mt6/2024/11/post-8175.html
- 2 購入数量・支出金額の推移(家計調査) – 農林水産省, 8月 11, 2025にアクセス、 https://www.maff.go.jp/j/seisan/keikaku/soukatu/attach/pdf/mr-862.pdf
- 令和5年産米の契約数量253.6万トンと販売数量208.2万トンを徹底分析-令和6年7月末時点の民間在庫82万トンの動向 – 【公式】福岡の求人広告は株式会社パコラ, 8月 11, 2025にアクセス、 https://www.pacola.co.jp/%E4%BB%A4%E5%92%8C5%E5%B9%B4%E7%94%A3%E7%B1%B3%E3%81%AE%E5%A5%91%E7%B4%84%E6%95%B0%E9%87%8F253-6%E4%B8%87%E3%83%88%E3%83%B3%E3%81%A8%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E6%95%B0%E9%87%8F208-2%E4%B8%87%E3%83%88%E3%83%B3/
- 肥料市場に関する調査を実施(2025年) | 市場調査とマーケティングの矢野経済研究所, 8月 11, 2025にアクセス、 https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3836
- 2024~2028年度石油製品需要見通し – 経済産業省, 8月 11, 2025にアクセス、 https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/demand_forecast/pdf/20240426_1.pdf
- 委託販売の流れ (平成28年産まで), 8月 11, 2025にアクセス、 https://org.ja-group.jp/challenge/wp_challenge/wp-content/uploads/2019/03/20190321134906335.pdf
- 『令和のコメ騒動』(3)コメ価格高騰の構造と備蓄米放出の意味 – 三菱総合研究所, 8月 11, 2025にアクセス、 https://www.mri.co.jp/knowledge/column/20250311_2.html
- 24年コメ購入量6%増 消費者、品薄不安視か 総務省家計調査 | BUSINESS LIVE – 四国新聞, 8月 11, 2025にアクセス、 https://www.shikoku-np.co.jp/bl/digital_news/article.aspx?id=K2025032300000009600
- 米国農務省穀物等需給報告(2024 年5月 10 日発表のポイント), 8月 11, 2025にアクセス、 https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/jki/attach/pdf/index-47.pdf

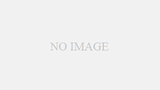
コメント