エグゼクティブ・サマリー
本レポートは、通称「小泉備蓄米」問題を多角的に分析し、物価高騰が農家の抱える懸念の直接的な原因であるか否かを検証する。分析の結果、2024年から2025年にかけての米価危機の発端は、広範な物価高騰が生産コストを押し上げ、同時に代替食品からの需要シフトを引き起こしたことに起因する、強力な「触媒」であったと結論付ける。
しかし、現役農家が現在最も恐れている問題の「直接的」な原因は、物価高騰そのものではない。その恐怖の根源は、危機に対応するために政府が実施した政策、すなわち生産コストを大幅に下回る価格での備蓄米大量放出にある。この市場介入は、消費者物価の抑制を意図したものであったが、結果として米価に不当な上限を設定し、稲作経営の経済的存立性を根底から脅かすという、意図せざる結果を招いている。農家は、これが将来の生産意欲の減退と作付面積の減少につながることを危惧している。
この一連の出来事は、日本の稲作が長年抱えてきた構造的脆弱性―すなわち、農業従事者の深刻な高齢化、長期的な米消費量の減少、そして過去の生産調整政策の遺産―を浮き彫りにした。
本レポートは、今後の日本の食料安全保障政策が重大な岐路に立たされていることを指摘する。大規模農家への「直接支払い」による構造改革を目指す路線と、広範な農家を対象とする「収入保険」によるセーフティネットを重視する路線が対立する中、消費者、生産者、そして国家の食料安全保障の三者をいかにして両立させるか。短期的な価格抑制策を超えた、持続可能で強靭な農業システムを構築するための長期的視点に立った政策提言をもって、本レポートを締めくくる。
I. 危機の解剖:「令和の米騒動」の構造
A. 完璧な嵐:供給ショックと需要シフトの合流
2024年から顕在化した米価高騰、通称「令和の米騒動」は、単一の原因によるものではなく、供給と需要の両面における複数の要因が連鎖的に作用した結果である。
第一の引き金は、供給サイドを襲った2023年夏の記録的な猛暑であった。この異常気象は、全国的な高温障害を引き起こし、米の品質を著しく低下させると同時に収穫量を減少させた 1。特に、日本の食卓で人気の高いコシヒカリへの影響は甚大で、例えば新潟県産米の一等米比率は、平年の75.3%からわずか4.9%へと壊滅的な水準まで落ち込んだ 1。これにより、消費者が求める高品質な主食用米が市場から枯渇し、品薄感が一気に高まった。
さらに、この危機をより深刻化させたのは、一般には見過ごされがちな「ふるい下米」の供給崩壊である。ふるい下米は、選別過程で取り除かれる低等級の米であり、主に外食・中食といった業務用や加工用原料として安価に流通している。このふるい下米の供給量が、2023年産では前年の51万トンから32万トンへと激減した 1。これにより、業務用米市場が深刻な原料不足に陥り、弁当業者やレストランチェーンなどは、本来の供給ルートを離れて、より高価な主食用米市場での原料確保を余儀なくされた。この動きが、主食用米の需給をさらに逼迫させ、価格上昇に拍車をかけた。つまり、この危機は単なる米の「量的」な不足ではなく、高品質米と低価格業務用米という二つの異なる市場が同時に崩壊した「質的・構造的」な危機であった。
需要サイドでは、世界的なインフレ環境が大きな役割を果たした。ウクライナ情勢などを背景とした小麦価格の高騰は、パンや麺類といった代替主食の価格を押し上げた。相対的に価格が安定していた米に割安感が生まれ、消費者の需要が米へとシフトした 1。これに加えて、コロナ禍からの経済回復に伴う外食産業の需要回復や、インバウンド観光客の急増も米の需要を押し上げる要因となった 1。
これらの経済的要因に、心理的要因が追い打ちをかけた。メディアが「令和の米騒動」として大々的に報じたことや、南海トラフ巨大地震の臨時情報発表などが重なり、消費者の間に食料備蓄への意識が高まった 1。これがスーパーマーケットなどでの一時的な買いだめ行動を誘発し、店頭での品切れを発生させ、社会的なパニックを増幅させる結果となった。
B. 価格高騰の定量化:生産現場から食卓まで
この需給の歪みは、具体的な価格データに明確に表れている。
卸売段階では、米穀卸売業者が全国農業協同組合連合会(JA全農)などから玄米を買い付ける価格が異常な高騰を見せた。60kgあたりの相対取引価格は、わずか1年間で1万5000円台から2万7000円台へと、実に8割もの上昇を記録した 3。
この卸売価格の上昇は、速やかに小売価格に転嫁された。スーパーマーケットの店頭では、精米5kgあたりの価格が従来の2500円程度から4200円にまで跳ね上がるケースも見られた 3。これは、月に5kg程度の米を消費する標準的な家庭にとって、年間で約2万円の追加負担を意味し、家計を直接圧迫する事態となった 4。
こうした価格高騰の背景には、深刻な在庫の枯渇があった。農林水産省のデータによれば、民間の米穀在庫量は、2022年11月末の330万トンから、2024年11月末には260万トンへと大幅に減少した。特に市場の需給バッファーとして機能する1年古米の在庫が、同期間に49万トンから18万トンへと激減したことは、市場の脆弱性を象徴している 1。この在庫の薄さが、わずかな需給の変動にも価格が過剰に反応する状況を生み出していた。
II. 政府の対応:備蓄米放出という両刃の剣
A. 政策の実行:速度と量を最優先した市場介入
深刻化する米価高騰と社会不安に対し、小泉進次郎農林水産大臣が率いる農林水産省は、政府備蓄米の大量放出という強力な市場介入に踏み切った。
その規模は異例のものであった。政府が保有する約100万トンの備蓄米のうち、最終的に80万トンが市場に放出される計画が示された 5。これは、過去3年間で累積したと推定される約60万トンの需給ギャップを埋め、さらに市場に安心感を与えるに十分な量とされた 6。
政策実行にあたり、政府は「スピード」を最優先した。従来の競争入札方式では、米が消費者の手元に届くまでに時間がかかると判断し、卸売業者などと直接契約を結ぶ「随意契約」へと方式を転換した 7。小泉農水相は、6月初旬には店頭に米を並べるという明確な目標を掲げ、迅速な流通を促した 9。
さらに、今回の介入が単なる供給量の増加に留まらない、積極的な価格抑制策であったことは特筆すべきである。政府は「精米5kgで2000円」という具体的な小売価格の目標を公に掲げた 6。この公的な価格目標の設定は、後の農家の懸念に直結する重要な政策決定であった。
これらの主要な施策に加え、政府は地方への輸送費を国が負担することで流通コストを抑制したり、投機的な転売を防ぐための罰則付き規制を導入したりするなど、安価な米が確実に消費者に届くための支援策も講じた 8。
B. 短期的な安定化と意図せざる副作用
政府による迅速かつ大規模な介入は、市場のパニックを鎮静化させるという短期的な目的においては、一定の効果を発揮した。備蓄米の大量供給は、需給逼迫感を和らげ、価格の際限ない上昇に歯止めをかけた 5。
小泉農水相は、この介入によって「三極化」した市場が形成されることを意図していた。すなわち、高価格帯の銘柄米、中価格帯の入札米、そして低価格帯の備蓄米という三つの選択肢を消費者に提供することで、物価高に苦しむ家計に手頃な選択肢を与えつつ、高級米市場の価格体系を完全に破壊することは避けるという狙いがあった 7。
しかし、この強力な介入は、新たな問題の火種を生み出した。特に卸売業者は、絶妙なタイミングの悪さに苦しめられた。彼らの多くは、価格がピークにあった時期に、60kgあたり2万7000円という高値で在庫を仕入れていた。そこへ政府が「5kgで2000円」という価格をベンチマークとする安価な米を大量に市場に投入したため、高値で仕入れた在庫を抱えたまま、価格競争に巻き込まれることになった。これは、卸売業者に莫大な損失をもたらすリスクを生じさせ、市場の正常な価格形成機能を歪める結果となった 3。
この一連の動きは、政府の備蓄米に対する市場の認識を根本的に変えてしまった。本来、備蓄米制度は、大規模な自然災害や地政学的リスクといった、国家の食料供給が危機に瀕する「非常事態」に備えるための食料安全保障の最後の砦である 11。しかし、今回の政府の対応は、備蓄米を消費者物価を抑制するための「価格統制ツール」として活用するものであった。この政策転換は、生産者に対し、政府は米価が政治的に不都合な水準まで上昇すれば、いつでも市場に介入して価格を抑制するという強力なメッセージを送った。これは、生産者の将来に対する予測可能性を著しく低下させ、長期的な生産投資への意欲を削ぐ危険な前例となった。
III. 農家のジレンマ:なぜ解決策が恐怖の源泉なのか
A. 生存の経済学:コストと価格の埋めがたい乖離
政府の備蓄米放出が農家にとって恐怖の対象となっている根本的な理由は、極めて単純な経済的現実に起因する。それは、政府が設定した放出価格と、農家が米を生産するために要するコストとの間に、経営の存続を不可能にするほどの巨大な隔たりが存在するからである。
まず、生産コストはインフレ圧力により高騰を続けている。肥料、燃料、農業機械などの価格上昇は、農家の経営を直接的に圧迫している 13。農林水産省の統計によれば、令和4年産の米の60kgあたりの全算入生産費(資本利子・地代を含む)は平均で1万5273円に達しており 16、秋田県大潟村の試算では1万5948円という数字も示されている 17。これが、農家が再生産を可能にするための最低限の価格水準である。
一方で、政府が卸売業者に放出した備蓄米の売渡価格は、60kgあたり約1万1010円(税抜き)であった 17。
この二つの数字を比較すれば、農家の恐怖の源泉は明白である。市場価格が政府の放出した備蓄米の価格水準に収斂した場合、農家は60kgの米を生産するごとに約5000円の確定的な損失を被ることになる。これは、低収益なビジネスが、確実に赤字を生み出す事業へと変貌することを意味する。全国有数の米産地である大潟村議会が提出した意見書は、この放出価格が「再生産可能な価格を大幅に下回る」ものであり、稲作経営そのものを成り立たせなくすると、強い危機感を表明している 17。
表1:日本の稲作における収益性ギャップの構造(2024-2025年)
|
項目 |
60kgあたり価格(玄米) |
5kgあたり価格(精米・小売換算) |
生産コスト比での農家損益(60kgあたり) |
|
生産コスト |
約 ¥15,948 17 |
約 ¥2,650 |
¥0 (損益分岐点) |
|
危機前の卸売価格 |
約 ¥15,000 3 |
約 ¥2,500 |
-¥948 |
|
政府備蓄米の放出価格 |
¥11,010 17 |
約 ¥1,835 |
-¥4,938 |
|
政府の目標小売価格 |
約 ¥12,000 (換算値) |
¥2,000 |
-¥3,948 |
注:小売換算価格および農家損益は、精米歩合や流通マージンを考慮した概算値。
B. 価格上限という前例:市場価格の構造的下方圧力への懸念
この直接的な経済的脅威に加え、農家は政府の介入がもたらす長期的な市場への悪影響を深く懸念している。
第一に、政府が「5kgで2000円」という目標価格を大々的に公表したことで、消費者の価格認識に強力な「アンカー」が打ち込まれてしまった。大潟村議会が警告するように、これが米の「適正価格」であるという誤解を消費者の間に広げ、将来的に農家が持続可能な経営を維持できる価格水準まで市場価格が回復することを、政治的にも商業的にも極めて困難にする可能性がある 17。
第二に、この介入は翌年(令和7年産)の作付け意欲に深刻な冷や水を浴びせている。政府が価格上昇を力ずくで抑え込む姿勢を見せたことで、農家は将来の価格見通しに対して極度の不確実性を抱くようになった。もし増産すれば、供給過剰で価格が暴落するのではないかという恐怖が、生産現場に広がっている。三菱総合研究所のレポートも、農業関係者の間で「みんなが増産したら、コメの価格が下がってしまうのではないか」という懸念が根強いことを指摘している 6。これは、農林水産省が掲げる56万トンの増産目標 18 とは全く逆行するインセンティブを市場に与えてしまっている。
最後に、この状況は農家に経済的な打撃だけでなく、精神的な疲弊と幻滅をもたらしている。ある米農家は、自らの作物が社会にとって不可欠であると再認識された喜びと、長年努力して築き上げてきた顧客への直接販売モデルが、安価な政府米の流入によって無に帰すことへの虚しさとが入り混じる、複雑な心境を吐露している 19。この感情的なダメージは、数字には表れない、日本の農業の持続可能性を蝕む深刻な要因である。
IV. 物価高騰の役割:直接原因か、構造的触媒か
A. 物価高騰がもたらす直接的なコスト増
広範な物価高騰(インフレ)は、米農家の経営を直撃する直接的なコストドライバーとして機能した。農林水産省が公表する農業物価指数は、その影響を客観的に示している。農業生産資材の総合価格指数は、令和2年を100として上昇を続けており、令和7年3月時点では前年同月比で2.1%の上昇となった。この背景には、特に光熱動力費の上昇がある 20。
より詳細なデータを見ると、その影響はさらに深刻である。ある年の調査では、肥料費が前年比で27.1%、農業用燃料費が13.4%も急騰したことが報告されている 13。米の生産費において、肥料費や農機具を動かす燃料費は大きな割合を占めるため 14、これらの資材価格の高騰は、規模の大小を問わず全ての農家の収益性を直接的に悪化させた。特に、経営基盤の弱い小規模農家にとっては、死活問題となりうるほどの経営圧迫要因となっている 14。したがって、一般的なインフレ、特にエネルギーや輸入化学原料(肥料の主成分)の価格上昇は、農家の経営難の直接的な原因の一つであることは間違いない。
B. 物価高騰がもたらす間接的な需要シフト
物価高騰は、コスト面だけでなく、需要面からも米市場に間接的ながら強力な影響を及ぼした。
これは「代替効果」として説明できる。世界的な穀物価格の上昇は、日本国内の小麦製品、すなわちパンや麺類の価格を押し上げた。2023年の猛暑による品質問題が顕在化するまで比較的価格が安定していた米は、これらの代替主食と比較して割安感が増した。その結果、消費者の食費節約志向が働き、需要の一部がパンや麺類から米へとシフトした 1。
この予期せぬ需要の増加は、農林水産省の当初の需給見通しを上回るものであった。結果として、ただでさえ供給が細っていた市場の在庫をさらに速いペースで減少させ、需給の不均衡を拡大させる一因となった 1。
C. 因果関係の結論:農家の恐怖の直接原因ではなく、強力な触媒
以上の分析を総合すると、今回の問題における物価高騰の役割が明確になる。
物価高騰は、日本の脆弱な米市場の均衡を崩壊させた強力な「触媒」であった。それは、生産コストを押し上げて農家の経営を圧迫すると同時に、需要を喚起して在庫を枯渇させるという、二方向からの同時攻撃であった。この圧力が、「令和の米騒動」という危機的状況を生み出す土壌を形成した。
しかし、本稿の核心的な問いである「物価高騰は、農家が現在抱える懸念の直接的な原因か」に対しては、その答えは「否」である。農家が今まさに直面している恐怖、すなわち再生産不可能な価格水準が市場の常識となりかねないという懸念は、物価高騰という経済現象の必然的な結果ではない。それは、物価高騰という危機に対して政府が選択した「政策的対応」―すなわち、生産コストを無視した価格での備蓄米大量放出―の直接的かつ直接的な帰結である。
この状況は、政府の政策決定における根本的な断絶を露呈している。政府は、一方では消費者物価指数を抑制するというマクロ経済的な課題に取り組み、そのための道具として備蓄米を利用した。しかしその一方で、農林水産省は収入保険や各種交付金といったミクロな生産者支援策も講じている 22。問題は、これらの政策が統合されていないことにある。価格統制という「左手」の政策が、市場価格を破壊することで、生産者支援という「右手」の政策の効果を無に帰している。政府は、消費者物価と生産者の経営存続性を別々の問題として扱っているが、実際にはそれらは同じコインの裏表であり、一方を無視した政策は必ずもう一方に深刻な歪みをもたらすのである。
V. 構造的脆弱性:数十年にわたる日本稲作の土台沈下
今回の危機は突発的な出来事ではなく、日本の稲作が数十年にわたって蓄積してきた構造的な脆弱性が、物価高騰という外部ショックによって一気に露呈したものである。
A. 人口動態という時限爆弾:高齢化と後継者不足
日本の農業が直面する最も深刻な課題は、労働力の高齢化と枯渇である。2023年時点で、基幹的農業従事者の平均年齢は68.7歳に達し、その約7割が65歳以上である 23。一方で、49歳以下の若手・中堅層は全体のわずか11%に過ぎない 24。
特に、昭和一桁生まれ(1926年~1934年)の世代が日本の農業を長年支えてきたが、彼らが引退期を迎える中で、後継者不足は危機的な状況にある 25。これは、たとえ米価が上昇し、増産の好機が訪れたとしても、実際に生産を担う「人」がいないという、根本的な供給能力の制約を意味する。
B. 減反政策の遺産:政策が作り出した供給制約
日本の米政策は、長らく「減反(生産調整)」によって特徴づけられてきた。これは、主食用米の作付けを人為的に抑制し、農家に補助金を支払うことで、米価を高く維持することを目的とした政策であった 27。
この政策は2018年に公式には廃止されたものの、その影響は深く根を張っている。数十年にわたる減反政策は、農家の意識、農業インフラ、土地利用のあり方を「供給を抑制する」という方向に最適化させてきた。今回のように、急激な「増産」が求められる事態は、長年の政策思想と現場の慣行とは真逆の方向転換であり、容易には対応できない。三菱総合研究所が「より純粋なコメの増産」の必要性を訴えているのは、この根深い減反マインドからの脱却がいかに困難であるかを物語っている 6。
C. 静かなる衰退:日本人の食生活の変化
日本の稲作が直面するもう一つの長期的な課題は、国内市場の縮小である。日本人の一人当たりの米消費量は、1962年の年間118.3kgをピークに、一貫して減少し続けてきた。2022年にはその半分以下である50.8kgにまで落ち込んでいる 30。
直近では、前年同月比での消費量増加が11ヶ月続くという異例のデータもあるが 33、これは物価高騰による他食品からの代替需要という一時的な現象である可能性が高く、長期的な減少トレンドが反転したと見るのは早計である。
この国内需要の長期低落こそが、減反政策の根本的な原因であり、日本の稲作セクター全体の活力を削いできた。縮小する市場は、外部からのショックを吸収する能力が低く、生産者の長期的な投資意欲を減退させる要因となっている。
VI. 政策の岐路:日本の米の持続可能な未来を描くために
A. 直接支払い vs 収入保険:二つの対立するビジョン
今回の危機を経て、日本の米政策は、その将来像をめぐる二つの対立するビジョンの間で、重大な選択を迫られている。
一つは、石破茂首相が言及し、山下一仁氏のような専門家が支持する「直接支払い」を軸とした構造改革路線である 3。この構想は、減反のような生産調整を完全に撤廃し、米価を市場原理に委ねて低下させることを許容する。その上で、政府は生産量とは切り離された形で、5ヘクタール以上といった効率的な大規模農家に対象を限定して直接的な所得補償を行う。この政策の狙いは、非効率な小規模兼業農家の退出を促し、意欲と能力のある担い手への農地集積を進めることにある。これにより、規模の経済が働き生産コストが低下し、日本の米の国際競争力が高まる。消費者は安価な米の恩恵を受け、納税者も補助金総額の抑制という利益を得られる「三方よし」の政策だと主張されている。
もう一方は、小泉農水相が推進する現行の「収入保険」を拡充する路線である 22。これは、青色申告を行う農家であれば規模を問わず加入できる、より広範なセーフティネットである。価格の低下や収量の減少によって収入が減った場合に、その一部を補填する仕組みだ。批判的な立場からは、この制度は非効率な小規模農家を温存し、農業の構造改革を阻害する「バラマキ」政策であると指摘される。価格水準そのものが低下する局面では、補填額が膨れ上がり、国家財政に過大な負担をかけるリスクも懸念されている 3。
B. 緊急対応を超えて:長期戦略の必要性
目下の課題として、今回の介入で枯渇した政府備蓄米の回復が挙げられる。自民党の森山裕幹事長は、食料安全保障の観点から「できるだけ早く」備蓄水準を元に戻す必要があると強調している 2。しかし、市場から米を買い上げて備蓄を積み増す行為は、米価に上昇圧力をかけるため、消費者物価の安定を目指す政府の目標と自己矛盾をきたす可能性がある。政府自身の計画では、数年かけた「自然回復」を基本としつつ、買入数量の増加も検討するとしているが 12、その具体的な道筋は不透明である。
さらに重要なのは、生産者が再生産可能だと感じられる、持続可能な価格水準をいかにして再構築するかという点である。森山幹事長は、生産者と消費者の双方が納得できる価格として「5kgあたり3000円から3500円」という水準に言及しており 2、これは政府が一時掲げた「2000円」という目標からの大幅な方針転換を示唆している。この価格水準を、市場メカニズムと政策支援を組み合わせていかに実現するかが、今後の焦点となる。
C. 強靭なシステムへの提言
日本の稲作が今回の危機から教訓を学び、より強靭なシステムへと移行するためには、以下の視点に基づいた統合的な政策が不可欠である。
第一に、消費者物価政策と生産者支援政策の断絶を乗り越え、両者を一体として設計すること。短期的な価格抑制のために生産基盤を破壊するような政策は、長期的にはより深刻な食料供給不安を招く。
第二に、単純な所得補償を超えた、生産基盤そのものを強化する構造改革への投資を優先すること。森山幹事長が言及したような、圃場の大区画化を進める土地改良事業への重点的な予算配分は、生産コストを恒久的に引き下げる効果が期待できる 2。
第三に、政府備蓄米の役割と発動条件を再定義し、その運用に透明性と予測可能性を持たせること。備蓄米を安易な価格統制の手段として用いることをやめ、真の食料安全保障上の危機に限定して発動するルールを明確化することで、生産者の政府に対する信頼を回復する必要がある。
日本の食卓の根幹をなす米の未来は、目先の危機対応に追われるのではなく、人口減少と国際環境の変化という大きな潮流を見据えた、長期的かつ一貫性のある国家戦略を描けるかどうかにかかっている。
引用文献
- 令和の米騒動を専門家が解説! お米を取り巻く経済の現状と、2025 …, 8月 16, 2025にアクセス、 https://gohan.soramido.com/magazine/reiwa-komesoudou2025
- 【インタビュー】 自民党 森山裕幹事長 備蓄米水準 できるだけ早く …, 8月 16, 2025にアクセス、 https://www.jacom.or.jp/noukyo/rensai/2025/07/250714-83207.php
- JAと農水省の逆襲がはじまった…小泉進次郎の「2000円の備蓄米」に …, 8月 16, 2025にアクセス、 https://cigs.canon/article/20250623_8992.html
- 【令和の米騒動】2025年最新動向|政府備蓄米放出の効果と今後 – 株式会社エデンレッドジャパン, 8月 16, 2025にアクセス、 https://edenred.jp/article/productivity/220/
- 「小泉備蓄米」これからじわじわと問題化…現役農家が今もっとも …, 8月 16, 2025にアクセス、 https://dot.asahi.com/articles/-/262844
- 『令和のコメ騒動』(6)備蓄米放出後の最重要課題 – 三菱総合研究所, 8月 16, 2025にアクセス、 https://www.mri.co.jp/knowledge/column/20250606.html
- 小泉農林水産大臣記者会見概要, 8月 16, 2025にアクセス、 https://www.maff.go.jp/j/press-conf/250610.html
- コメ価格高騰に政府が緊急対応 『5キロ2000円』備蓄米放出の裏で農家に不安 – coki, 8月 16, 2025にアクセス、 https://coki.jp/article/news/53068/
- 小泉農林水産大臣記者会見概要, 8月 16, 2025にアクセス、 https://www.maff.go.jp/j/press-conf/250527.html
- 備蓄米12万トン受付開始 小泉農水大臣「転売規制を導入する方針」 – YouTube, 8月 16, 2025にアクセス、 https://www.youtube.com/watch?v=TzY_wrWozxE
- 備蓄米とは古い米?政府から放出される米はいつの米なのか・仕組みや味についてもわかりやすく解説 – Spaceship Earth(スペースシップ・アース)|SDGs・ESGの取り組み事例から私たちにできる情報をすべての人に提供するメディア, 8月 16, 2025にアクセス、 https://spaceshipearth.jp/bitikumai-seihu/
- 米の備蓄運営について ② – 農林水産省, 8月 16, 2025にアクセス、 https://www.maff.go.jp/j/seisan/keikaku/attach/pdf/bichikumai-8.pdf
- 物価高騰により稲作農家の2022年の経営実績はどうなるのか? | 農業利益創造研究所, 8月 16, 2025にアクセス、 https://nougyorieki-lab.or.jp/management/9852/
- 日本の米生産原価(人件費除く)の規模別比較(2022~2024年)|oft0n@AIエンジニア – note, 8月 16, 2025にアクセス、 https://note.com/oft0nland/n/n1fa94ea1c638
- 生産費は経営総体と品目別で検討を – アグリポートWeb, 8月 16, 2025にアクセス、 https://agriport.jp/agriculture/ap-1798/
- 令和4年産 米生産費(個別経営体) – 農林水産省, 8月 16, 2025にアクセス、 https://www.maff.go.jp/j/tokei/kekka_gaiyou/noukei/nou_seisanhi/r4/kome/index.html
- 備蓄米の格安放出で農家圧迫 米どころ秋田の大潟村議会 小泉農相に …, 8月 16, 2025にアクセス、 https://www.jacom.or.jp/kome/news/2025/06/250617-82534.php
- 小泉農林水産大臣記者会見概要, 8月 16, 2025にアクセス、 https://www.maff.go.jp/j/press-conf/250715.html
- 私たち「“直売”米農家」のやりきれない思い…「備蓄米の放出」に思うこと【お米農家のヨメごはん】, 8月 16, 2025にアクセス、 https://kufura.jp/family/childcare/662354
- 農業物価指数(令和7年3月):農林水産省, 8月 16, 2025にアクセス、 https://www.maff.go.jp/j/tokei/kekka_gaiyou/noubukka/noubukka_m/r7/m3.html
- 米の生産コスト4割削減に向けて, 8月 16, 2025にアクセス、 https://www.jataff.or.jp/project/inasaku/koen/koen_h26_2.pdf
- 小泉農林水産大臣記者会見概要, 8月 16, 2025にアクセス、 https://www.maff.go.jp/j/press-conf/250808.html
- 日本の農業人口はどう推移している? 農業現場へ与える影響とは – minorasu(ミノラス, 8月 16, 2025にアクセス、 https://minorasu.basf.co.jp/80076
- (1)基幹的農業従事者 – 農林水産省, 8月 16, 2025にアクセス、 https://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/r3/r3_h/trend/part1/chap1/c1_1_01.html
- 図録 農業者の高齢化-年齢別農業従事者数, 8月 16, 2025にアクセス、 https://honkawa2.sakura.ne.jp/0530.html
- 人口構造の変化等が農業政策に与える影響と課題について – 総務省, 8月 16, 2025にアクセス、 https://www.soumu.go.jp/main_content/000578741.pdf
- 新しくなった食糧法(改正食糧法)について – 玉川学園, 8月 16, 2025にアクセス、 https://www.tamagawa.ac.jp/sisetu/kyouken/rice/syokuryouhou/index.html
- 食糧管理制度 – Wikipedia, 8月 16, 2025にアクセス、 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%9F%E7%B3%A7%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%88%B6%E5%BA%A6
- コメ高騰、備蓄米放出…亡国農政のツケは国民に回る | キヤノングローバル戦略研究所, 8月 16, 2025にアクセス、 https://cigs.canon/article/20250305_8672.html
- 米情勢.pdf, 8月 16, 2025にアクセス、 https://www.zennoh.or.jp/press/release/2022/10/12/%E7%B1%B3%E6%83%85%E5%8B%A2.pdf
- Ⅰ 米の消費に関する動向 – 農林水産省, 8月 16, 2025にアクセス、 https://www.maff.go.jp/j/seisan/kikaku/pdf/data01.pdf
- 米消費の減少と中食化の世代別分析 ―公表の食料消費統計に依拠して― – 日本農業研究所, 8月 16, 2025にアクセス、 http://www.nohken.or.jp/KOUENKAIKIROKU/No.8_2020/kobetsuPDF/2020-3_aoyagiitsuki.pdf
- 1人当たり米の消費量 11か月連続で前年比増 2月は1.3%増 米穀機構調査 2025年3月26日 – JAcom, 8月 16, 2025にアクセス、 https://www.jacom.or.jp/kome/news/2025/03/250326-80453.php
- 【収入保険】私の選択・加入者の声, 8月 16, 2025にアクセス、 https://nosai-zenkokuren.or.jp/subscriber-voice03.html

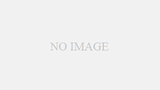
コメント