2025年版フィッシング詐欺対策完全ガイド:あなたのデジタル資産を守るための知識と技術
【序章】 あなたの日常を狙う「見えない釣り針」:フィッシング詐欺の正体
宅配業者から荷物の不在通知を知らせる一通のSMSメッセージが届く。ちょうど何かを注文していたため、何の気なしに記載されたURLをクリックする。このほんの数秒の行動が、犯罪者に自身の個人情報への扉を開けてしまう瞬間となり得る 1。これは特別な物語ではなく、今日のデジタル社会に生きる誰もが直面しうる現実である。
フィッシング詐欺は、もはや稀なサイバー犯罪ではない。フィッシング対策協議会へ寄せられる報告件数は過去最多を更新し続けており、月によっては数十万件にものぼる 3。これは、オンラインで活動するほぼ全ての人が、詐欺の標的となりうる「デジタルなパンデミック」と呼ぶべき状況を示している。
では、「フィッシング詐欺」とは一体何であろうか。この言葉は、魚釣りの「fishing」と、「洗練された」を意味する「sophisticated」を組み合わせた造語であるとされている 3。その名の通り、詐欺師は本物そっくりに作り込んだ「餌」(偽のメールやSMS)を使い、標的となる「魚」(被害者)を巧みに誘い出す。そして、本物と見分けがつかない「釣り場」(偽のウェブサイト)へと誘導し、そこで個人情報や金融情報といった最も価値のある「獲物」を釣り上げるのである 6。
本レポートは、2025年8月現在の最新の状況を踏まえ、読者がこの見えない脅威から自身を守るための知識と具体的な防御策を提供することを目的とする。かつて有効だった「怪しいメールの件名に注意する」「URLが『http』ではなく『https』であることを確認する」といった古い常識は、もはや通用しない。敵は進化しており、我々の防御策もまた進化しなければならない。本ガイドが、そのための羅針盤となることを目指す。
【第1部】 2025年、フィッシング詐欺の「今」:巧妙化する手口の最前線
フィッシング詐欺の手口は、単純な誤字脱字だらけのメールを送る段階から、テクノロジーと心理学を駆使した高度な攻撃へと劇的に進化した。ここでは、その最前線で用いられている攻撃手法を解き明かす。
1.1. 伝統的手口の進化:メール(フィッシング)とSMS(スミッシング)
フィッシング攻撃の根幹をなすのは、依然として電子メールとSMSである。しかし、その質は数年前とは比較にならないほど向上している。
- 電子メール(フィッシング)
古典的な手法でありながら、その巧妙さは危険なレベルに達している。攻撃者は現在、銀行、大手ECサイト、公的機関などが送信する正規のメールを完璧に複製する能力を持つ 1。ロゴやデザインはもちろんのこと、文面も本物と見分けがつかないほど自然であり、受信者を巧みに騙して偽サイトへと誘導する。 - SMS(スミッシング)
SMS(ショートメッセージサービス)を利用したこの手口は、その効果の高さから主流となりつつある。電子メールよりもパーソナルで緊急性が高いと感じられやすく、人々が常に携帯しているスマートフォンに直接届くため、開封率が非常に高い 1。特に、「宅配業者からの不在通知」「携帯電話会社からの未払い料金の警告」「カード会社からの不正利用検知」といった内容は、日常生活に密着しているため、多くの人が疑いなくリンクをクリックしてしまう傾向にある 7。
これらの進化は、フィッシング詐欺を見抜くための伝統的な「危険信号(レッドフラグ)」が無効化されつつあるという、重大な事実を示している。かつては、「不自然な日本語」「誤字脱字」「安全でないhttp接続」などが詐欺を見分けるポイントだとされてきた。しかし、2025年の詐欺師たちは、AIを活用して文法的に完璧な日本語の文章を生成し 8、ウェブサイトを寸分違わず複製する 8。さらに、偽サイトであってもSSL証明書を容易に取得できるため、ブラウザのアドレスバーには安全な接続を示す「鍵マーク」が表示されるのが当たり前となっている 8。
この現実は、「信頼性のパラドックス」を生み出している。つまり、私たちが安全の証として信頼するように教えられてきた視覚的なサイン(プロフェッショナルなデザイン、鍵マークなど)が、今や詐欺師に悪用されているのである 12。このため、防御戦略の核心は、メッセージを
受動的に見て判断することから、メッセージの外で能動的に事実確認を行うことへと移行しなければならない。もはや、見た目の欠陥を探すというアプローチは、2025年においては通用しない戦略なのである。
1.2. 新たな脅威:声(ビッシング)と検索エンジン(SEOポイズニング)の悪用
攻撃の経路はメールやSMSだけにとどまらない。より信頼させやすい媒体が悪用され始めている。
- ボイスフィッシング(ビッシング)
電話の「声(Voice)」を利用したこの手口は、急速に被害を拡大させている。詐欺師は銀行員、テクニカルサポート、あるいは警察官になりすまして標的に電話をかける 11。最初は自動音声で始まり、ユーザーが操作すると人間のオペレーターに繋がるケースも多い 13。文字だけのコミュニケーションとは異なり、人間の声には感情を揺さぶり、冷静な判断を奪う力がある。特に「緊急事態です」といった緊迫した口調で話されると、多くの人は疑うことを忘れ、指示に従ってしまう 13。 - SEOポイズニング
これは、検索エンジンの仕組みを逆手に取った巧妙な手口である。詐欺師は、特定のキーワード(例:「〇〇銀行 カスタマーサポート」)で検索した際に、自らが作成した悪質な偽サイトが検索結果の上位に表示されるように操作する 7。ユーザーは公式な情報を探しているつもりで、検索結果のリンクをクリックし、気づかぬうちに詐欺サイトへ足を踏み入れてしまう。正規サイトと誤認させるため、被害に気づきにくいのが特徴である 7。
1.3. テクノロジーの悪用:AI、QRコード、そしてSNS
最新技術は、詐欺師にとって強力な武器となっている。
- AI生成詐欺
生成AIは、フィッシング詐欺の世界におけるゲームチェンジャーである。自然言語処理技術により、ターゲットの状況や背景に合わせた、極めて説得力のある詐欺メールやメッセージを大量に自動生成できる 10。さらに深刻なのは、ディープフェイク技術の悪用である。企業の経営幹部の声や映像を偽造し、ビデオ会議を通じて従業員に不正な送金を指示するといった、映画のような手口が現実の被害として報告されている 14。 - QRコードフィッシング(クイッシング)
フィッシングサイトへのリンクをQRコードに埋め込むこの新しい手口は、「クイッシング」とも呼ばれる 15。多くのセキュリティソフトはテキストベースのURLをスキャンして危険を検知するが、画像であるQRコードを解析するのは難しく、フィルターをすり抜けてしまうことがある。これらのQRコードは、メールの本文だけでなく、公共の場に貼られたポスターや偽の駐車違反切符などに印刷されている場合もあり、注意が必要である 16。 - ソーシャルメディアフィッシング
X(旧Twitter)、Instagram、FacebookといったSNSプラットフォームも、詐欺の温床となっている 3。詐欺師は、有名ブランドの偽の公式ページを作成して悪質な広告を流したり、アカウントを乗っ取ってその人の友人リストにフィッシングリンクを送信したりする。友人からのメッセージという信頼性を悪用するため、非常に効果的な手口となっている 11。
【第2部】 詐欺師の心理術:なぜ私たちは騙されてしまうのか
フィッシング詐欺の成功は、技術的な巧妙さだけでなく、人間の心理的な脆弱性を突くことにかかっている。なぜ、注意しているはずの人間が騙されてしまうのか。そのメカニズムを理解することは、最も根本的な防御策となる。
2.1. 狙われるのは「心の隙」:多忙、疲労、そして思い込み
フィッシング詐欺に引っかかりやすいのは、情報リテラシーが低い人だけではない。むしろ、日々の業務に追われる多忙な人、疲れている人、あるいは多くの通知を処理することに慣れてしまっている人こそが、格好の標的となる 17。人間は、ストレス下や疲労時には注意力が散漫になり、批判的思考能力が低下する。詐欺師は、私たちが最も無防備になる、そうした「心の隙」を正確に狙ってくるのである。
2.2. 感情を操る7つのトリガー
詐欺師は、人間の基本的な感情を刺激することで、冷静な判断を麻痺させる。彼らが用いる代表的な心理的トリガーは以下の7つである。
- 恐怖 (Fear): 「お客様のアカウントが不正に利用されました」「セキュリティ上の問題で口座を凍結しました」といったメッセージで、深刻な事態が起きていると信じ込ませ、パニック状態に陥らせる 1。
- 欲望 (Greed): 「高額賞金に当選しました」「限定ポイントが付与されました」といった文言で、得をしたい、儲けたいという欲求を刺激する 1。
- 緊急性 (Urgency): 「24時間以内に対応しないとアカウントは削除されます」のように、行動までの時間制限を設けることで、じっくり考える余裕を奪い、即座の行動を促す 7。
- 権威 (Authority): 警察、国税庁、銀行といった、人々が通常従うべきだと考える組織になりすますことで、メッセージの信憑性を高め、指示に従わせやすくする 17。
- 好奇心 (Curiosity): 「あなたの荷物の配送状況が更新されました」「〇〇さんがあなたのプロフィールを閲覧しました」といった内容で、つい確認したくなる人間の好奇心をくすぐる 2。
- 信頼 (Trust): 友人や同僚のアカウントを乗っ取ってメッセージを送ったり、日常的に利用している有名ブランドになりすましたりすることで、受信者の警戒心を解く 1。
- 親切心 (Helpfulness): 「お客様の安全のため、アカウント情報の確認にご協力ください」のように、相手を助けたい、協力したいという善意の感情を利用する。
近年、これらのトリガーの使われ方にも変化が見られる。これまで詐欺の典型とされてきたのは、「アカウント停止」や「不正利用」といった恐怖や不安を煽るネガティブな文脈であった。しかし、利用者がこうした警告文への警戒を強めるにつれて、詐欺師たちはより巧妙なアプローチへとシフトしている。
その一つが、「ポイント付与」や「特別キャンペーン」といったポジティブな文脈の悪用である 15。PayPayやJCBカードをかたる詐欺の事例では、お得なキャンペーンを知らせる件名が多用されていることが報告されている 17。「脅威」を提示されると人間は防御的になるが、「機会」を提示されると警戒心が薄れ、それを逃したくないという気持ちが強くなる。この心理的な転換により、被害者はパニックに陥った「反応者」ではなく、報酬を期待する**意欲的な「参加者」**へと変貌させられる。彼らは自ら進んでリンクをクリックし、情報を入力してしまうのである。したがって、現代のサイバーセキュリティ意識は、「脅威に警戒せよ」というだけでなく、「うますぎる話にも懐疑的であれ」という新たな教訓を加えなければならない。
【第3部】 詐欺師の「なりすまし」図鑑:2025年版・要注意事例集
詐欺師は、私たちが日常的に利用し、信頼を置いている企業や公的機関になりすますことで、その防御網を突破しようと試みる。ここでは、2025年現在、特に報告が多く、注意が必要ななりすましの手口を具体的な事例と共に紹介する。手元に届いた不審なメールやSMSが、ここに挙げられたパターンと一致しないか確認することは、被害を未然に防ぐための有効な手段となる。
表1: 2025年版:フィッシング詐欺なりすまし手口の具体例
|
標的 (Target) |
手口の概要 (Tactic Overview) |
件名・SMS文面の例 (Example Subject Lines/SMS Text) |
狙われる情報 (Targeted Information) |
注意すべき点 (Key Points to Watch For) |
|
金融機関 (銀行・カード会社) りそな銀行, JCB, 三井住友, PayPayカード等 1 |
不正利用の警告、アカウントロック、セキュリティ更新、ポイント付与などを口実に偽サイトへ誘導。 |
「【重要】お客様のJCBカードがロックされています」 「【PayPay】2025年をスタートダッシュ!抽選イベント実施中!」 「【三井住友】お客様の銀行口座を一時凍結しています」 「ご請求金額のお知らせ【2025年6月請求】」 |
ID/パスワード、クレジットカード番号、セキュリティコード、暗証番号、個人情報 |
金融機関がメールやSMSで直接パスワードやカード番号全文を聞くことは絶対にない。緊急性を煽る文言は詐欺の典型。 |
|
ECサイト・宅配業者 Amazon, 楽天, ヤマト運輸, 佐川急便等 1 |
注文確認、決済エラー、不在通知、アカウント情報更新などを装う。 |
「お荷物のお届けにあがりましたが、不在の為持ち帰りました。下記よりご確認ください」 「【Amazon】プライム会費のお支払い方法に問題があります」 「購入確認メール」 |
ログイン情報、クレジットカード情報、住所、電話番号 |
大手宅配業者はSMSでの不在通知にURLを記載しないと公言している 10。決済情報は必ず公式サイトやアプリで直接確認する。 |
|
公的機関 国税庁 (e-Tax), 地方自治体, 警察庁等 14 |
税金の未納通知、還付金手続き、給付金の案内、法執行機関からの警告などを装う。 |
「【国税庁】e-Tax税務署からの【未払い税金のお知らせ】」 「【督促状】滞納した税金がございます。」 「【警察庁】セキュリティ警告:銀行口座の確認が必要です」 |
マイナンバーカード情報、銀行口座情報、個人情報 |
公的機関からの重要な連絡は郵送が基本。メールやSMSで納税や個人情報入力を直接要求することは稀。警察庁を騙るSMSも確認されている 19。 |
|
テック企業・通信キャリア Apple, Google, Microsoft, ドコモ, au, ソフトバンク等 17 |
アカウントのセキュリティ警告、ストレージ容量の警告、料金未払い通知。 |
「【NTTドコモ】dカードが利用停止のお知らせ」 「【Apple】あなたのアカウントはセキュリティ上の理由でロックされています」 「ANAマイレージクラブ:マイル加算手続きについて」 |
アカウントのID/パスワード、決済情報 |
ログインや支払い状況の確認は、必ず公式アプリやブックマークした公式サイトから行う。SMSでのアプリインストール誘導は特に危険 5。 |
【第4部】 あなたのデジタル護身術:鉄壁の多層防御戦略
巧妙化するフィッシング詐欺に対抗するためには、単一の対策に頼るのではなく、複数の防御策を組み合わせた「多層防御」のアプローチが不可欠である。ここでは、意識改革から具体的な技術設定まで、鉄壁の防御を築くための戦略を3つの層に分けて解説する。
4.1. 第1層:意識改革「クリックせず、まず確認」
最も重要かつ効果的な防御層は、技術ではなく、利用者自身の意識と行動習慣である。
- 黄金律:リンクを信用せず、自ら確認する
フィッシング対策における絶対的な黄金律は、**「受信したメールやメッセージ内のリンクやボタンから、重要なアカウントにログインしない」**ことである。銀行、ECサイト、SNSなど、重要なサービスを利用する際は、メッセージ内のリンクをクリックするのではなく、事前にブラウザにブックマーク(お気に入り登録)しておいた公式サイトや、スマートフォンにインストール済みの公式アプリからアクセスする習慣を徹底する 17。この一つの習慣を身につけるだけで、大多数のフィッシング攻撃は無力化できる。 - 健全な懐疑心の育成
自分に届く全てのメッセージ、特に何らかの行動や情報の入力を求めるものに対しては、「これは本物だろうか?」と一瞬立ち止まって考える健全な懐疑心を持つことが重要である。特に、第2部で解説したような感情的なトリガー(恐怖、欲望、緊急性など)が含まれている場合は、詐欺である可能性が極めて高いと判断すべきである。
4.2. 第2層:必須の技術設定「デジタルな鍵と鎧」
意識改革を土台とし、次に技術的な設定で防御を固める。これらは、万が一の際に被害を食い止めるためのセーフティネットとなる。
- 多要素認証(MFA/2FA)の絶対的な有効化
多要素認証は、フィッシングに対する最も強力な技術的防御策である。これは、パスワードに加えて、スマートフォンに送られる確認コードや指紋認証など、第二の認証要素を要求する仕組みである 22。たとえ詐欺師にパスワードを盗まれたとしても、この第二の要素がなければアカウントにログインすることはできないため、被害を劇的に減らすことができる 14。利用可能なサービスでは、必ず多要素認証を設定することが強く推奨される。 - パスワード管理の徹底
複数のサービスで同じパスワードを使い回すことは、非常に危険な行為である 20。一つのサイトからパスワードが漏洩すると、他のすべてのアカウントが連鎖的に乗っ取られる危険があるからだ。パスワード管理ツール(パスワードマネージャー)を利用すれば、各サイトごとに複雑でユニークなパスワードを自動生成し、安全に保管することができる 5。 - ソフトウェアの最新化
OS(オペレーティングシステム)、ブラウザ、各種アプリケーションを常に最新の状態に保つことは、基本的ながら極めて重要なセキュリティ対策である。ソフトウェアのアップデートには、発見されたセキュリティ上の脆弱性を修正するパッチが含まれている。これを怠ると、攻撃者に悪用される隙を与えることになる 16。 - セキュリティソフトの活用
信頼できるセキュリティ対策ソフトを導入することで、既知のフィッシングサイトへのアクセスを自動的にブロックしたり、悪意のある添付ファイルを検知したりすることができる 14。これらのソフトは、利用者が気づかないうちに危険なサイトへアクセスしようとした際の最後の砦となる 29。
4.3. 第3層:上級者向け見破り術「詐欺師のサインを読む」
基本的な対策を講じた上で、さらに詐欺の兆候を見抜く能力を高めるための知識を身につける。
- URLの解剖学
リンク先のURLを注意深く見ることで、偽サイトを見破れる場合がある。重要なのは、URLの「ドメイン名」を正しく識別することである。ドメイン名は、「https://」の直後から最初の「/」(スラッシュ)までの部分にある。例えば、https://secure.realbank.co.jp.login-update.com/ というURLの場合、本当のドメインは login-update.com であり、realbank.co.jp ではない。このように、正規のドメイン名に似せたサブドメインを使って偽装する手口は古典的だが依然として使われている 3。 - 送信元アドレスの偽装
メールの「差出人(From)」に表示される名前やメールアドレスは、簡単に偽装可能である 8。そのため、差出人名が信頼できる組織のものであっても、それだけでメールを信用してはならない。より技術的な確認方法として、メールのヘッダ情報を表示し、送信元のIPアドレスなどを確認する方法もあるが、一般の利用者には難しい場合が多い 30。 - 「鍵マーク」の罠
前述の通り、ブラウザのアドレスバーに表示される鍵マーク(HTTPS接続)は、もはや安全の証明にはならない 8。このマークが意味するのは、ブラウザとウェブサイト間の通信が暗号化されているという事実だけであり、そのウェブサイトの運営者が本物であることや、サイトが悪意のないものであることを保証するものではない。詐欺サイトも暗号化通信を利用するのが一般的であるため、鍵マークの有無でサイトの真偽を判断することはできない。
【第5部】 もし、針にかかってしまったら:緊急対応と被害回復への道
どれだけ注意していても、一瞬の隙を突かれてフィッシング詐欺の被害に遭ってしまう可能性はゼロではない。万が一、偽サイトに情報を入力してしまった場合に備え、冷静かつ迅速に行動するための緊急対応計画を事前に理解しておくことが極めて重要である。
5.1. 直ちに行動せよ:被害を最小限に食い止める初動
被害に気づいた瞬間からの数時間が、被害の拡大を防ぐ上で決定的に重要となる。パニックにならず、以下の手順を順番に実行する。
- Step 1: 連絡(Contact)
クレジットカード番号や銀行口座の情報を入力してしまった場合、直ちにそのカード会社や金融機関に電話で連絡する。連絡先は、メールやSMSに記載されたものではなく、必ずカードの裏面や公式サイトに記載されている正規の番号を使用する 31。状況を説明し、カードや口座の利用停止を依頼する 17。 - Step 2: 変更(Change)
IDとパスワードを入力してしまった場合は、直ちにそのサービスの公式サイトにアクセスし、パスワードを変更する 20。もし、その盗まれたパスワードを他のサービスでも使い回している場合は、該当するすべてのサービスのパスワードも変更する必要がある 24。 - Step 3: 確認(Check)
カード会社や銀行に連絡した後も、自身のクレジットカードの利用明細や銀行口座の入出金履歴を注意深く確認する。身に覚えのない取引がないか、定期的にチェックすることが重要である 22。不正利用を早期に発見できれば、補償を受けられる可能性が高まる 24。
5.2. 誰に、何を、どう伝えるか:公式な相談・通報窓口
初動対応と並行して、適切な機関に被害を報告・相談することも重要である。これは自身の被害回復だけでなく、他の人々を同様の詐欺から守るための社会的な貢献にも繋がる。
- 警察
実際に金銭的な被害が発生した場合は、最寄りの警察署、または警察のサイバー犯罪相談窓口(全国共通の短縮ダイヤル「#9110」)に相談する 32。警察への被害届の提出は、後の捜査だけでなく、金融機関での補償手続きを円滑に進める上で重要な証拠となる場合がある 24。 - 消費生活センター
契約トラブルや詐欺被害に関する全般的なアドバイスが必要な場合は、消費者ホットライン「188」に電話する。専門の相談員が、今後の対応について助言を提供してくれる 17。 - フィッシング対策協議会
被害に遭った偽サイト(フィッシングサイト)のURLが分かっている場合は、フィッシング対策協議会に情報提供を行う。提供された情報は、サイトの閉鎖措置などに活用され、さらなる被害の拡大を防ぐのに役立つ 17。 - なりすまされた企業
詐欺メールで名前を使われた企業(銀行、ECサイトなど)の問い合わせ窓口にも、そのような詐欺があったことを報告することが望ましい。これにより、企業側が他の顧客に対して注意喚起を行うことができる。
被害に遭った際、多くの人はまず自身のパスワード変更や銀行への連絡といった個人的なダメージコントロールに集中する。それは当然の行動であるが、その一歩先、つまり警察やフィッシング対策協議会への「通報」という行動には、より大きな意味がある。
この通報という行為は、単なる被害報告ではない。それは、サイバー犯罪のエコシステムに対する反撃の狼煙である。フィッシングサイトを報告すれば、そのサイトは閉鎖され、次の被害者を出す前に対処できるかもしれない。警察に情報を提供すれば、犯罪者グループの特定や逮捕に繋がるデータとなる。企業に知らせれば、社会全体への警告が発せられる。
このように考えると、被害者はもはや単なる無力な標的ではない。その経験を社会に還元することで、デジタル社会全体の防衛力を高める「積極的な貢献者」へと変わることができる。個人の脆弱性が、社会全体の強さを生み出す瞬間である。被害後の報告は、個人の回復のためだけでなく、デジタル時代の市民的義務として捉えるべきなのである。
【結論】 デジタル社会を賢く生き抜くために
本レポートでは、2025年現在のフィッシング詐欺の最新手口、その背後にある心理的なメカニズム、そして個人が実践できる多層的な防御戦略と緊急時の対応策を詳述してきた。脅威はかつてないほど巧妙化し、私たちの日常生活のあらゆる側面に浸透している。
重要な防御策を要約すると、以下の3点に集約される。
- 意識の変革: 「リンクを信用せず、自ら確認する(Verify, Don’t Trust)」という行動原則を徹底する。これが最もシンプルかつ強力な防御策である。
- 技術的な必須設定: 多要素認証(MFA)の有効化は、もはや選択肢ではなく、デジタル社会を生きる上での義務と考えるべきである。パスワードの使い回しをやめ、ソフトウェアを常に最新に保つことも同様に重要である。
- 緊急時対応計画の理解: 万が一被害に遭った場合に、誰に連絡し、何を変更し、どこに報告すべきかを事前に知っておく。迅速な行動が被害を最小限に食い止める。
詐欺師たちの技術や手口は、今後も進化を続けるだろう。AIはより人間らしい文面を生成し、ディープフェイクはさらに見分けがつかなくなるかもしれない。したがって、私たちの防御もまた、一度きりの対策で終わらせるのではなく、継続的な学習と適応のプロセスでなければならない。
しかし、脅威の現実を前にして、無力感を覚える必要はない。本レポートで示したように、私たちには自らを守るための強力な知識とツールがある。詐欺師の手口を理解し、防御策を習得し、そして何よりも健全な懐疑心を持ち続けることで、私たちは自信と安全をもってデジタル世界を航海することができる。賢明で、警戒心を持ち、そして準備を怠らないデジタル市民であることが、この時代を生き抜くための鍵なのである。
【IT業向け資料】過去から現在へフィッシング詐欺との攻防の経緯
引用文献
- フィッシング詐欺とは?その手口や被害に遭わないための対策方法を解説! – りそな銀行, 8月 19, 2025にアクセス、 https://www.resonabank.co.jp/kojin/column/credit/column_0007.html
- フィッシングメールとは?詐欺の手口や対処法・防止策まで徹底解説 – NECフィールディング, 8月 19, 2025にアクセス、 https://www.fielding.co.jp/service/security/measures/column/column-11/
- 【NTT西日本】フィッシング詐欺とは?手口や事例、企業ができる対策を解説, 8月 19, 2025にアクセス、 https://business.ntt-west.co.jp/service/security/security_omakase/article/phishing.html
- フィッシング対策協議会 Council of Anti-Phishing Japan | 報告書類 …, 8月 19, 2025にアクセス、 https://www.antiphishing.jp/report/monthly/202505.html
- 月次報告書 | 2025/02 フィッシング報告状況 – フィッシング対策協議会, 8月 19, 2025にアクセス、 https://www.antiphishing.jp/report/monthly/202502.html
- フィッシングとは?| フィッシング攻撃の防止策 – Cloudflare, 8月 19, 2025にアクセス、 https://www.cloudflare.com/ja-jp/learning/access-management/phishing-attack/
- フィッシング詐欺とは?主な手口6つをわかりやすく解説 – wiz …, 8月 19, 2025にアクセス、 https://www.lanscope.jp/blogs/cyber_attack_pfs_blog/20230619_31578/
- 消費者の皆様へ | フィッシングとは – フィッシング対策協議会 Council of Anti-Phishing Japan, 8月 19, 2025にアクセス、 https://www.antiphishing.jp/consumer/abt_phishing.html
- 3分で読める |SMSが罠になる |進化するスミッシング詐欺の実態|中堅プロマネ・Wedge, 8月 19, 2025にアクセス、 https://note.com/itsecurityman/n/nf06c24d9ec9f
- 【2025年最新】フィッシング詐欺の事例8選!対策と被害に遭った時の対処法も解説, 8月 19, 2025にアクセス、 https://frauddetection.cacco.co.jp/media/knowhow/9473/
- 25年4月号 セキュリティコラム「多様化する『フィッシング』詐欺の手口」~メールだけではないさまざまなフィッシング詐欺について~ | JSSEC, 8月 19, 2025にアクセス、 https://www.jssec.org/column/20250428.html
- 『2025最新事例』実際に届いた迷惑・詐欺・攻撃メール【第2回】 – アクモス, 8月 19, 2025にアクセス、 https://cloud-srv.acmos.co.jp/blog/case2_2025
- 【2025年6月 マルウェアレポート】2025年に被害が増加している …, 8月 19, 2025にアクセス、 https://eset-info.canon-its.jp/malware_info/malware_topics/detail/malware2506.html
- 【2025年最新】フィッシング詐欺の最新事例 – サイバーセキュリティ総研, 8月 19, 2025にアクセス、 https://cybersecurity-info.com/column/31109/
- フィッシング詐欺の現状, 8月 19, 2025にアクセス、 https://www.mcpc-jp.org/pdf/security_seminars_20250212.pdf
- フィッシング詐欺、日本が世界最大の標的に!「自分は大丈夫」と思う前に読んでほしいセキュリティ対策, 8月 19, 2025にアクセス、 https://support.digion.com/blog/2025/07/anti-phishing-security-2025/
- 【2025年最新】個人が行うべきフィッシング詐欺対策5つ!被害が …, 8月 19, 2025にアクセス、 https://frauddetection.cacco.co.jp/media/knowhow/21039/
- 『2025最新事例』実際に届いた迷惑・詐欺・攻撃メール【第1回】 – アクモス, 8月 19, 2025にアクセス、 https://cloud-srv.acmos.co.jp/blog/case1_2025
- 警察庁を騙るフィッシングに注意 | トピックス | 脅威情報, 8月 19, 2025にアクセス、 https://www.jc3.or.jp/threats/topics/article-212.html
- フィッシング対策|警察庁Webサイト, 8月 19, 2025にアクセス、 https://www.npa.go.jp/bureau/cyber/countermeasures/phishing.html
- SMSやメールでのフィッシング詐欺に注意(国民生活センター) – 中央区, 8月 19, 2025にアクセス、 https://www.city.chuo.lg.jp/a0012/syohisikatsu/20240425.html
- 利用者向け フィッシング詐欺対策ガイドライン, 8月 19, 2025にアクセス、 https://www.antiphishing.jp/report/consumer_antiphishing_guideline_2025.pdf
- フィッシング対策ガイドライン2024の 概要と改定ポイント, 8月 19, 2025にアクセス、 https://www.nic.ad.jp/ja/materials/iw/2024/proceedings/c9/c9-kimura.pdf
- フィッシング詐欺にあったら?覚えておきたい対処法まとめ – LANSCOPE, 8月 19, 2025にアクセス、 https://www.lanscope.jp/blogs/cyber_attack_pfs_blog/20250526_27427/
- ちょっと待って!-SMSやメールでの“フィッシング詐欺”の相談が依然高水準!, 8月 19, 2025にアクセス、 https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20231108_2.html
- サポート詐欺対策|警察庁Webサイト, 8月 19, 2025にアクセス、 https://www.npa.go.jp/bureau/cyber/countermeasures/support-fraud.html
- フィッシング詐欺とは? | 国民のためのサイバーセキュリティサイト, 8月 19, 2025にアクセス、 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/cybersecurity/kokumin/basic/risk/04/
- 利用者向けフィッシング詐欺対策 ガイドライン, 8月 19, 2025にアクセス、 https://www.antiphishing.jp/report/consumer_antiphishing_guideline_2023.pdf
- フィッシングサイトの対策はどうする?被害例やとるべき対策を紹介 – NTTドコモビジネス, 8月 19, 2025にアクセス、 https://www.ntt.com/business/services/network/internet-connect/ocn-business/bocn/knowledge/archive_77.html
- フィッシング110番 – 警視庁ホームページ, 8月 19, 2025にアクセス、 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/cyber/security/cyber406.html
- フィッシング詐欺に遭った場合、また遭わないようにするためには、何をすればいいでしょうか?, 8月 19, 2025にアクセス、 https://www.cybersecurity.metro.tokyo.lg.jp/security/KnowLedge/580/index.html
- フィッシング詐欺被害とは?メールによる手口とその対策方法 – SAXA-DX Navi – サクサ, 8月 19, 2025にアクセス、 https://www.saxa.co.jp/saxa-dx_navi/trend/tr0049-security-u01-n003-n010.html
- ショッピングサイトで購入手続きをしたが、詐欺サイトのようだ – 愛知県警察, 8月 19, 2025にアクセス、 https://www.pref.aichi.jp/police/anzen/cyber/soudan/shoppingsite.html
- フィッシング詐欺に引っかかった場合に想定される被害とは?対処法についても解説, 8月 19, 2025にアクセス、 https://anshin-security.docomo.ne.jp/security_news/mail-sms/column022.html
- フィッシング詐欺被害に遭わないための注意事項 – 一般社団法人日本クレジット協会, 8月 19, 2025にアクセス、 https://www.j-credit.or.jp/customer/attention/attention_02.html
- SMSやメールでのフィッシング詐欺に注意(見守り情報) – 国民生活センター, 8月 19, 2025にアクセス、 https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen479.html

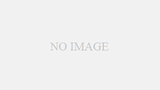
コメント