序論:革命から世界的パワーへ
1949年の中華人民共和国(PRC)建国以来、その歴史は、軍事力の抑制された行使を通じて3つの中核的目標を達成するための継続的な闘争として特徴づけられる。すなわち、国家権力と領土保全の確立、内外の脅威に対する中国共産党(CCP)の支配の確保、そして「中華民族の偉大なる復興」というビジョンを達成するための複雑な国際環境の航行である。本報告書の中心的なテーマは、中国の軍事力行使が圧倒的に政治的な性質を帯びており、限定的な軍事行動を用いて重大な戦略的・心理的効果を達成することを目的としてきたという点にある。多くの場合、戦闘そのものの結果よりも、それが伝える政治的メッセージや、それによって引き起こされる戦略的再編の方が重要であった。
本報告書は、主要な紛争を詳細なケーススタディとして扱いながら、時系列に沿って検証を進める。これらのケーススタディは、中国の軍事ドクトリンの進化と、世界的な安全保障アクターとしての台頭に関するテーマ別分析の基盤となる。報告書の構成は4つの主要部に分かれており、建国初期の紛争から現代における中国のグローバルな軍事的プレゼンスに至るまで、分析の論理的道筋を読者に示す。
まず、中国が関与した軍事紛争の全体像を概観するため、以下の年表を提供する。
表1:中華人民共和国が関与した主要軍事紛争の時系列概要(1949年~現在)
|
紛争名 |
期間 |
主要な敵対勢力 |
中国の役割 |
地理的範囲 |
結果 |
|
国共内戦 |
1945年–1949年 |
中華民国(国民党) |
直接戦闘員 |
中国大陸 |
共産党の勝利、PRC建国 1 |
|
チャムドの戦い |
1950年 |
チベット |
直接戦闘員 |
チベット |
勝利、PRCによるチベット併合 1 |
|
朝鮮戦争 |
1950年–1953年 |
韓国、米国、国連軍 |
同盟国(北朝鮮) |
朝鮮半島 |
停戦、現状維持(uti possidetis) 1 |
|
第一次台湾海峡危機 |
1954年–1955年 |
中華民国、米国 |
直接戦闘員 |
台湾海峡 |
停戦、戦前の状態(status quo ante bellum)に復帰 1 |
|
第二次台湾海峡危機 |
1958年 |
中華民国、米国 |
直接戦闘員 |
台湾海峡 |
停戦、PRCが砲撃を停止 1 |
|
中緬国境作戦 |
1960年–1961年 |
中華民国(ビルマ残留部隊) |
同盟国(ビルマ) |
ビルマ国境 |
勝利、国民党軍のビルマからの追放 1 |
|
中印国境紛争 |
1962年 |
インド |
直接戦闘員 |
中印国境 |
勝利、戦前の状態に復帰 1 |
|
ベトナム戦争 |
1965年–1969年 |
南ベトナム、米国、同盟国 |
同盟国(北ベトナム) |
インドシナ |
米軍の撤退、インドシナの共産化 1 |
|
ナトゥ・ラおよびチョ・ラでの衝突 |
1967年 |
インド |
直接戦闘員 |
中印国境 |
敗北、PRCが当該地域から撤退 1 |
|
中ソ国境紛争 |
1969年 |
ソビエト連邦 |
直接戦闘員 |
中ソ国境 |
敗北、戦前の状態に復帰 1 |
|
西沙諸島の戦い |
1974年 |
南ベトナム |
直接戦闘員 |
南シナ海 |
勝利、PRCが西沙諸島を支配 1 |
|
中越戦争 |
1979年 |
ベトナム |
直接戦闘員 |
中越国境 |
両国が勝利を主張、戦前の状態に復帰 1 |
|
中越国境紛争 |
1979年–1991年 |
ベトナム |
直接戦闘員 |
中越国境 |
停戦、関係正常化 1 |
|
第三次台湾海峡危機 |
1995年-1996年 |
中華民国、米国 |
軍事演習/威嚇 |
台湾海峡 |
停戦、PRCがミサイル発射を停止 1 |
第I部:建国初期の紛争と冷戦の新たな戦線
この部では、PRCの戦略的姿勢を決定づけ、CCPの国内支配を固め、その後の外交政策と軍事行動の永続的なパターンを確立した初期の紛争を分析する。
第1章:国家の確立(1949年~1950年代)
1.1 未完の内戦と領土の統合
1949年10月1日、毛沢東が天安門広場で中華人民共和国の建国を宣言したとき、戦争は終わっていなかった。中国共産党は大陸の支配権を確立したが、蔣介石率いる中華民国(ROC)政府は台湾に撤退し、内戦は「未完」のまま新たな段階に入った 1。この事実は、その後の数十年にわたるPRCの軍事戦略、特に台湾海峡における周期的な危機を理解する上での根源的な文脈となる。
国家の確立は、単に敵対勢力を打ち負かすことだけではなかった。それは、広大で多様な領土に対する実効支配を確立し、特に戦略的に脆弱な辺境地域を確保することを意味した。この文脈で、1950年のチベットへの軍事侵攻、すなわち「チャムドの戦い」が行われた 1。PRCはこれを「平和的解放」と位置づけたが、実際には軍事力を用いてチベットを併合するものであった。この行動は、単なる領土拡大ではなく、外国勢力(特にインドや西側諸国)の潜在的な影響力を排除し、中国の戦略的な西側面を確保するという、安全保障上の必須事項であった 1。この作戦は、国家安全保障に不可欠と見なされる辺境地域を統合するために軍事力を行使するという、PRCのその後の行動パターンの先駆けとなった。
1.2 朝鮮戦争(1950年~1953年):血と炎の中で国家を鍛える
建国からわずか1年後、PRCは朝鮮半島で世界最強の大国であるアメリカと直接対決するという、国家の存亡をかけた決断を下した。この介入は、PRCの歴史において最も重要かつ形成的な出来事の一つであり、その動機、遂行、そして結果は、その後の中国の戦略思想に深い痕跡を残した。
介入の決定
中国の参戦は、単一の要因ではなく、安全保障、イデオロギー、国内政治という3つの要素が複雑に絡み合った結果であった。
第一に、安全保障上の脅威が最も直接的な動機であった。国連軍、実質的には米軍が38度線を越えて北進し、中朝国境である鴨緑江に迫ったことで、北京の指導部は深刻な脅威を感じた 6。毛沢東は、米国が支援する統一朝鮮が国境に誕生することを、自国の産業中心地である満州への直接的な脅威であり、新生PRCの存立を危うくする「ドミノ」の第一歩と見なした 8。さらに、トルーマン大統領が台湾海峡に第7艦隊を派遣したことは、米国が中国の内戦に介入し、共産党政権に敵対する意図を持っているという北京の認識を確固たるものにした 9。
第二に、イデオロギー的連帯と国際的威信が重要な役割を果たした。PRCは、同じ共産主義国家である北朝鮮を支援し、「米帝の侵略に抵抗する」ことで、世界共産主義運動における指導的地位を確立しようとした 10。これは、ソ連の衛星国ではない、独立した革命大国としての地位を誇示する機会でもあった 8。
第三に、国内の権力基盤強化という目的があった。建国間もないPRCは、国民党の残党やその他の反体制派など、国内に多くの不安定要因を抱えていた。外部の脅威、特に米国との戦争は、国民のナショナリズムを喚起し、戦争で疲弊した国民を「抗米援朝(米国に抵抗し朝鮮を援助する)」のスローガンの下に結束させ、共産党の支配を盤石にするための強力な手段となった 8。
人民解放軍の戦績と戦術
中国は公式には正規軍ではなく、「中国人民志願軍」(CPV)の名の下に派兵した。これは、米国との全面戦争を避けるための政治的な建前であった。人民解放軍(PLA)は、朝鮮戦争で「人海戦術」として知られる戦術を用いたが、これは単に兵士を無謀に突撃させるものではなかった。むしろ、夜間の浸透、偽装、地形の利用を駆使して国連軍の陣地に密かに接近し、近距離で奇襲をかけることで、国連軍の圧倒的な火力(砲兵、航空支援)の優位性を無力化しようとする、より洗練された軽歩兵戦術であった 10。この戦術は、介入初期において劇的な成功を収め、国連軍を38度線以南へと押し戻した。しかし、国連軍が戦術に適応し、火力を効果的に用いるようになると、PLAは甚大な犠牲者を出すことになった。この戦争は、PLAが精神力と戦術だけでは技術的劣勢を克服できないという厳しい現実を突きつけられる経験となった 10。
人的・経済的コスト
朝鮮戦争の代償は計り知れなかった。中国側の死傷者数の正確な数字は不明だが、西側の推定では数十万人に上るとされている 15。特に、経験豊富な将校や下士官の損失は、その後の軍の再建に大きな影響を与えた 14。経済的にも、戦争は「深刻な負担」となり、軍事費は国家予算の大きな割合を占め、内戦からの復興に不可欠な希少資源を軍事に振り向けなければならなかった 12。これにより、PRCは軍事装備の供給をソ連に大きく依存することになり、その経済的従属を深める結果となった 14。
戦略的帰結
莫大な犠牲にもかかわらず、朝鮮戦争はPRCに多大な戦略的利益をもたらした。
- 国内的:戦争は毛沢東の指導力を絶対的なものとし、「米帝」への抵抗という共通の経験を通じて強力な国民的アイデンティティを形成した。
- 国際的:PRCは、世界最強の軍隊を相手に膠着状態に持ち込むことで、主要な軍事大国としての地位を確立し、その国際的威信を飛躍的に高めた。また、北朝鮮を戦略的な緩衝国家として確保することに成功した。しかし、その代償として、米国との敵対関係は決定的となり、数十年にわたる外交的孤立を招いた。
- 軍事的:この戦争は、PLAに近代戦に関する貴重な実戦経験をもたらした。しかし同時に、技術、兵站、兵科連合能力における深刻な弱点を露呈させた。この経験は、PLAが抱える技術的劣等感の根源となり、その後の数十年にわたる近代化努力の原動力となった。朝鮮戦争で学んだ教訓、特に米国の技術的優位性に対抗する必要性は、中国の軍事ドクトリンと装備開発の方向性を決定づける「 foundational trauma(根源的なトラウマ)」として、その後の歴史を通じて繰り返し参照されることになる。
1.3 台湾海峡危機(1954-55年、1958年):レッドラインの探求
朝鮮戦争の休戦後も、中国の内戦は台湾海峡でくすぶり続けた。1950年代に発生した二度の台湾海峡危機は、この未完の内戦の延長線上にあり、PRCが米国の防衛意志の限界を探り、台湾の事実上の独立を阻止するための軍事・政治的圧力であった 1。
1954年から55年にかけての第一次危機と、1958年の第二次危機において、PLAは台湾が支配する金門島と馬祖島に対して大規模な砲撃を行った 18。これらの島々は中国大陸の目と鼻の先にあり、PRCにとっては「解放」されるべき領土であり、ROCにとっては大陸反攻の象徴であった。PRCの目的は、これらの離島を占領すること自体よりも、米国とROCの間に結ばれた米華相互防衛条約の適用範囲を試すことにあった 18。
これらの危機において決定的な役割を果たしたのは、米国の介入であった。米国は第7艦隊を派遣してROCの補給線を護衛し、核兵器の使用を示唆することで、PRCのいかなる侵攻の試みも抑止した 18。これにより、PRCは台湾に関連するいかなる軍事行動においても、米国の介入を前提として計画を立てなければならないという厳しい教訓を学んだ。危機は最終的に停戦に至り、台湾海峡には緊張をはらみつつも安定した現状が確立された。
これらの初期の紛争を通じて、一つの明確なパターンが浮かび上がる。それは、軍事征服そのものよりも政治的目標の達成を優先するという中国の戦略文化である。チベット併合は領土保全という政治目標を達成するためであり、朝鮮戦争の介入は体制の安定と緩衝地帯の確保が目的であった。台湾海峡危機もまた、軍事力を用いて米国の意図を探り、政治的現状を変更させないための威嚇であった。これらの事例は、PRCが限定的な軍事力を、より大きな戦略的目標を達成するための「懲罰的」あるいは「強要的」な手段として用いる傾向があることを示している。このパターンは、その後の中国の軍事行動を理解する上で重要な鍵となる。
第II部:共産主義ブロックの分裂と辺境での戦争
中ソ同盟が崩壊するにつれて、中国は近隣諸国に「教訓を与え」、自国の戦略的地位を確保し、独立した地政学的道を歩むために軍事力を行使するようになった。この時期の紛争は、中国の軍事力が、もはやイデオロギー的連帯のためではなく、純粋な国益と勢力均衡の計算に基づいて行使されるようになったことを示している。
表2:中華人民共和国の主要戦争の比較分析
|
項目 |
朝鮮戦争 (1950-53) |
中印国境紛争 (1962) |
中ソ国境紛争 (1969) |
中越戦争 (1979) |
|
敵対勢力の相対的戦力 |
優越(米・国連軍) |
劣勢(インド軍) |
対等/優越(ソ連軍) |
劣勢(ベトナム民兵/国境警備隊) |
|
中国の公式な動機 |
「抗米援朝」 |
「自衛反撃」 |
「ソ連修正主義への反撃」 |
「自衛反撃」 |
|
根底にある戦略目標 |
体制の安定、緩衝地帯の確保、国際的威信の確立 7 |
領土問題の解決、インドの非同盟政策への打撃、アジアでの指導的地位の確立 20 |
イデオロギー的優位性の誇示、国内政治の引き締め、米ソ対立の利用 22 |
ベトナムのカンボジア侵攻への懲罰、ソ連の影響力抑制、鄧小平の権力掌握 23 |
|
PLAの主要戦術 |
夜間浸透、近接戦闘、人海戦術 10 |
奇襲、迅速な機動、二正面攻撃 21 |
待ち伏せ、限定的な武力衝突 22 |
大規模な正面攻撃、人海戦術 23 |
|
PLAの戦績評価 |
戦術的成功と甚大な損害。技術的劣勢が露呈。 |
圧倒的勝利。目標を効率的に達成。 |
戦術的膠着状態。政治的目標は達成。 |
戦術的苦戦。多大な損害を被り、戦略目標は未達。 |
|
推定される中国側死傷者 |
40万人以上(死者・負傷者) 14 |
1,400人~2,400人(死者・負傷者) 20 |
約70人~800人(死者) 22 |
26,000人~62,000人(死者・負傷者) 30 |
|
主要な戦略的帰結 |
米国との敵対関係の固定化、北朝鮮の存続、軍近代化の必要性の認識。 |
中印関係の長期的悪化、中国の国境支配の確立。 |
中ソ対立の決定的悪化、米中接近の契機となり、冷戦構造を三極化。 |
PLAの旧式化が露呈し、全面的な軍事改革の直接的な引き金となった。 |
第2章:中印国境紛争(1962年):ヒマラヤにおける「懲罰」戦争
2.1 紛争の根源
1962年の中印国境紛争は、単なる領土争いではなかった。それは、領土、主権、そしてアジアにおける指導的地位をめぐる、二つの新興大国間の複雑な対立の表出であった。
紛争の直接的な原因は、二つの主要な係争地をめぐる領有権問題であった。一つは西部のアクサイチン地方で、中国はチベットと新疆ウイグル自治区を結ぶ戦略的に重要な道路(G219国道)を建設していた 28。インドはこの地域を自国領カシミールの一部と主張していた。もう一つは東部のマクマホンラインで、これは1914年のシムラ会議でイギリス領インドとチベットの間で引かれた国境線であったが、中国政府はこれを一度も承認していなかった 21。
しかし、この領土問題を燃え上がらせたのはチベット問題であった。1959年にチベットで反乱が発生し、インドがダライ・ラマ14世に亡命を許可したことを、北京は中国の国内問題への重大な干渉であり、主権侵害であると見なした 20。これにより、国境問題は中国の核心的利益であるチベットの安定と不可分に結びついた。
さらに、この紛争にはアジアにおける地位をめぐる競争という側面があった。当時、インドのネルー首相は非同盟運動の指導者として国際的な名声を得ており、中国はこれをアジアにおける自国の影響力に対する挑戦と捉えていた 20。中国にとって、この戦争はインドの軍事力だけでなく、その外交政策と国際的地位に打撃を与えるためのものでもあった。
2.2 戦争の遂行と結果
インドが国境地帯に前進拠点を設置する「前進政策」を推し進めたことに対し、中国は1962年10月、周到に準備された二正面からの奇襲攻撃を開始した。PLAは、装備も準備も不十分なインド軍を圧倒し、短期間で係争地域を制圧した 21。
この戦争の最も特徴的な点は、中国が軍事目標を達成した後、11月21日に一方的な停戦を宣言し、占領地から撤退したことである 21。PLAは、実効支配線(Line of Actual Control, LAC)まで後退した。この行動は、中国の目的が領土の恒久的な征服ではなく、インドに決定的かつ屈辱的な敗北を与えることであったことを明確に示している。それは、軍事力を用いた暴力的なメッセージであり、インドの政策と認識を根本から覆すことを狙った「懲罰」戦争であった。死傷者の数も、PLAの準備の周到さとインド軍の不備を反映して、大きな差がついた 21。
2.3 長期的な影響
この戦争は、インドに深刻な衝撃を与えた。ネルー首相の非同盟政策と「ヒンディ・チニ・バイ・バイ(インドと中国は兄弟)」という理想は打ち砕かれ、インドは軍の近代化を余儀なくされ、外交的には西側諸国やソ連との関係を強化する方向へと舵を切った 25。この紛争は、今日まで続く中印間の根深い不信と戦略的ライバル関係を決定づけた。
地政学的には、中国はアクサイチンの支配を確固たるものにし、マクマホンラインの正当性を事実上無効化して、LACを既成事実としての国境とした 21。この未確定の国境線は、その後も両国間の緊張の火種であり続けている。この戦争は、中国が自国の核心的利益が脅かされたと判断した場合、たとえ国際的な非難を浴びようとも、断固たる軍事行動をとることを躊躇しないという明確なメッセージを世界に送った。
第3章:中ソ国境紛争(1969年):同志から戦闘員へ
3.1 大分裂
1960年代、かつては鉄の結束を誇った中ソ同盟は、イデオロギーと地政学的な対立により、取り返しのつかないほどに決裂した。この「大分裂」は、1969年のウスリー川での武力衝突で頂点に達した。
対立の根源は、1956年のフルシチョフによるスターリン批判に遡る。毛沢東はこれをマルクス・レーニン主義からの逸脱であり、修正主義への裏切りと見なした 34。さらに、ソ連が提唱した西側との「平和共存」路線は、毛沢東の世界革命論と真っ向から対立した。
イデオロギー論争は、やがて地政学的なライバル関係へと発展した。両国は世界共産主義運動の指導権をめぐって争い、また、帝政ロシア時代に結ばれた「不平等条約」に起因する長い国境線をめぐる緊張も高まっていた 22。ソ連が1968年にチェコスロバキアに侵攻し、「制限主権論」として知られるブレジネフ・ドクトリンを掲げたことは、中国に自国もソ連の「社会帝国主義」の標的になりかねないという強い警戒感を抱かせた 22。
3.2 珍宝島(ダマンスキー島)事件
1969年3月、ウスリー川の中州である珍宝島(ソ連側呼称:ダマンスキー島)で、中ソ両国の国境警備隊が衝突した。多くの分析は、最初の衝突が中国側によって周到に計画された待ち伏せ攻撃であったことを示唆している 22。
この軍事行動は、文化大革命の混乱の最中にあった毛沢東にとって、複数の戦略的意図を持っていた。第一に、ブレジネフ・ドクトリンに対抗し、ソ連の覇権主義に屈しないという断固たる姿勢を内外に示すこと。第二に、外部の脅威を煽ることで、文化大革命によって引き裂かれた国内の結束を図ること。そして第三に、ソ連の反応を試し、米ソ対立の力学を利用することであった 22。
衝突は数週間にわたって断続的に続き、両軍ともに重火器を使用し、双方に少なからぬ死傷者を出した 22。この事件により、二つの核保有国は全面戦争の瀬戸際に立たされた。
3.3 世界への影響:三極構造の世界へ
中ソ国境紛争は、軍事的には小規模な衝突であったが、その地政学的な影響は計り知れなかった。これは冷戦の構造を根本的に変える転換点となった。
この紛争は、共産主義ブロックがもはや一枚岩ではないことを世界に、とりわけ米国に明確に示した。リチャード・ニクソン米大統領はこの戦略的好機を逃さず、中国との関係改善に乗り出した。中ソの対立は、敵の敵は味方という地政学的な論理に基づき、1972年のニクソン訪中と米中和解への道を開いた 22。これにより、米ソの二極対立を基軸としていた冷戦は、米・ソ・中の三極構造へと変貌した。
この紛争は、中国の軍事力が単なる国境防衛の手段ではなく、大国の地政学的ゲームを動かすための洗練された外交ツールとしても機能しうることを示した。1962年のインドへの戦争が、地域のライバルに対する「懲罰」というコミュニケーションであったとすれば、1969年のソ連との衝突は、モスクワとワシントンの両方に対する、より複雑な戦略的メッセージであった。モスクワに対しては中国がソ連の覇権に屈しないという警告であり、ワシントンに対してはソ連に対抗するための潜在的な戦略的パートナーとなりうるというシグナルであった。これらの紛争に共通する根底には、領土、イデオロギー、国際的地位を含む「主権」に対する中国の極めて鋭敏な感覚がある。他国が中国の核心的な主権利益を侵害していると認識されたとき、紛争のリスクが最も高まるというこの歴史的パターンは、台湾や南シナ海をめぐる現代の緊張を理解する上で、依然として極めて重要である。
第III部:最後の戦争と近代化への道
この部では、中国が経験した最後の大規模な通常戦争に焦点を当てる。この戦争は、戦略的には多くの目標を達成できなかったものの、皮肉にも人民解放軍(PLA)を近代的な戦闘部隊へと変革させるための決定的な起爆剤となった。
第4章:中越戦争(1979年):中国に教訓を与えた戦争
4.1 動機の複雑な網
1979年2月、中国は突如としてベトナム北部に大規模な侵攻を開始した。かつて「唇と歯」のような関係と称された二つの共産主義国家間のこの戦争は、複数の動機が複雑に絡み合った結果であった。
第一に、公式な理由は**ベトナムへの「懲罰」**であった。1978年、ベトナムはカンボジアに侵攻し、中国が支援していたポル・ポトのクメール・ルージュ政権を打倒した 30。北京はこれを、自らの影響圏に対する許しがたい挑戦と見なした。
第二に、より大きな戦略的文脈として、ソ連への対抗があった。ベトナムは1978年にソ連と相互防衛条約を締結しており、中国はこれをソ連による自国への「包囲網」の一環と捉えていた 24。この戦争は、ベトナムを罰すると同時に、その背後にいるソ連を牽制し、ソ連の安全保障の約束がどこまで信頼できるかを試すという、代理戦争の側面を色濃く持っていた 38。
第三に、鄧小平の国内政治的思惑が決定的な役割を果たした。文化大革命の混乱を経て実権を掌握しつつあった鄧小平にとって、この戦争は複数の国内的目標を達成するための手段であった。第一に、毛沢東時代の古い考えに固執する軍の長老たちを抑え、自らの軍に対する支配権を確立すること 24。第二に、毛沢東の後継者であった華国鋒などの政敵を完全に失脚させること。そして第三に、侵攻の直前に訪問した米国に対し、中国がソ連に対抗する信頼できるパートナーであることを行動で示し、自らが推進する「改革開放」政策への西側からの支持と投資を取り付けることであった 23。
4.2 「高くついた勝利」:PLAの戦績と失敗
中国は数十万の兵力を国境に投入し、ベトナム北部の複数の省都を占領した 27。しかし、その進軍は困難を極めた。ベトナム軍の主力部隊はカンボジアにいたものの、国境地帯の民兵や地方部隊は、長年の対米戦争で培ったゲリラ戦の経験を活かし、侵攻軍に対して予想以上に激しい抵抗を行った 40。
約20年ぶりに大規模な実戦を経験したPLAは、深刻な問題を露呈した。
- 旧式化した戦術:朝鮮戦争時代のような人海戦術に依存し、多大な犠牲者を出した 23。
- 劣悪な兵站:山岳地帯での補給能力が著しく不足していた。
- 非効率な指揮統制:兵科間の連携が取れず、通信システムも旧式で、友軍相撃さえ発生した 24。
- 不十分な装備:兵士の装備はベトナム軍に劣る部分さえあった。
この戦争での死傷者数は双方ともに極めて多く、正確な数字は不明だが、数万人に上ると推定されている 27。中国は約1ヶ月後に「懲罰の目的は達成した」として一方的に勝利を宣言し、撤退した。しかし、主目的であったベトナム軍のカンボジアからの撤退を強いることはできず、ベトナムのカンボジア支配はその後10年間続いた 30。多くの分析家は、この戦争を中国の戦略的失敗、あるいはせいぜい「高くついた勝利」と見なしている 23。
4.3 全面的な改革への起爆剤
しかし、この戦術的・戦略的な失敗こそが、現代のPLAを誕生させる最大の要因となった。PLAの惨憺たる戦績は、中国の指導部に強烈な衝撃を与えた。「人民戦争」を戦うために作られた軍隊が、近代的な戦争には全く対応できないという事実を白日の下に晒したからである 24。
この「ウェイクアップコール」は、鄧小平が主導する抜本的な軍事改革の強力な追い風となった。鄧小平は、この失敗を口実に軍の長老たちを退け、自らの改革路線に沿った新しい世代の指導者を登用した。戦争後、PLAの改革は一気に加速し、その焦点は「革命化」から**「近代化、正規化」**へと劇的にシフトした。具体的には、兵員の削減と専門性の向上、時代遅れの装備の更新、そして何よりも、中国の周辺地域における限定的かつハイテクな紛争を遂行するための新しい軍事ドクトリンの開発へと向かった 42。したがって、1979年の中越戦争は、現代PLAの創設における最も重要な単一の出来事であったと言える。
この戦争は、鄧小平が軍事的な失敗をいかにして政治的な成功へと転換させたかを示す見事な事例でもある。PLAの劣悪なパフォーマンスは、彼が毛沢東時代の将軍たちを排除し、「四つの近代化」(軍事もその一つ)の緊急性を訴えるための正当化となった。同時に、この戦争は中国がソ連に対抗するために血を流す覚悟があることを西側に見せつけ、経済・技術協力のパートナーとしての魅力を高めた。このように、ベトナムでの軍事的失敗は、皮肉にも中国の経済的離陸を可能にする重要な触媒となったのである。さらに、この戦争は、同じ共産党が支配する国家間で行われた最後の大規模な戦争であり、一枚岩の共産主義ブロックという理念の完全な終焉を象徴していた。中国の動機は、イデオロギーではなく、国益、地政学、勢力均衡といった現実主義的な計算に完全に基づいていた。これは、中国が革命国家から現実主義的な大国へと移行する決定的な転換点であった。
第IV部:軍事戦略とグローバル・プレゼンスの新時代
この部では、歴史的な紛争からテーマ別の分析へと移行し、中国の軍隊がどのように変貌を遂げ、21世紀においてどのように力を投射しているかを探る。これは、伝統的な辺境での戦争という焦点からの脱却を意味する。
第5章:人民解放軍ドクトリンの進化:「人民戦争」から「情報化戦争」へ
1979年の中越戦争での苦い経験は、人民解放軍(PLA)のドクトリンに根本的な変革をもたらした。その後の数十年間、PLAは外部の軍事技術の進展、特に米国の戦争遂行能力に強い影響を受けながら、段階的にその戦略思想を進化させてきた。
5.1 「人民戦争」から「局地戦争」への転換
1985年以前の中国の軍事戦略の根幹は、毛沢東が編み出した**「人民戦争」**であった。これは、ソ連や米国による大規模な侵攻を想定し、広大な国土に「敵を深く誘い込み」、長期にわたる消耗戦で打ち負かすという、本質的に防勢的な戦略であった 44。
しかし、1985年、鄧小平が議長を務める中央軍事委員会は、PLAの戦略的焦点を、中国周辺における**「限定的な目標を持つ局地戦争」**(局部战争)へと転換させる歴史的な決定を下した 44。これは、1979年の戦争の教訓と、大規模な全面侵攻の脅威が低下したという新たな安全保障環境評価に基づいていた。この転換は、PLAが国土防衛だけでなく、国境の外で国益を守るための、より積極的で機動的な能力を必要とすることを意味した。
5.2 湾岸戦争の衝撃と「ハイテク条件下の局地戦争」
PLAのドクトリン進化における第二の転換点は、1991年の湾岸戦争であった。この戦争で米軍が示した圧倒的なハイテク兵器、精密誘導爆撃、情報ネットワーク中心の作戦能力は、中国の軍事指導者に再び深刻な衝撃を与えた 47。
この結果、PLAのドクトリンは**「現代ハイテク条件下の局地戦争」(高技术条件下的局部战争)に勝利することへと再定義された 44。これは、単に兵器を近代化するだけでなく、米国の技術的優位性に対抗するための非対称的な能力、いわゆる「殺手鐧(暗殺者のメイス)」の開発に重点を置くことを意味した。具体的には、弾道ミサイル・巡航ミサイル(後のPLAロケット軍が担当)、サイバー攻撃、宇宙兵器、そして米空母打撃群の接近を阻止するための接近阻止・領域拒否(A2/AD)**戦略の開発が加速された 46。
5.3 習近平の改革と「智能化戦争」
習近平が最高指導者となると、PLAの変革は最終段階に入った。2015年に開始された抜本的な軍事改革は、PLAの組織構造を根本から作り変えた。伝統的な陸軍中心の組織から、米軍に倣った統合軍である戦区を中心とする、真に統合作戦が可能な軍隊へと再編された 47。
現在のPLAのドクトリンは、「情報化戦争」(信息化战争)から、さらに進んだ**「智能化戦争」(智能化战争)へと進化している。これは、サイバー、宇宙、電磁スペクトラムといった領域における優位性を確保することが、物理的な領域での勝利の前提条件であるという考えに基づいている 46。人工知能(AI)やビッグデータ、無人システムを駆使して、敵の意思決定ループを破壊し、迅速に勝利を収めることが目標とされている。最終的なゴールは、21世紀半ばまでに米軍と肩を並べる「世界一流の軍隊」**を建設することである 49。この公式な軍事戦略の名称「積極防御」は、その戦略的曖昧さから注目に値する。歴史的には国土への侵攻を撃退するという防衛的な意味合いが強かったが、「前方防御」や「周辺での局地戦争」といった現代的な解釈は、作戦レベルではますます攻勢的になっている。これは、脅威が本土に到達する前に、国境から遠く離れた場所で先制的に無力化することも辞さないという思想の表れであり、「積極防御」という言葉は政治的な継続性のために維持されつつも、その作戦上の意味は「攻勢的防御」ドクトリンへと進化している。
第6章:グローバルな安全保障アクターとしての中国:青いヘルメットと遠洋海軍
21世紀に入り、中国の軍事力行使のあり方は、伝統的な国境紛争から大きく様変わりした。経済的なグローバル化に伴い、中国の国益は世界中に拡大し、それを保護するための新たな手段が必要となった。その結果、中国は国連平和維持活動(PKO)への積極的な参加と、遠洋での海軍力展開という、二つの新しい顔を持つようになった。
6.1 棄権から最大の貢献国へ:中国と国連PKO
かつて中国は、PKOを内政干渉の道具と見なし、安保理の関連決議では棄権を貫くことが多かった。しかし、1989年のナミビアでの活動への文民職員派遣を皮切りに、その姿勢は劇的に変化した 50。1992年のカンボジアPKOには、初めて部隊(工兵部隊)を派遣した 51。
今日、中国は国連安保理常任理事国(P5)の中で最大のPKO要員派遣国であり、PKO予算においても米国に次ぐ第2位の拠出国となっている 51。この変化の背景には、複数の動機がある。
- ソフトパワーと国際的イメージ:「責任ある大国」としてのイメージを国際社会に示し、その影響力を高める 53。
- 経済的利益の保護:特にアフリカなど、中国が巨額の投資を行っている紛争地域にPKO部隊を派遣することで、現地の安定を維持し、自国の経済的利益と在外中国人の安全を確保する 52。
- 作戦経験の獲得:PKOは、PLAが海外の多様な環境で兵站、指揮統制、現地住民との協力といった実戦的な経験を積むための、低リスクな訓練の場となっている 52。
表3:国連平和維持活動への中国の参加の拡大(1990年~現在)
|
年 |
派遣要員数(軍人/警察) |
主要なミッション |
財政的貢献(分担率) |
拠出国中での順位(財政) |
|
1990 |
5人(軍事監視員) |
UNTSO(中東) |
ごくわずか |
N/A |
|
1992 |
400人以上 |
UNTAC(カンボジア) |
0.79% |
15位 |
|
2000 |
約50人 |
UNTAET(東ティモール)等 |
0.995% |
13位 |
|
2003 |
800人以上 |
MONUC(コンゴ)、UNMIL(リベリア) |
1.54% |
9位 |
|
2013 |
1,500人以上 |
MINUSMA(マリ) |
5.15% |
6位 |
|
2015 |
3,000人以上 |
UNMISS(南スーダン) |
6.64% |
3位 |
|
2019 |
2,500人以上 |
UNMISS, UNIFIL, MONUSCO等 |
12.01% |
2位 |
|
2023 |
2,200人以上 |
UNMISS, UNIFIL, MINURSO等 |
15.21% |
2位 |
出典:50
6.2 アジアを越える戦力投射:ジブチ基地と海賊対策
PLA海軍(PLAN)にとって、2008年に開始されたソマリア沖アデン湾での海賊対策任務への参加は、本格的な「遠洋」展開の幕開けであった 57。この任務は、中国のシーレーン防衛の重要性を浮き彫りにし、持続的な海外プレゼンスの必要性と経験を提供した。
その論理的帰結が、2017年に開設されたアフリカの角に位置するジブチの海外基地である。公式には「後方支援施設」とされているが、その戦略的意義は多岐にわたる。海賊対策やPKO部隊への補給拠点であると同時に、紅海とアデン湾を結ぶバブ・エル・マンデブ海峡という世界の海上交通の要衝を扼し、エネルギー資源や貿易の安全を確保する役割を担う 59。また、中東やアフリカで有事が発生した際に、多数の在外中国人を避難させるための拠点(Non-combatant Evacuation Operations, NEO)としても機能する 58。この基地は、PLAがインド洋やアフリカへと戦力を投射するための恒久的な足がかりであり、中国の軍事的プレゼンスがもはやアジア地域に限定されないことを象徴している。
PKOへの参加やジブチ基地の設置は、単なる国際貢献活動ではない。これらは、中国の壮大な国家戦略と不可分に結びついている。PKO派遣は、中国の「一帯一路」構想と密接に関連する地域に集中しており、経済的利益を安全保障面から支える役割を果たしている。ジブチ基地は、中国の経済的生命線であるシーレーンを保護するためのものである。このように、中国は国連PKOや海賊対策といった国際的に正当性のある枠組みを利用して、自らのグローバルな野心を実現するためのハード・ソフト両面のインフラを構築している。これは、過去の懲罰戦争という鈍器のような手段から、銃火を交えることなく国益を確保し、PLAのグローバルな存在感を常態化させる、より洗練され、持続可能な権力投射への進化を示している。
結論:中国の軍事力行使におけるパターンと軌跡
本報告書は、1949年の中華人民共和国建国以来、同国が関与してきた戦争および軍事紛争を多角的に分析してきた。その歴史を通じて、中国の軍事力行使には一貫したパターンと明確な進化の軌跡が見られる。
主要なパターンの統合
分析を通じて、以下の4つの中核的な特徴が浮かび上がった。
- 政治目標の優位性:中国の軍事行動は、ほとんどの場合、純粋な軍事的勝利や領土征服を目的とするのではなく、特定の政治的目標を達成するための手段として用いられてきた。朝鮮戦争での体制安定、中印戦争での懲罰的メッセージ、中ソ国境紛争での地政学的シグナルなど、軍事力は常に国家の大戦略に従属する道具であった。
- 主権への鋭敏な感受性:紛争の最も強力な引き金は、領土、内政、イデオロギー的自立性を含む「主権」と「核心的利益」が侵害されたという認識であった。チベット問題が絡んだ中印戦争、台湾をめぐる危機、そして「不平等条約」に根差す中ソ間の緊張は、このパターンを明確に示している。
- 失敗からの学習:中国の軍事ドクトリンと組織の進化は、勝利の経験よりも、むしろ失敗や弱点が露呈した経験によって強力に推進されてきた。朝鮮戦争での甚大な犠牲は技術的劣等感を植え付け、中越戦争での惨憺たる戦績はPLAの全面的な近代化を不可避にした。これらの「トラウマ」こそが、変革の最大の触媒であった。
- 計算されたリスク:中国は、自国よりも強大な敵(朝鮮戦争での米国)に対しても、自国の存亡がかかっていると判断すれば、リスクを冒して介入することを厭わなかった。しかし、その行動は常に計算されており、全面戦争へのエスカレーションを避けるための限定的な目標設定(中印、中越戦争での一方的撤退)や政治的建前(「志願軍」)が用いられた。
発展の軌跡
中国の軍事的役割は、建国以来、劇的な変貌を遂げた。当初は、内戦を終結させ、国境を固めることに集中する大陸国家であった。その軍事力は、主に国内の安定と辺境地域の防衛に向けられていた。中ソ対立を経て、中国は自らを二つの超大国と対峙する独立した極と位置づけ、限定的ながらも国境を越えて力を投射する能力を示した。
改革開放以降、特に21世紀に入ってからは、経済的利益のグローバルな拡大に伴い、中国は海洋国家、そしてグローバル・パワーへと移行しつつある。その軍事力は、もはや国境防衛のためだけのものではない。PKO、海賊対策、海外基地の設置を通じて、遠方のシーレーンと海外権益を保護し、国際的な安全保障問題に関与する能力を構築している。この軌跡は、内向きで防衛的な姿勢から、外向きで積極的な権力投射への明確なシフトを示している。
将来への展望
本報告書で明らかになった歴史的パターンは、現在の地政学的緊張を理解する上で重要な示唆を与える。
- 台湾は、依然として「未完の内戦」の象徴であり、中国の主権に関する最も核心的な利益と見なされている。過去の台湾海峡危機は、中国が米国の介入を最大の変数と捉えつつも、台湾の独立に向けた動きを阻止するためには軍事的威嚇を躊躇しないことを示している。
- 南シナ海における中国の行動は、歴史的な主権の主張と、戦略的なシーレーン確保という現代的な要求が結びついたものである。
- 中印国境では、1962年以来の地位をめぐる競争と不信が根強く残っており、偶発的な衝突がより大きな紛争に発展するリスクをはらんでいる。
PLAが「世界一流の軍隊」になるという目標を達成しつつある現在、世界は新たな安全保障上の課題に直面している。より高い能力と自信を備えたPLAは、これまで以上に広範な選択肢を持つことになるだろう。今後の最大の問いは、中国が伝統的に示してきた、計算され抑制された限定的な軍事力行使というパターンを維持するのか、それとも、新たに手にした能力が、より大きなリスクを伴う行動へと指導部を誘うことになるのか、という点にある。その答えは、21世紀のアジア太平洋地域、ひいては世界の平和と安定を左右するであろう。
引用文献
- List of wars involving the People’s Republic of China – Wikipedia, 10月 15, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wars_involving_the_People%27s_Republic_of_China
- List of wars involving the People’s Republic of China, 10月 15, 2025にアクセス、 https://wikipedia.nucleos.com/viewer/wikipedia_en_all_maxi_2024-01/A/List_of_wars_involving_the_People’s_Republic_of_China
- List of wars involving the People’s Republic of China – Bharatpedia, 10月 15, 2025にアクセス、 https://en.bharatpedia.org/wiki/List_of_wars_involving_the_People%27s_Republic_of_China
- 国共内戦(第2次) – 世界史の窓, 10月 15, 2025にアクセス、 https://www.y-history.net/appendix/wh1601-083.html
- 国共内戦 – Wikipedia, 10月 15, 2025にアクセス、 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E5%85%B1%E5%86%85%E6%88%A6
- [現代中国経済] 1-3. 中華人民共和国の成立 – Konan-u, 10月 15, 2025にアクセス、 http://kccn.konan-u.ac.jp/keizai/china/01/03.html
- China’s Role in a Future Korean War > US Army War College – Publications > Display, 10月 15, 2025にアクセス、 https://publications.armywarcollege.edu/News/Display/Article/4217982/chinas-role-in-a-future-korean-war/
- Explaining China’s Intervention in the Korean War in 1950 – Inquiries Journal, 10月 15, 2025にアクセス、 http://www.inquiriesjournal.com/articles/1069/explaining-chinas-intervention-in-the-korean-war-in-1950
- View of The Psychology of the Korean War: The Role of Ideology and Perception in China’s Entry into the War | Journal of Conflict Studies, 10月 15, 2025にアクセス、 https://journals.lib.unb.ca/index.php/jcs/article/view/367/580
- Chinese intervention in the Korean War – LSU Scholarly Repository, 10月 15, 2025にアクセス、 https://repository.lsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2803&context=gradschool_theses
- China’s Decision to Enter the Korean War: History Revisted – Cambridge University Press, 10月 15, 2025にアクセス、 https://www.cambridge.org/core/journals/china-quarterly/article/chinas-decision-to-enter-the-korean-war-history-revisted/9C35CA60CCE3D8B9C619938281348DD9
- cia/osr /memo ef 75 1010 korean war costs uncl, 10月 15, 2025にアクセス、 https://www.cia.gov/readingroom/docs/CIA-RDP86T00608R000700100007-8.pdf
- Was the Chinese strategy in the Korean War actually “overwhelm with sheer numbers?”., 10月 15, 2025にアクセス、 https://www.reddit.com/r/WarCollege/comments/f8a1wh/was_the_chinese_strategy_in_the_korean_war/
- Foreign Relations of the United States, 1951, Korea and China, Volume VII, Part 2 – Historical Documents – Office of the Historian, 10月 15, 2025にアクセス、 https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1951v07p2/d135
- Korean War Memorial – FoundSF, 10月 15, 2025にアクセス、 https://www.foundsf.org/Korean_War_Memorial
- Korean War | National Army Museum, 10月 15, 2025にアクセス、 https://www.nam.ac.uk/explore/korean-war
- ECONOMIC EFFECTS OF THE KOREAN WAR IN CHINA – CIA, 10月 15, 2025にアクセス、 https://www.cia.gov/readingroom/docs/CIA-RDP79R01012A000800050048-5.pdf
- The 1958 Taiwan Straits Crisis: A Documented History – RAND, 10月 15, 2025にアクセス、 https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_memoranda/2006/RM4900.pdf
- The 1958 Taiwan Straits Crisis: A Documented History – RAND, 10月 15, 2025にアクセス、 https://www.rand.org/pubs/research_memoranda/RM4900.html
- Positional Issues and the 1962 Sino-Indian War (Chapter 4) – Cambridge University Press, 10月 15, 2025にアクセス、 https://www.cambridge.org/core/books/sinoindian-rivalry/positional-issues-and-the-1962-sinoindian-war/F9AC5C0FE6D647F21B93672027F3D233
- Causes of the 1962 Sino-Indian War: A Systems Level Approach – Digital Commons @ DU, 10月 15, 2025にアクセス、 https://digitalcommons.du.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=advancedintlstudies
- The 1969 Sino-Soviet Border Conflicts As A Key Turning Point Of The Cold War, 10月 15, 2025にアクセス、 https://www.hoover.org/research/1969-sino-soviet-border-conflicts-key-turning-point-cold-war
- Remembering and Forgetting the Last War: Discursive Memory of the Sino-Vietnamese War in China and Vietnam | TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia, 10月 15, 2025にアクセス、 https://www.cambridge.org/core/journals/trans-trans-regional-and-national-studies-of-southeast-asia/article/remembering-and-forgetting-the-last-war-discursive-memory-of-the-sinovietnamese-war-in-china-and-vietnam/3E1F02FD344EE290EBEFC97F4F3EEC7E
- The 1979 Sino-Vietnamese War and Its Consequences – Hoover Institution, 10月 15, 2025にアクセス、 https://www.hoover.org/research/1979-sino-vietnamese-war-and-its-consequences
- Foreign Relations of the United States, 1961–1963, Volume XIX, South Asia – Historical Documents – Office of the Historian, 10月 15, 2025にアクセス、 https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v19/d190
- The Sino-Soviet Border Dispute: Background, Development, and the March 1969 Clashes* | American Political Science Review, 10月 15, 2025にアクセス、 https://www.cambridge.org/core/journals/american-political-science-review/article/sinosoviet-border-dispute-background-development-and-the-march-1969-clashes/13085683914C871D92AF8DACDA3B6D1A
- A Costly Victory The Sino-Vietnamese War 1979 – British Modern Military History Society, 10月 15, 2025にアクセス、 https://bmmhs.org/a-costly-victory-the-sino-vietnamese-war-1979/
- Sino-Indian War – Wikipedia, 10月 15, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/Sino-Indian_War
- Sino-Soviet border conflict – Wikipedia, 10月 15, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/Sino-Soviet_border_conflict
- Sino-Vietnamese War – Wikipedia, 10月 15, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/Sino-Vietnamese_War
- China Invades Vietnam | Research Starters – EBSCO, 10月 15, 2025にアクセス、 https://www.ebsco.com/research-starters/history/china-invades-vietnam
- The China-India Relationship: Between Cooperation and Competition, 10月 15, 2025にアクセス、 https://www.cfr.org/backgrounder/china-india-relationship-between-cooperation-and-competition
- Sino-Indian Relations, 1954-1962, 10月 15, 2025にアクセス、 https://src-h.slav.hokudai.ac.jp/publictn/eurasia_border_review/Vol3SI/luthi.pdf
- The Sino-Soviet Split: A Domestic Ideology Analysis – BYU ScholarsArchive, 10月 15, 2025にアクセス、 https://scholarsarchive.byu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1328&context=sigma
- Sino-Soviet split – Wikipedia, 10月 15, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/Sino-Soviet_split
- World: VIOLENCE ON THE SINO-SOVIET BORDER – Time Magazine, 10月 15, 2025にアクセス、 https://time.com/archive/6633917/world-violence-on-the-sino-soviet-border/
- February 17, 1979: The Start of the Sino-Vietnamese Border War, 10月 15, 2025にアクセス、 https://www.thevietnamese.org/2022/02/february-17-1979-the-start-of-the-sino-vietnamese-border-war/
- Sino-Vietnamese border war in 1979 and post-war geopolitical adjustments of Vietnam – Le, 10月 15, 2025にアクセス、 https://vietnamjournal.ru/2618-9453/article/view/86978
- Deng’s War: Assessing the Success of the Sino-Vietnamese War – Inquiries Journal, 10月 15, 2025にアクセス、 http://www.inquiriesjournal.com/articles/1922/dengs-war-assessing-the-success-of-the-sino-vietnamese-war
- How many Chinese soldiers were killed in the 1979 Sino-Vietnamese War? – Quora, 10月 15, 2025にアクセス、 https://www.quora.com/How-many-Chinese-soldiers-were-killed-in-the-1979-Sino-Vietnamese-War
- During the Sino-Vietnamese War 1979, why did the Chinese forces suffer similar casualties to Vietnamese forces : r/AskHistory – Reddit, 10月 15, 2025にアクセス、 https://www.reddit.com/r/AskHistory/comments/1kt8osm/during_the_sinovietnamese_war_1979_why_did_the/
- Chinese Warfighting: The PLA Experience since 1949 (review) – ResearchGate, 10月 15, 2025にアクセス、 https://www.researchgate.net/publication/265902188_Chinese_Warfighting_The_PLA_Experience_since_1949_review
- Operational Art in the Sino-Vietnamese War – DTIC, 10月 15, 2025にアクセス、 https://apps.dtic.mil/sti/tr/pdf/ADA614152.pdf
- The Evolution of China’s Military Strategy – MIT, 10月 15, 2025にアクセス、 http://web.mit.edu/fravel/www/fravel.2005.evolution.china.military.strategy.pdf
- Patterns in China’s use of force : evidence from history and doctrinal writings | RAND, 10月 15, 2025にアクセス、 https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_reports/2007/MR1160.pdf
- China’s Active Defense Military Strategy – Marine Corps Association, 10月 15, 2025にアクセス、 https://www.mca-marines.org/wp-content/uploads/57-Chinas-Active-Defense-Military-Strategy.pdf
- Xi Jinping’s PLA Reforms and Redefining “Active Defense” – Army University Press, 10月 15, 2025にアクセス、 https://www.armyupress.army.mil/Journals/Military-Review/English-Edition-Archives/September-October-2023/Active-Defense/
- Modernization of the Chinese People’s Liberation Army and Its Impact on the Security of the Indo-Pacific Region Strategic Pape, 10月 15, 2025にアクセス、 https://www.dohainstitute.org/en/Lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/modernization-of-chinese-army-impact-on-security-of-the-indo-pacific-region.pdf
- SECTION 2: CHINA’S MILITARY REORGANIZATION AND MODERNIZATION: IMPLICATIONS FOR THE UNITED STATES, 10月 15, 2025にアクセス、 https://www.uscc.gov/sites/default/files/2019-09/Chapter%202%20Section%202-%20China%27s%20Military%20Reorganization%20and%20Modernization%2C%20Implications%20for%20the%20United%20States_0.pdf
- Peace, Development and Cooperation_Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, 10月 15, 2025にアクセス、 https://www.mfa.gov.cn/eng/wjb/zzjg_663340/gjs_665170/gjsxw_665172/202406/t20240606_11401067.html
- Timeline of China’s participation in UN peacekeeping missions – Chinadaily.com.cn, 10月 15, 2025にアクセス、 https://global.chinadaily.com.cn/a/202509/03/WS68b7805ea3108622abc9e874.html
- Is China Contributing to the United Nations’ Mission? – ChinaPower Project, 10月 15, 2025にアクセス、 https://chinapower.csis.org/china-un-mission/
- China’s Role in UN Peacekeeping – Institute for Security & Development Policy, 10月 15, 2025にアクセス、 https://www.isdp.eu/wp-content/uploads/2018/03/PRC-Peacekeeping-Backgrounder.pdf
- china’s expanding peacekeeping role: its significance and the policy implications – SIPRI, 10月 15, 2025にアクセス、 https://www.sipri.org/sites/default/files/files/misc/SIPRIPB0902.pdf
- MINURSO’S PEACEKEEPERS: NATIONAL DAY OF PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, 10月 15, 2025にアクセス、 https://peacekeeping.un.org/en/minursos-peacekeepers-national-day-of-peoples-republic-of-china-0
- Timeline of nation’s participation in UN peacekeeping missions, 10月 15, 2025にアクセス、 http://eng.mod.gov.cn/xb/News_213114/TopStories/16351281.html
- China’s Military Interventions: Patterns, Drivers, and Signposts | RAND, 10月 15, 2025にアクセス、 https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA444-4.html
- China’s Engagement in Djibouti | Congress.gov, 10月 15, 2025にアクセス、 https://www.congress.gov/crs-product/IF11304
- China’s Military Base in Djibouti – Begin-Sadat Center for Strategic Studies, 10月 15, 2025にアクセス、 https://besacenter.org/wp-content/uploads/2018/08/153-Chaziza-Chinas-Military-Base-in-Djibouti-web.pdf
- Is China Eyeing a Second Military Base in Africa? | United States Institute of Peace, 10月 15, 2025にアクセス、 https://www.usip.org/publications/2024/01/china-eyeing-second-military-base-africa
- Djibouti is the next arena for US-China competition in the Red Sea – Atlantic Council, 10月 15, 2025にアクセス、 https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/djibouti-is-the-next-arena-for-us-china-competition-in-the-red-sea/

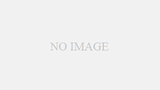
コメント