序論:継続性と変容 – 戦後ロシア軍事史の概観
本報告書の目的は、第二次世界大戦の終結(1945年)から現在に至るまで、ソビエト社会主義共和国連邦(以下、ソ連)およびその後継国家であるロシア連邦が関与した軍事紛争を、単なる回数の列挙に留まらず、その動機、形態、影響、そして国際的文脈の変化という多角的な視点から深く分析することにある。分析対象とする「ロシア」は、1991年まではソ連を指し、それ以降はロシア連邦を指す。この連続性は、地政学的な思考や戦略文化において、断絶よりも多くの継続性が認められるため、極めて重要である 1。
報告書全体を通じて、ロシアの軍事行動の根底には、①自国の安全保障を確保するための緩衝地帯(勢力圏)の維持・創設、②大国としての地位の国際的承認、③国内の政治的安定の確保、という三つの主要な動機が一貫して存在することを論証する。これらの動機は、時代の変遷とともにその正当化の論理(イデオロギー、対テロ、自国民保護など)を変えながらも、ロシアの対外行動を理解する上での不変の核として機能してきた。
本報告書の冒頭に、分析の全体像を把握するため、第二次世界大戦後にソ連・ロシアが関与した主要な軍事紛争をまとめた包括的な一覧表を提示する。この表は、各紛争を体系的に整理し、関与形態、公式な正当化事由、そして本報告書で分析する真の動機を対比させることで、多角的な分析を視覚的に補強するものである。
第二次世界大戦後のソ連・ロシアが関与した主要軍事紛争一覧
|
時代区分 |
紛争名 |
期間 |
関与形態 |
公式な正当化事由 |
分析される真の動機 |
結果と長期的影響 |
|
冷戦期 |
朝鮮戦争 |
1950–1953 |
代理戦争(兵器・顧問提供) |
国際主義的義務 |
共産主義圏の拡大、米国の封じ込め |
朝鮮半島の分断固定化 2 |
|
|
ハンガリー動乱 |
1956 |
直接軍事侵攻 |
「反革命」からの兄弟国救援 |
東欧衛星国の支配維持、ワルシャワ条約機構の結束強化 |
親ソ政権の樹立、制限主権論の確立 4 |
|
|
ベトナム戦争 |
1955–1975 |
代理戦争(兵器・顧問提供) |
民族解放運動支援 |
米国の影響力削ぎ、東南アジアでの勢力拡大 |
北ベトナムの勝利、ベトナムの共産化 3 |
|
|
チェコスロバキア侵攻 |
1968 |
直接軍事侵攻 |
「プラハの春」自由化の阻止 |
勢力圏の維持、ブレジネフ・ドクトリンの実践 |
改革派政権の打倒、「正常化」体制の確立 5 |
|
|
アフガニスタン侵攻 |
1979–1989 |
直接軍事侵攻 |
親ソ政権からの要請、善隣友好条約 |
イスラム原理主義の波及阻止、南側国境の安定化 |
ソ連軍の撤退、ソ連崩壊の一因、国際テロの温床化 5 |
|
ポスト冷戦移行期 |
トランスニストリア紛争 |
1992 |
内戦介入(平和維持名目) |
平和維持、ロシア系住民の保護 |
モルドバの西側への統合阻止、影響力維持 |
「凍結された紛争」の創出、ロシア軍の駐留継続 3 |
|
|
アブハジア・南オセチア紛争 |
1991–1993 |
内戦介入 |
平和維持、少数民族の保護 |
ジョージアの主権弱体化、影響力維持 |
「凍結された紛争」の創出 3 |
|
|
第一次チェチェン紛争 |
1994–1996 |
国内の分離主義鎮圧 |
領土一体性の維持、「違法武装集団」の掃討 |
資源(石油パイプライン)の確保、分離独立の波及阻止 |
事実上の敗北、チェチェンの事実上の独立状態 3 |
|
|
第二次チェチェン紛争 |
1999–2009 |
国内の分離主義鎮圧 |
対テロ作戦 |
領土一体性の回復、プーチン政権の権力基盤強化 |
ロシアの支配回復、強権的統治の確立 5 |
|
プーチン時代 |
ロシア・ジョージア戦争 |
2008 |
直接軍事侵攻 |
自国民(ロシア国籍者)保護、平和強制 |
NATO東方拡大への対抗、勢力圏の誇示 |
南オセチア・アブハジアの「独立」承認 5 |
|
|
シリア内戦介入 |
2015–現在 |
内戦介入(空爆主体) |
テロとの戦い、正統政府からの要請 |
アサド政権の維持、中東での影響力回復、国際的孤立からの脱却 |
アサド政権の延命、ロシアの中東におけるプレゼンス確立 3 |
|
|
ウクライナ戦争 |
|
|
|
|
|
|
|
– クリミア併合 |
2014 |
領土併合 |
住民の自決権の尊重、歴史的正義の回復 |
不凍港の確保、NATO拡大阻止、国内支持率向上 |
ロシアによるクリミア半島の併合、国際的制裁 14 |
|
|
– 全面侵攻 |
2022–現在 |
直接軍事侵攻 |
非ナチ化・非軍事化、ドンバス住民の保護 |
ウクライナのNATO加盟阻止、親露政権樹立、勢力圏の再確立 |
戦争の長期化、ロシアの国際的孤立と甚大な経済的損失 16 |
第1部:冷戦時代(1945年~1991年)- 勢力圏の維持とイデオロギーの戦い
第二次世界大戦後の世界は、米国を中心とする西側陣営とソ連を中心とする東側陣営による二極対立構造によって規定された。この時代におけるソ連の軍事行動は、ヤルタ体制下で獲得した東欧における衛星国の支配を維持し、第三世界で影響力を拡大するという二つの大きな目標に集約される。その行動は、イデオロギー闘争という大義名分を掲げつつも、その核心には常に地政学的な安全保障の確保という現実的な動機が存在した。
1.1 東欧衛星国の支配: 「制限主権論」の実践
第二次世界大戦の甚大な被害を経験したソ連にとって、西側からの潜在的な脅威に対する緩衝地帯の確保は、国家安全保障の至上命題であった 19。この目的のために、ソ連は東ヨーロッパ諸国に共産主義政権を樹立し、ワルシャワ条約機構という軍事同盟を通じて、自らの支配下に置いた。この「ソ連ブロック」内におけるいかなる自由化の動きやソ連からの離反の試みも、ソ連の安全保障に対する直接的な脅威と見なされ、武力による介入も辞さないという断固たる姿勢で臨んだ。
ケーススタディ:ハンガリー動乱(1956年)
1953年のスターリンの死後、ソ連国内で始まった「雪どけ」は東欧諸国にも波及した。ハンガリーでは、1956年にスターリン批判を契機として反ソ暴動が発生し、改革派のナジ・イムレが首相に就任した 20。ナジ政権が一党独裁の廃止やワルシャワ条約機構からの脱退を宣言するに至り、ソ連指導部はこの動きを社会主義体制そのものと自国の安全保障に対する許容しがたい「反革命」と断定した 4。
ソ連の動機は、単なるイデオロギーの純粋性を守るという観念的なものではなく、軍事同盟の環が一つでも崩れることへの地政学的な恐怖にあった 4。ソ連は戦車部隊を首都ブダペストに投入し、民衆の抵抗を容赦なく鎮圧 21。ナジ政権を打倒し、カーダール・ヤーノシュを首班とする親ソ政権を樹立した 4。この軍事介入は、ソ連が自らの勢力圏内にある衛星国の主権を、「社会主義共同体全体の利益」という名目の下に制限する権利を持つとする、後の「ブレジネフ・ドクトリン(制限主権論)」の事実上の先駆けとなった。
国際社会の反応は、ソ連の行動を計算に入れる上で重要な要素となった。国連はソ連軍の撤退を求める決議を採択したが 22、奇しくも同時期に発生したスエズ危機に西側諸国の関心が集中したこともあり、具体的な軍事的介入や実効的な制裁は行われなかった 23。この西側の事実上の黙認は、ソ連指導部にとって重要な学習経験となった。すなわち、自らの勢力圏内での「秩序維持」行動に対しては、西側は口頭での非難に留まり、本質的な介入はしてこないという計算が成り立つ可能性が示唆されたのである。
ケーススタディ:プラハの春とチェコスロバキア侵攻(1968年)
ハンガリー動乱から12年後、チェコスロバキアでドゥプチェク第一書記の指導の下、「人間の顔をした社会主義」をスローガンとする自由化改革、いわゆる「プラハの春」が始まった。言論・報道の自由化や経済改革が進む中、ソ連のブレジネフ政権はこれを社会主義体制の根幹を揺るがし、ひいてはソ連ブロック全体の結束を弱める危険な動きと見なした 24。
1968年8月、ソ連はポーランド、東ドイツ、ハンガリー、ブルガリアからなるワルシャワ条約機構軍を率いてチェコスロバキアに侵攻し、改革運動を武力で圧殺した 3。この行動は、ハンガリー動乱に対する西側の反応が限定的であったという過去の経験に後押しされた側面がある。ソ連は、再び自らの勢力圏内での問題解決において、武力行使という選択肢を躊躇なく採用した。
注目すべきは、その正当化の論理である。ソ連は公式には、この侵攻を「西側帝国主義の陰謀からチェコスロバキアの兄弟人民を救出するための国際主義的援助」であると位置づけた 25。このプロパガンダは、ソ連国内だけでなく、侵攻に参加したハンガリーなどの他の東欧諸国においても、教育を通じて徹底的に浸透させられた 26。その結果、侵攻された側の国民と、侵攻に加担させられた側の国民とで、同じ歴史的事件に対する認識が全く異なるという状況が生まれた。これは、軍事行動が単に物理的な支配を確立するだけでなく、情報統制とプロパガンダを通じて歴史認識や価値観そのものを書き換え、支配を内面から正当化しようとする、より深いレベルでの影響を及ぼすことを示している。武力行使と情報操作を組み合わせるこの手法は、現代の「ハイブリッド戦争」の原型とも言えるものであった。
1.2 グローバルな代理戦争
ソ連の軍事活動は東欧に限定されなかった。米国との世界的な覇権をめぐる冷戦の文脈の中で、ソ連はアジア、アフリカ、ラテンアメリカにおける民族解放運動や親ソ・共産主義勢力を積極的に支援した。これは、核戦争のリスクを伴う米ソ間の直接的な軍事衝突を避けつつ、イデオロギーと地政学的な覇権を争う「代理戦争」という形態をとった 27。
その関与は広範にわたる。
- 朝鮮戦争 (1950-1953): ソ連は、金日成政権下の北朝鮮に対し、軍事顧問団の派遣や最新鋭の戦闘機を含む兵器供与を行い、中国人民義勇軍と共に間接的に戦争を支援した 2。
- ベトナム戦争 (1955-1975): 北ベトナムに対し、地対空ミサイルや戦車などの高度な兵器、軍事専門家、そして莫大な経済援助を提供し、米国の軍事介入に対抗する上で決定的な役割を果たした 3。
- 中東: イスラエルとアラブ諸国との対立において、ソ連は一貫してアラブ側を支援した。特に1967年の第三次中東戦争後の「消耗戦争」(1967-1970)では、エジプトに軍事顧問やパイロットを派遣し、イスラエルと対峙した 3。
- アフリカ: ポルトガルの植民地支配からの独立後、アンゴラで内戦 (1975-2002) が勃発すると、ソ連はキューバ軍と連携してMPLA(アンゴラ解放人民運動)を支援した。また、エチオピアとソマリアが領土を争ったオガデン戦争 (1977-1978) では、エチオピアの社会主義政権を支援した 3。
これらの代理戦争への関与は、ソ連がグローバルな超大国としての地位を維持し、世界中にその影響力を投射するための重要な手段であった。
1.3 アフガニスタン侵攻(1979-1989)という泥沼
1979年12月のソ連によるアフガニスタンへの軍事侵攻は、冷戦後期の国際情勢を大きく揺るがし、最終的にはソ連自身の運命にも深刻な影響を与えた。公式には、1978年に締結された善隣友好協力条約に基づき、国内の反乱に苦しむアフガニスタンの親ソ共産党政権からの「要請」に応じたものとされた 8。しかし、その背後にはより複雑で切迫した動機が存在した。
第一に、隣国イランで同年発生したイスラム革命への強い警戒感があった。ソ連指導部は、イスラム原理主義の波が国境を越え、イスラム教徒を多く抱えるソ連南部の中央アジア諸共和国に波及し、分離独立運動を誘発することを極度に恐れた 8。第二に、アフガニスタンのアミン政権がソ連のコントロールを離れ、米国に接近する可能性への不信感があった。ソ連は、より従順なカルマル政権を樹立することで、アフガニスタンを確実に自らの勢力圏内に留め置こうとした 8。
しかし、ソ連の介入は泥沼のゲリラ戦争へと発展した。米国、パキスタン、サウジアラビアなどが「ジハード(聖戦)」を掲げるイスラム武装勢力「ムジャヒディン」に最新の兵器を含む大規模な支援を行った 9。ソ連軍は近代的な兵器で優位に立っていたものの、山岳地帯でのゲリラ戦に苦しみ、戦争は10年近くに及んだ。この長期化した戦争は「ソ連のベトナム戦争」と化し、1万5000人以上のソ連兵が死亡、5万人以上が負傷するという甚大な人的損失をもたらした 30。
経済的な影響も壊滅的であった。既に構造的な停滞に陥っていたソ連経済にとって、莫大な戦費は大きな負担となり、国家財政を圧迫した 8。この経済的疲弊は、ペレストロイカの失敗と相まって、最終的にソ連崩壊の重要な一因となったと広く認識されている 7。
さらに、この紛争は意図せざる長期的な帰結をもたらした。ソ連との戦いのために世界中から集まったアラブ人義勇兵たちは、アフガニスタンを拠点にネットワークを構築し、戦闘経験を積んだ。その中には、後に国際テロ組織「アルカイダ」を創設するオサマ・ビン・ラディンも含まれていた 9。ソ連が自国の南側国境の安定化という地域的な地政学的目的で開始した軍事行動が、結果として21世紀の国際社会を脅かすグローバルなテロリズムの温床を創り出すという、極めて皮肉な結末を迎えたのである。これは、一国の地政学的行動が、予測不可能な第三次的なグローバルな脅威を生み出す危険性を示す典型例として、歴史的な教訓となっている。
第2部:ポスト冷戦の混乱期(1991年~1999年)- 「近隣諸国」の確保と国内の分離主義
1991年のソ連崩壊は、ロシアにとって地政学的な大惨事であった。かつて広大な影響力を誇った超大国は、深刻な経済危機と政治的混乱に見舞われ、国際舞台での地位は著しく低下した。この時代、ロシアの軍事行動の焦点は、かつてのグローバルなイデオロギー闘争から、旧ソ連空間(ロシアが「近隣諸国」と呼ぶ地域)における影響力の維持と、ロシア連邦自体の領土一体性を脅かす国内の分離主義運動の鎮圧へと劇的にシフトした。
2.1 旧ソ連空間における紛争介入: 「凍結された紛争」の創出
ソ連の解体により、ロシアは長年にわたって築き上げてきた西側の緩衝地帯を一夜にして失った。新たに独立した旧ソ連構成共和国では、ソ連時代に抑圧されていた民族間の対立が噴出し、各地で武力紛争が発生した。これらの紛争に対し、ロシアは「平和維持」や「ロシア系住民の保護」を名目に介入した 32。しかしその真の目的は、これらの新興独立国家が完全にロシアの影響下から離脱し、西側陣営に接近するのを防ぐことにあった。
- トランスニストリア紛争 (1992): モルドバ東部のロシア系住民が多数を占めるトランスニストリア地域が分離独立を宣言すると、ロシアは現地に駐留していた旧ソ連軍(第14軍)を通じて分離主義勢力を公然と支援し、モルドバ政府軍の鎮圧を阻止した。結果として停戦が成立したが、トランスニストリアは事実上の独立状態となり、現在に至るまでロシア軍が「平和維持軍」として駐留を続けている 3。
- アブハジア紛争 (1992-1993) と南オセチア紛争 (1991-1992): ジョージア国内の自治州であったアブハジアと南オセチアが分離独立を求めてジョージア政府と武力衝突を起こすと、ロシアはこれらの分離主義勢力を支援した 10。これにより、ジョージアは自国領土の一部に対する実効支配を失った 3。
- タジキスタン内戦 (1992-1997): 中央アジアのタジキスタンで政府軍とイスラム勢力などが衝突する内戦が始まると、ロシアは政府軍を支援するために軍事介入し、内戦終結後も軍事基地を維持し続けた 3。
これらの介入に共通する戦略は、紛争を完全には解決させないことであった。ロシアは、どちらかの側が決定的な勝利を収めることを防ぎ、停戦状態に持ち込むことで、未解決の領土問題を意図的に作り出した。この「凍結された紛争」の存在は、対象国(モルドバ、ジョージアなど)にとって永続的な不安定要因となり、国家主権を不完全なものにする。主権が不完全な国家は、NATO(北大西洋条約機構)やEU(欧州連合)のような西側の組織への加盟が事実上不可能となる。このようにしてロシアは、全面的な占領という高いコストを払うことなく、これらの国々に対する恒久的な影響力(レバレッジ)を確保し、その外交政策を効果的に拘束する、極めて巧妙な地政学的戦略を確立したのである。
2.2 チェチェン紛争: 領土一体性をめぐる戦い
「近隣諸国」への介入と並行して、新生ロシアは自らの国内で深刻な分離主義の脅威に直面した。その最も血なまぐさい現れが、北カフカスに位置するチェチェン共和国との二度にわたる紛争であった。
ソ連崩壊の過程で、チェチェンは1991年に一方的に独立を宣言した。エリツィン政権下のロシアは、これを断固として認めなかった。その動機は複合的であった。第一に、一つの共和国の独立を認めれば、多民族国家であるロシア連邦の他の地域にも分離独立の動きがドミノ倒し的に波及し、国家の崩壊につながりかねないという、領土一体性の維持に対する強い懸念があった 11。第二に、チェチェンはカスピ海の石油を黒海へ輸送するための重要なパイプラインが通過する戦略的要衝であり、その利権確保という経済的な動機も存在した 33。
第一次チェチェン紛争 (1994-1996)
ロシア軍はチェチェンの独立を武力で阻止するために侵攻を開始した。しかし、アフガニスタンでの教訓を生かせず、準備不足と士気の低いロシア軍は、地の利を生かしたチェチェン武装勢力のゲリラ戦に苦戦し、多大な犠牲者を出した。首都グロズヌイは破壊し尽くされたものの、最終的にロシアは停戦協定に合意せざるを得ず、事実上の敗北を喫した。チェチェンはロシアからの独立こそ国際的に承認されなかったものの、事実上の独立状態を維持した 3。
第二次チェチェン紛争 (1999-2009)
1999年、ロシア国内のモスクワなどで発生した連続アパート爆破事件を契機に、状況は一変する。ロシア政府はこれをチェチェン独立派武装勢力のテロ行為と断定(真相には諸説ある)。当時、エリツィン大統領によって首相に抜擢されたばかりのウラジーミル・プーチンは、「テロとの戦い」を掲げ、チェチェンへの大規模な軍事作戦の開始を宣言した 11。
第一次紛争の失敗を教訓に、ロシア軍は今回は圧倒的な火力を用いてグロズヌイを包囲・制圧し、チェチェン全土を支配下に置いた。そして、親ロシア派のカディロフ一族をトップとする強権的な政権を樹立した 3。国際社会は、特に紛争初期におけるロシア軍の無差別爆撃などによる人権侵害に懸念を表明したものの 35、9.11同時多発テロ以降の「テロとの戦い」という世界的な風潮の中で、ロシアの行動を国内問題として事実上黙認する傾向が強かった。
この第二次チェチェン紛争は、単にロシアの領土一体性を回復しただけでなく、ロシアの国内政治に決定的な影響を与えた。1999年当時、プーチンはまだ国民にほとんど知られていない存在であった。しかし、彼はこの戦争において「テロリストは便所に追い詰めてでも息の根を止める」といった強硬な姿勢を鮮明に打ち出し、ポスト冷戦期の混乱と屈辱に疲弊していたロシア国民のナショナリズムを刺激し、絶大な支持を獲得した。この戦争は、彼を「秩序を回復できる強い指導者」として国民に印象付け、大統領への道を確実なものにしたのである。これは、対外・国内を問わず、紛争が「旗の下への結集」効果を生み出し、指導者の権力基盤を盤石にするという現象の典型例であり、後のプーチン政権の行動様式を理解する上で極めて重要な前例となった。
第3部:プーチン時代のロシア(2000年~現在)- 大国としての再興と挑戦
2000年に大統領に就任したウラジーミル・プーチン統治下のロシアは、2000年代のエネルギー価格の高騰を追い風に経済力を回復させ、ポスト冷戦期の混乱を乗り越えて「強いロシア」の復活を国家目標として掲げた。国内では権力の垂直統合を進め、対外的には失われた大国としての地位を取り戻すべく、より積極的かつ挑戦的な軍事・外交政策を展開する。この時代の軍事行動は、NATOの東方拡大への対抗、グローバルな影響力の再確立、そして「ロシア世界(ルースキー・ミール)」という独自の文明圏の防衛という、より野心的な目標によって特徴づけられる。
3.1 「強いロシア」の誇示: NATO東方拡大への対抗
プーチン政権にとって、冷戦終結後にワルシャワ条約機構の旧加盟国やバルト三国までもがNATOに加盟したことは、ロシアの安全保障に対する裏切りであり、容認しがたい脅威と映った。特に、ウクライナやジョージアといった旧ソ連の中核的な共和国がNATO加盟を目指す動きは、越えてはならない一線(レッドライン)と見なされた。
ケーススタディ:ロシア・ジョージア戦争(2008年)
2003年の「バラ革命」以降、親西側路線を鮮明にしたジョージアのサーカシヴィリ政権がNATO加盟への動きを加速させると、ロシアの警戒感は頂点に達した 36。ロシアはこれに対抗するため、周到な準備を進めた。1990年代から「凍結」されていたジョージア国内の分離独立地域、南オセチアとアブハジアの住民に対し、ロシア国籍のパスポートを大量に発給する「パスポート化」政策を推進した。
2008年8月、北京オリンピックの開会と時を同じくして、ジョージア軍が南オセチアの支配を回復するために軍事行動を開始すると、ロシアはこれを待っていたかのように大規模な軍事介入を開始した。その正当化事由として掲げられたのが、「ロシア国民の保護」であった 12。ロシアは、事前に自国民として登録した住民を守るという名目で、主権国家であるジョージアの領土に侵攻したのである。ロシア軍は短期間でジョージア軍を圧倒し、首都トビリシ近郊まで進軍。停戦後、ロシアは一方的に南オセチアとアブハジアの「独立」を承認し、軍事基地を建設した。これは、ソ連崩壊後の国境線を武力によって変更するという明確な意思表示であり、旧ソ連空間における現状変更を力で行うことを辞さないというロシアの新たな姿勢を国際社会に見せつけるものであった。
この戦争は、後のより大規模な紛争の重要な前段階と見なすことができる。西側諸国はロシアの行動を強く非難したものの、具体的な軍事的対応はなく、経済制裁も限定的であった 37。この国際社会の「ソフト」な反応は、プーチン政権にとって、西側は旧ソ連圏の問題に対しては本気で軍事的に介入する意思も能力もないという確信を深めさせる結果となった 10。この経験は、ロシアがより大胆な行動へと踏み出す際の心理的ハードルを著しく下げた。その意味で、2008年のジョージア戦争は、6年後の2014年のクリミア併合、そして2022年のウクライナ全面侵攻へと続くエスカレーション・ラダー(段階的拡大)の重要な一歩であり、西側の決意を試す「テストケース」であったと言える。
3.2 中東への回帰: グローバル・プレーヤーとしての地位確立
2010年代に入り、ロシアは旧ソ連圏を越えて、再びグローバルな舞台での影響力を行使し始める。その象徴的な出来事が、シリア内戦への軍事介入であった。
ケーススタディ:シリア内戦への介入(2015年~)
2011年に始まった「アラブの春」がシリアに波及し、アサド政権に対する反政府運動が内戦へと発展すると、政権は崩壊の危機に瀕した。この状況に対し、ロシアは2015年9月に空爆を中心とする本格的な軍事介入を開始した。その動機は多層的であった。
第一に、地中海に海軍基地を持つシリアは、中東におけるロシアの最後の同盟国であり、アサド政権の崩壊はロシアにとって大きな戦略的損失を意味した 38。
第二に、2014年のクリミア併合によって国際的に孤立していたロシアにとって、シリア問題に深く関与することは、米国と対等な立場で交渉するテーブルに着き、グローバル・プレーヤーとしての地位を回復する絶好の機会であった 13。
第三に、ISIL(イスラム国)などの過激派組織がシリアで勢力を拡大する中、ロシアはこれを「対テロ作戦」と位置づけ、チェチェンや中央アジア出身の戦闘員がロシア国内に脅威をもたらす前に、シリアでこれを叩くという安全保障上の目的も持っていた 13。
ロシアの軍事介入は、戦況を決定的に変えた。ロシア空軍の支援を受けたアサド政権軍は息を吹き返し、反体制派が支配していた多くの地域を奪還した。外交面でも、ロシアは国連安全保障理事会で拒否権を繰り返し行使してアサド政権を擁護し 13、独自の和平交渉の枠組み(アスタナ・プロセス)を主導するなど、中東における外交の主導権を握った。この介入の成功により、ロシアは比較的少ないコストで中東における影響力を劇的に回復させ、大国としての地位を国際社会に改めて印象づけた。
3.3 ウクライナ戦争:集大成としての全面紛争
ウクライナに対するロシアの行動は、プーチン時代の地政学的野心の集大成であり、第二次世界大戦後のヨーロッパの安全保障秩序を根底から揺るがすものであった。
クリミア併合 (2014年)
2014年2月、ウクライナの首都キーウで親ロシア派のヤヌコーヴィチ大統領が民衆の抗議運動(ユーロマイダン革命)によって追放され、親西側政権が樹立されると、ロシアはウクライナが完全に西側陣営に移行することへの強い危機感を抱いた 15。これに対し、プーチン大統領はクリミア半島の併合という電撃的な行動を決断した。
ロシアは「緑の小人」と呼ばれる所属不明の武装部隊(実際にはロシア軍特殊部隊)をクリミアに展開して主要施設を占拠。その後、ロシアの完全な管理下で「住民投票」を実施し、圧倒的多数がロシアへの編入を支持したとして、併合を正当化した。その動機は、ジョージア戦争やシリア介入以上に複合的であった。
- 軍事戦略的動機: クリミア半島のセヴァストポリは、ロシア黒海艦隊の唯一の不凍港であり、地中海へのアクセスを確保する上で死活的に重要な軍事拠点であった 40。ウクライナの親西側化により、この基地を失うリスクをロシアは許容できなかった 14。
- 歴史的・民族的動機: ロシア国民の多くは、クリミアが歴史的にロシア領土であり、1954年にフルシチョフの決定でウクライナに移管されたのは不当であるという感情を共有していた 15。プーチンはこのナショナリズムに訴えかけることで、国内の圧倒的な支持を得た。
- 国内政治的動機: クリミア併合はプーチンの支持率を急上昇させ、「クリミア・コンセンサス」と呼ばれる熱狂的な愛国ムードを醸成し、政権基盤を一層強固なものにした 43。
全面侵攻 (2022年~)
クリミア併合後、ウクライナ東部のドンバス地方でウクライナ政府軍とロシアが支援する分離主義武装勢力との紛争が8年間続いた。そして2022年2月24日、ロシアはウクライナ全土への大規模な軍事侵攻を開始した。
ロシア側が公式に掲げた侵攻の動機は、①ウクライナの「非ナチ化」と「非軍事化」、②ドンバス地方のロシア系住民をウクライナ政府による「ジェノサイド」から保護すること、であった 18。しかし、その背後には、これまでのロシアの行動の延長線上にある、より根本的な戦略目標が存在する。
- NATO拡大の阻止: ロシアは、ウクライナのNATO加盟を自国の安全保障に対する直接的な脅威と見なし、これを武力で阻止することを最終目的とした 17。
- 勢力圏の再確立: 侵攻の目的は、ウクライナに親ロシア政権を樹立し、同国をロシアの恒久的な勢力圏に引き戻すことにあった 44。
- 歴史認識と「ロシア世界」: プーチン大統領は、ロシア人とウクライナ人は「一つの民族」であるという独自の歴史観を繰り返し表明しており 17、ウクライナという国家の主権そのものを否定する考えが根底にある。これは、言語・文化・宗教を共有する「ロシア世界(ルースキー・ミール)」という文明圏を防衛・拡大するという、帝国主義的な思想の現れである。
国際社会の反応は、2008年のジョージアや2014年のクリミアの時とは比較にならないほど迅速かつ強力であった。米国、EU、日本などはロシアに対して史上最大規模の経済制裁を科し 45、国連総会ではロシアの侵略を非難し、即時撤退を求める決議が圧倒的多数で繰り返し採択された 47。この戦争は、戦後ロシア軍事史の集大成であると同時に、ロシアと西側との関係を決定的に破綻させ、世界の地政学的構造を大きく変容させる歴史的な転換点となった。
第4部:通時的テーマ分析
第二次世界大戦後から現在に至るまでのソ連・ロシアの軍事紛争への関与を個別に見ていくと、それぞれの時代背景や地域特性に応じた違いが見られる。しかし、それらを俯瞰し、通時的に分析することで、その行動様式を貫くいくつかの重要なパターンと変遷が浮かび上がってくる。
4.1 動機と正当化の変遷
ロシア(ソ連)が軍事行動を内外に正当化するために用いてきた「物語(ナラティブ)」は、時代と共にその装いを大きく変えてきたが、その根底にある地政学的な目的は驚くほど一貫している。
- 冷戦期: 軍事介入の正当化は、マルクス・レーニン主義のイデオロギーに強く依拠していた。ハンガリー動乱やチェコスロバキア侵攻は、「反革命の陰謀から兄弟的な社会主義国家を防衛する」という国際主義的義務として語られた 4。これは、ソ連ブロックという閉じた世界の中でのみ通用する論理であった。
- ポスト冷戦期: イデオロギーの権威が失墜すると、正当化の言説はより国際社会が(少なくとも表向きは)理解しやすいものへと変化した。第二次チェチェン紛争は、9.11以降の世界的な潮流に乗り、「国際テロとの戦い」として位置づけられた 11。旧ソ連空間への介入は、西側の介入でも用いられる「平和維持活動」という衣をまとった 32。
- プーチン時代: 正当化の論理は、よりナショナリスティックで、ロシア独自の価値観を前面に押し出すものへと先鋭化していく。2008年のジョージア戦争で初めて本格的に用いられた「自国民(ロシア国籍を付与した住民)の保護」という論理は 12、2014年のクリミア併合や2022年のウクライナ侵攻でも繰り返し使われた 49。さらに、NATOの東方拡大がロシアの生存を脅かすという「防衛的」な安全保障論 17 や、ウクライナとロシアは歴史的に一体であるとする「歴史的正義の回復」、そして「ロシア世界」という独自の文明圏を防衛するという、より広範で文明論的な言説が前面に押し出されるようになった。
この言説の変化は、ロシアの自己認識の変化を反映している。しかし、その根底にある目的、すなわちロシア国境周辺に親ロシア的、あるいは少なくとも中立的な緩衝地帯を確保し、外部勢力(特に西側)の影響力を排除するという地政学的な衝動は、冷戦時代から一貫して変わっていない。イデオロギーが失われた後、ロシアは「自国民保護」や「文明圏」といった、より原始的で感情に訴えかけるナショナリズムを、この古くからの地政学的目標を達成するための新たな、そしてより強力な道具として利用しているのである。
4.2 国際的反応と制裁の効果
ロシアの軍事行動に対する国際社会の反応は、その後のロシアの行動を規定する上で重要な役割を果たしてきた。特に、国連の機能と経済制裁の実効性は、常に大きな課題であった。
- 国連の機能不全: ソ連時代からロシアは国連安全保障理事会の常任理事国であり、拒否権を有している。このため、自らの行動や同盟国の行動が議題となった場合、安保理が非難決議や強制力のある措置を採択することを、拒否権を行使して何度も阻止してきた。シリア内戦におけるアサド政権を擁護する決議案への拒否権行使 39 や、2022年のウクライナ侵攻を非難する決議案への拒否権行使 50 はその典型例である。これにより、国際の平和と安全を維持するという安保理の本来の機能は麻痺し、対応の主舞台は法的拘束力のない国連総会へと移らざるを得なくなる 47。
- 経済制裁のパラドックス: 経済制裁は、国際社会が武力行使以外でロシアの行動を変えさせようとする主要な手段であった。しかし、その効果は一様ではない。2014年のクリミア併合後に科された西側諸国の制裁は、ロシア経済に一定の打撃を与え、ルーブルの価値を下げた 51。しかし、同時にこの制裁は、ロシア国内で輸入代替産業の育成を促し、中国や他の非西側諸国との経済関係を強化させる契機ともなった 52。この経験は、ロシアにある程度の「制裁耐性」をつけさせる結果を招いた側面がある。2022年以降に発動された、中央銀行資産の凍結やSWIFTからの排除を含む前例のない規模の制裁は、ロシア経済に遥かに深刻な影響を与えているが 54、戦争を終結させる決定打とはなっておらず、制裁が政治的目的を達成する上での限界も露呈している。
4.3 国内への影響:「旗の下への結集」効果と経済的代償
対外的な軍事行動は、ロシアの国内政治と社会に深く、そしてしばしば矛盾した影響を与えてきた。
- 政治的影響: 短期的には、軍事行動は国民の愛国心を刺激し、政権への支持を急上昇させる「旗の下への結集(rally ‘round the flag)」効果をもたらす傾向が顕著である。第二次チェチェン紛争の開始はプーチンの権力掌握を決定づけ、2014年のクリミア併合は彼の支持率を過去最高の水準に押し上げた 43。2022年のウクライナ侵攻後も、当初の60%台から80%台へと支持率は上昇した 56。同時に、政権は戦争状態を口実に、独立系メディアの閉鎖、反戦デモの徹底的な弾圧、そして「フェイクニュース法」の制定など、国内の言論統制を極限まで強化し、あらゆる反体制的な動きを封じ込める 57。
- 経済的・社会的影響: 長期的には、軍事紛争がもたらす代償は極めて大きい。アフガニスタン侵攻がソ連経済を疲弊させ、崩壊の一因となったように 8、戦争は莫大な戦費を必要とし、国家の資源を軍事部門に偏在させる。ウクライナ侵攻後の強力な経済制裁は、西側の先端技術へのアクセスを断ち、ロシア経済の近代化を阻害する 55。エネルギー価格の高騰は一時的にロシアの財政を支えるが、サプライチェーンの混乱や外資系企業の撤退は、長期的な経済基盤を蝕む 60。また、戦争と抑圧的な国内環境は、優秀なIT技術者や研究者などの国外流出(頭脳流出)を加速させ、国家の将来的な競争力を著しく損なう。
ここには、ロシアの現代史を貫く根本的なトレードオフの構造が見て取れる。政権は、軍事行動を通じて短期的に高い支持率を獲得し、権威主義的な支配を強化する。しかし、その代償として、国家は国際社会から孤立し、経済は停滞し、社会は活力を失っていく。これは、政権の存続という短期的な政治的利益のために、国家の長期的な発展と繁栄を犠牲にするという構造的なジレンマである。紛争を続けるほど政権は(短期的には)安泰になるが、国力そのものは着実に蝕まれていくのである。
結論:戦後ロシア軍事史の教訓と今後の展望
第二次世界大戦の終結から70年以上にわたり、ソ連およびその後継国家であるロシア連邦は、その回数を単純に集計することが困難なほど、数多くの軍事紛争に多様な形態で関与してきた。本報告書が明らかにしたように、重要なのはその回数ではなく、その行動を貫く一貫した論理とパターンの存在である。
その中核にあるのは、自国の安全保障と大国としての地位を、周辺国の主権や国際法の原則よりも優先するという地政学的な思考様式である。この思考は、冷戦期の「社会主義共同体の防衛」というイデオロギー、ポスト冷戦期の「テロとの戦い」や「平和維持」という国際的に受け入れられやすい言説、そしてプーチン時代の「自国民保護」や「ロシア世界」というナショナリズムといった、時代ごとに異なる「衣装」をまといながらも、ロシアの対外行動の不変の核として存在し続けてきた。すなわち、自らの国境周辺に外部勢力の影響が及ばない緩衝地帯を確保するという目標は、帝政ロシアからソ連、そして現代ロシアに至るまで、驚くべき継続性をもって追求されてきた。
本分析から得られるもう一つの重要な教訓は、国際社会の反応がロシアの将来の行動に与える影響である。ハンガリー動乱やジョージア戦争に対する西側諸国の反応が限定的であった場合、ロシアはそれを事実上の黙認と解釈し、次なる、より大胆な行動へと踏み出す傾向が明確に見て取れる。国際社会の決意の欠如や不一致は、現状変更を試みる国に対し、誤ったシグナルを送る危険性をはらんでいる。
現在のウクライナ戦争は、この70年以上にわたる歴史の集大成と言える。そこには、緩衝地帯の確保、NATO拡大への対抗、歴史認識に基づく領土要求、そして国内の権力基盤強化という、これまで見てきた全ての動機が凝縮されている。これは、ロシアが自らの安全保障観と国際秩序における地位をかけて挑んだ、建国以来最大の賭けである。その帰結は、ウクライナの運命はもちろんのこと、ロシア自身の国家としての未来、そして冷戦終結後に築かれた国際秩序そのもののあり方を左右する、極めて重大な意味を持つだろう。ロシアの軍事史を理解することは、単に過去を振り返ることではなく、21世紀の世界が直面する課題の根源を理解し、今後の国際関係を展望するための不可欠な鍵となるのである。
引用文献
- ソヴィエト社会主義共和国連邦/ソ連邦/ソ連 – 世界史の窓, 10月 15, 2025にアクセス、 https://www.y-history.net/appendix/wh1501-117.html
- America’s Wars – U.S. Department of Veterans Affairs, 10月 15, 2025にアクセス、 https://department.va.gov/americas-wars/
- List of wars involving the Soviet Union – Wikipedia, 10月 15, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wars_involving_the_Soviet_Union
- 1956 年ハンガリー動乱を読み解く – 盛田常夫, 10月 15, 2025にアクセス、 https://www.morita-from-hungary.com/j-01/01-08/01-08-168.pdf
- List of Russian Wars: Wars Fought By Russia From 1283 Till 2022, 10月 15, 2025にアクセス、 https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/list-of-wars-fought-by-russia-1645792641-1
- プラハの春 – 世界史の窓, 10月 15, 2025にアクセス、 https://www.y-history.net/appendix/wh1604-027.html
- www.y-history.net, 10月 15, 2025にアクセス、 https://www.y-history.net/appendix/wh1702-001.html#:~:text=%EF%BC%91%EF%BC%99%EF%BC%97%EF%BC%99%E5%B9%B4%E3%80%81%E3%82%BD%E9%80%A3%E3%81%AE%E3%83%96%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%83%95,%E4%B8%80%E5%9B%A0%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%80%82
- ソ連のアフガニスタン侵攻/アフガニスタン撤退 – 世界史の窓, 10月 15, 2025にアクセス、 https://www.y-history.net/appendix/wh1702-001.html
- アフガニスタン | 国際テロリズム要覧について | 公安調査庁, 10月 15, 2025にアクセス、 https://www.moj.go.jp/psia/ITH/situation/SW_S-asia/Afghanistan.html
- 「戦争は平和である」ロシアの近代戦争と帝国主義文化 – Ukraїner, 10月 15, 2025にアクセス、 https://www.ukrainer.net/ja/senso-wa-heiwadearu/
- 第一次チェチェン紛争への道程 – 群馬大学リポジトリ, 10月 15, 2025にアクセス、 https://gunma-u.repo.nii.ac.jp/record/1249/files/07_noda.pdf
- 14年前にも、意に沿わない国をねじ伏せた ジョージア侵攻でプーチン氏が学んだこと, 10月 15, 2025にアクセス、 https://globe.asahi.com/article/14696068
- シリア戦争とロシアの世界政策 – 北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター, 10月 15, 2025にアクセス、 https://src-h.slav.hokudai.ac.jp/publictn/slavic-studies/68/Matsuzato%20Kimitaka.pdf
- いまさら聞けない「ウクライナ紛争」について東大生が超要約してみた【書籍オンライン編集部セレクション】, 10月 15, 2025にアクセス、 https://diamond.jp/articles/-/360593
- ウクライナ危機の世界史的意義 ―ロシア・ウクライナ関係史の視点から, 10月 15, 2025にアクセス、 https://ippjapan.org/archives/4697
- List of wars involving Russia – Wikipedia, 10月 15, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wars_involving_Russia
- ロシアのウクライナ侵攻の背景をわかりやすく解説! – プルーヴ株式会社, 10月 15, 2025にアクセス、 https://www.provej.jp/column/russia/russia-ukraine-background/
- ロ シ ア に よ る ウ ク ラ イ ナ 軍 事 侵 攻, 10月 15, 2025にアクセス、 https://www.keidanren.or.jp/journal/monthly/2022/07/p60.pdf
- ロシアによるウクライナ侵攻の背後には何がある?『池上彰の世界の見方 東欧・旧ソ連の国々 ロシアに服属するか、敵となるか』 | 小学館, 10月 15, 2025にアクセス、 https://www.shogakukan.co.jp/news/475352
- ハンガリー反ソ暴動/ハンガリー事件 – 世界史の窓, 10月 15, 2025にアクセス、 https://www.y-history.net/appendix/wh1602-046.html
- ハンガリー動乱 – Wikipedia, 10月 15, 2025にアクセス、 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%82%AC%E3%83%AA%E3%83%BC%E5%8B%95%E4%B9%B1
- ハンガリー動乱(1956年)に対するソ連とアメリカの反応は、冷戦の発展にどう影響したの?, 10月 15, 2025にアクセス、 https://www.reddit.com/r/AskHistorians/comments/m5f9ej/how_did_the_reactions_of_the_ussr_and_the_usa_to/?tl=ja
- 弁護士会の読書:ハンガリー革命1956, 10月 15, 2025にアクセス、 https://www.fben.jp/bookcolumn/2008/05/post_1817.php
- 【1968(昭和43)年1月5日】プラハの春、東欧民主化の芽 | トウシル 楽天証券の投資情報メディア, 10月 15, 2025にアクセス、 https://media.rakuten-sec.net/articles/-/47285
- 「プラハの春」再考 – 中央大学学術リポジトリ, 10月 15, 2025にアクセス、 https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/record/12095/files/1343-2125_24_131-147.pdf
- 「プラハの春」について聞いてみた – note, 10月 15, 2025にアクセス、 https://note.com/culture_map/n/nbb46328a4785
- Wars of the Soviet Union | The History Guy: War and Conflicts News, 10月 15, 2025にアクセス、 https://historyguy.com/soviet_wars.htm
- Category:Wars involving the Soviet Union – Wikipedia, 10月 15, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Wars_involving_the_Soviet_Union
- ソ連のアフガニスタン経験 – 防衛研究所, 10月 15, 2025にアクセス、 https://www.nids.mod.go.jp/publication/kiyo/pdf/bulletin_j12_1_1.pdf
- 旧ソ連を震撼させたアフガニスタン 侵攻失敗、帰還兵はPTSD…そして国家崩壊, 10月 15, 2025にアクセス、 https://globe.asahi.com/article/14419755
- ソ連アフガニスタン戦争の終結 – 提言・論考 – SSDP 安全保障・外交政策研究会 – Society of Security and Diplomatic Policy Studies, 10月 15, 2025にアクセス、 http://ssdpaki.la.coocan.jp/proposals/168.html
- Russia’s wars for the last 30 years and their consequences – Ukraїner, 10月 15, 2025にアクセス、 https://www.ukrainer.net/en/russian-wars/
- 【大人の教養】プーチンの私兵か、ウクライナの義勇兵か…チェチェン人の悲劇とは?, 10月 15, 2025にアクセス、 https://diamond.jp/articles/-/371669
- ソ連期のチェチェンにおける政治・経済・社会構造, 10月 15, 2025にアクセス、 https://tohoku.repo.nii.ac.jp/record/122923/files/KJ00006238779.pdf
- 河野外務大臣談話, 10月 15, 2025にアクセス、 https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/danwa/07/dko_0209.html
- 内田州「ロシアによるウクライナ侵攻を紐解くためのジョージア情勢 – 創発戦略研究オープンラボ(ROLES) – 東京大学, 10月 15, 2025にアクセス、 https://roles.rcast.u-tokyo.ac.jp/publication/20240928
- 2008年グルジア・ロシア戦争:詳細な分析と国際関係への影響 – Georgia.to, 10月 15, 2025にアクセス、 https://georgia.to/ja/2008-war/
- シリア内戦とは?アサド政権の現在は?終わらない理由や現在の難民の生活・アメリカの介入をわかりやすく解説 – Spaceship Earth(スペースシップ・アース)|SDGs・ESGの取り組み事例から私たちにできる情報をすべての人に提供するメディア, 10月 15, 2025にアクセス、 https://spaceshipearth.jp/syria-conflict/
- シリア情勢と米露関係(2) | 研究プログラム – 東京財団, 10月 15, 2025にアクセス、 https://www.tkfd.or.jp/research/detail.php?id=1910
- クリミア併合に何の意味があったか知ってますか 常に支配国が変わってきた歴史を経て今がある, 10月 15, 2025にアクセス、 https://toyokeizai.net/articles/-/541749
- ロシアはどのようにクリミアを占領したのか? – Ukraїner, 10月 15, 2025にアクセス、 https://www.ukrainer.net/ja/kurimia-o-senryo-shita/
- 2014 年クリミア併合過程におけるハイブリッド戦の考察, 10月 15, 2025にアクセス、 https://www.mod.go.jp/msdf/navcol/assets/pdf/ssg2022_06_03.pdf
- ロシアのウクライナ侵攻 第4章:ウクライナ侵攻とロシア内政―大統領支持率、エリート、異論派, 10月 15, 2025にアクセス、 https://www.nira.or.jp/paper/research-report/2022/142209.html
- ロシアのウクライナ侵攻のなぜ?どうして? みんなの質問に岡部さんが回答 – 学研キッズネット, 10月 15, 2025にアクセス、 https://kids.gakken.co.jp/kagaku/nandemo/ukraine-qa220822/
- ウクライナ侵攻に伴う対ロシア経済制裁の影響 – 日本政策投資銀行(DBJ), 10月 15, 2025にアクセス、 https://www.dbj.jp/upload/investigate/docs/26595bff984cbb5c0bde83383ec5487d_1.pdf
- 第1節 ロシアのウクライナ侵略による世界経済への影響:通商白書2022年版 (METI/経済産業省), 10月 15, 2025にアクセス、 https://www.meti.go.jp/report/tsuhaku2022/2022honbun/i1110000.html
- ウクライナ情勢をめぐるグローバル・サウスの動向 -国連総会決議をめぐる各国の投票行動を中心に – 参議院, 10月 15, 2025にアクセス、 https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2023pdf/20230601048.pdf
- 国連総会がロシア非難決議を採択、クアッド首脳会談でウクライナ情勢を議論 – ジェトロ, 10月 15, 2025にアクセス、 https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/03/7f12ab7c19f6b58e.html
- ロシア・ウクライナ戦争 「そもそも原因は何だったのか?」について 6352 – 公明党, 10月 15, 2025にアクセス、 https://www.komei.or.jp/km/gyota/2024/03/27/%E3%83%AD%E3%82%B7%E3%82%A2%E3%83%BB%E3%82%A6%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%8A%E6%88%A6%E4%BA%89%E3%81%AE%E5%8E%9F%E5%9B%A0%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/
- ロシアによるウクライナ侵攻への国連の対応 :国際法の遵守に向けた一致を目指して, 10月 15, 2025にアクセス、 https://oilgas-info.jogmec.go.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/009/952/202311_1a.pdf
- 欧米の対露制裁措置の現状と効果、ロシアによるカウンター制裁について, 10月 15, 2025にアクセス、 https://www.cistec.or.jp/jaist/event/kenkyuutaikai/kenkyu34/01-02harada.pdf
- 経済面から見たウクライナ侵攻 3 年目 – 防衛研究所, 10月 15, 2025にアクセス、 https://www.nids.mod.go.jp/publication/commentary/pdf/commentary305.pdf
- 対露制裁の現状と見通し – 日本国際問題研究所, 10月 15, 2025にアクセス、 https://www.jiia.or.jp/topic-cdast/event/20221014-01.pdf
- ウクライナでの戦争が世界地域にどう影響しているか, 10月 15, 2025にアクセス、 https://www.imf.org/ja/Blogs/Articles/2022/03/15/blog-how-war-in-ukraine-is-reverberating-across-worlds-regions-031522
- 第3章 ロシアへの経済制裁とその影響, 10月 15, 2025にアクセス、 https://www.nira.or.jp/paper/report032205_3.pdf
- ロシア基礎データ|外務省 – Ministry of Foreign Affairs of Japan, 10月 15, 2025にアクセス、 https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/russia/data.html
- 第4章 ウクライナ侵攻とロシア内政 ―大統領支持率、エリート, 10月 15, 2025にアクセス、 https://www.nira.or.jp/paper/report032205_4.pdf
- ウクライナ戦争のロシア経済・社会への影響 – 日本国際問題研究所, 10月 15, 2025にアクセス、 https://www.jiia.or.jp/pdf/research/R04_Russia/01-05.pdf
- 第3章 各地域の情勢と日本との関係 第4節 旧ソ連, 10月 15, 2025にアクセス、 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bluebook/1992/h04-3-4.htm
- ロシア軍事侵攻、ウクライナ日系企業に深刻な影響 – ジェトロ, 10月 15, 2025にアクセス、 https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/03/d9ad7d994fac1208.html
- Global Risk Manager Vol.003 ロシアのウクライナ侵攻によるサプライチェーンへの影響と対策とは, 10月 15, 2025にアクセス、 https://www.aig.co.jp/sonpo/global/trend/risk-manager/003-ukraine-crisis-and-supply-chain

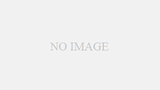
コメント