序論:「民主主義の兵器廠」から世界の警察官へ
第二次世界大戦の終結は、世界に恒久的な平和をもたらすという期待を抱かせた。アメリカ合衆国は、ファシズムに対する勝利において決定的な役割を果たし、「民主主義の兵器廠」としての地位を確立した。しかし、戦後の現実は、平和の時代の到来ではなく、新たな形態の世界的紛争の幕開けであった。かつては孤立主義を国是とし、ヨーロッパの紛争への不介入を掲げたワシントン初代大統領以来の伝統を持つ国家が 1、いかにして世界で最も頻繁に軍事介入を行う超大国へと変貌を遂げたのか。このパラドックスこそが、第二次世界大戦後のアメリカ外交政策を理解する上での核心的な問いである。
本報告書は、「アメリカは第二次世界大戦後に何度戦争を起こしたか、または参戦したか」という問いに答えることを目的とする。しかし、その答えは単なる数字の列挙ではあり得ない。この問いは、アメリカの権力、イデオロギー、そしてその行使がもたらした数々の帰結を深く掘り下げるための出発点である。議会による正式な宣戦布告が行われた戦争はごく僅かであり、アメリカの軍事行動の大部分は、より曖昧な法的・政治的枠組みの中で実行されてきた。したがって、本報告書では、大規模戦争から秘密作戦、代理戦争、限定的な空爆に至るまで、多様な軍事介入の形態を分類し、それぞれの時代背景における戦略的・イデオロギー的動機を分析する。冷戦、唯一の超大国時代、そして対テロ戦争という三つの異なる時代を通じて、アメリカの軍事介入がどのように変容し、国際秩序、介入対象国、そしてアメリカ自身にどのような影響を与えてきたのかを多角的に検証する。
第1部 戦場の定義:アメリカの軍事介入に関する類型論
アメリカの戦後史における軍事行動を正確に理解するためには、まず「戦争」という言葉そのものを解体する必要がある。アメリカ合衆国憲法は、戦争を宣言する権限を議会に与えているが、第二次世界大戦後、議会がこの権限を行使したのは一度もない。しかし、これはアメリカが平和を享受してきたことを意味するものではない。むしろ、歴代政権は、議会の承認を必要としない、あるいはより簡素な手続きで実行可能な、多様な形態の軍事力行使を選択してきた。したがって、介入の回数を単純に数えるのではなく、その性質と規模に基づいて類型化することが、より分析的な視点を提供する。
「戦争」の解体
アメリカの軍事介入を分析する上で、公式な宣戦布告の有無は決定的な基準にはならない。むしろ、大統領府は、その時々の政治的・法的制約を回避するために、軍事行動を「警察行動」「司令部作戦」「懲罰的空爆」など、意図的に曖昧な名称で呼ぶことが多かった 3。この言葉の選択は、単なる修辞的な問題ではない。それは、議会の監督を最小限に抑え、大統領の外交・軍事における権限を最大化するための政治的手段であった。
この戦略の典型例が、ベトナム戦争への本格介入を決定づけた1964年の「トンキン湾決議」である 5。これは宣戦布告ではなかったが、ジョンソン大統領に対し、東南アジアにおける「共産主義の侵略」に対抗するために「あらゆる必要な措置」を講じる広範な権限を与えた 7。後に、決議の根拠となったトンキン湾事件の一部がアメリカ側のでっち上げ、あるいは誤認であったことが明らかになったが 8、この決議は、公式な戦争宣言なしに大規模な戦争を遂行する道を切り開いた。このように、法的・意味論的な曖昧さを利用して大統領権限を拡大し、軍事行動の自由度を高めるという手法は、戦後アメリカの対外政策における一貫した特徴となっている。
軍事介入の類型
アメリカの軍事行動は、その目的、規模、手段において多岐にわたる。以下に、分析の枠組みとして主要な類型を示す。
- 大規模戦争(Major Wars):数十万から数百万の米軍兵士が投入され、長期間にわたって行われた大規模な紛争。朝鮮戦争(1950-1953年)、ベトナム戦争(1961-1973年)、アフガニスタン戦争(2001-2021年)、イラク戦争(2003-2011年)がこれに該当する。
- 限定的軍事介入(Limited Military Interventions):特定の限定的な目的を達成するために、比較的短期間で行われる直接的な戦闘を伴う軍事作戦。1983年のグレナダ侵攻、1989年のパナマ侵攻、1992-1993年のソマリア介入などが代表例である 10。
- 空爆・ミサイル攻撃(Bombing Campaigns & Air Raids):地上部隊の関与を最小限に抑え、空軍力および海軍力を主たる手段とする軍事行動。1986年のリビア空爆、1995年のボスニア空爆、1999年のコソボ空爆などが含まれる 10。
- 秘密作戦・政権転覆(Covert Operations & Regime Change):中央情報局(CIA)などが主導し、アメリカの直接的な軍事関与を隠蔽した形で行われる政権の転覆や支援活動。1953年のイラン、1954年のグアテマラ、1973年のチリにおけるクーデターへの関与がこれにあたる 3。
- 代理戦争(Proxy Wars):敵対する大国(主にソビエト連邦)が支援する勢力に対し、アメリカが直接派兵するのではなく、現地の同盟国や反政府勢力に資金、武器、情報を提供して戦わせる紛争。1980年代のソ連に対するアフガニスタンのムジャヒディン支援がその典型である 13。
- 核による威嚇(Nuclear Threats):紛争相手国に対して、核兵器の使用を明示的または暗示的に示唆することで、政治的・軍事的な目的を達成しようとする行為。朝鮮戦争中やベルリン危機、スエズ危機など、冷戦期に複数回行われたと記録されている 3。
第2部 冷戦の要請(1945年~1991年):共産主義の封じ込め
第二次世界大戦後、アメリカの外交政策を規定した最大の要因は、ソビエト連邦とのイデオロギー的・地政学的な対立、すなわち冷戦であった。ソ連の影響力と共産主義の拡大を阻止するという「封じ込め政策」が、トルーマン・ドクトリン以降の歴代政権の対外政策の根幹をなし、世界各地での軍事介入を正当化する包括的な論理的枠組みを提供した 13。
火による試練:朝鮮戦争(1950年~1953年)
1950年6月、北朝鮮が韓国に侵攻したことで朝鮮戦争が勃発した。これは、冷戦がアジアにおける大規模な「熱戦」へと転化した最初の事例であった 16。アメリカは国連安全保障理事会の決議を主導し、国連軍の中核として韓国を防衛するために軍事介入した 17。当初の目的は、北緯38度線まで侵攻軍を押し戻し、戦前の状態を回復することであった。しかし、マッカーサー元帥率いる国連軍が仁川上陸作戦を成功させ、戦況が逆転すると、トルーマン政権は朝鮮半島の武力統一へと目標を拡大した 15。この決定が、中国の「人民義勇軍」の介入を招き、戦争は泥沼の消耗戦へと陥った。
最終的に、戦争は1953年に北緯38度線をほぼそのままの形で軍事境界線とする休戦協定によって終結した 16。アメリカにとっては、明確な勝利とは言えない結果であったが、この戦争はアメリカの国家安全保障政策に計り知れない影響を与えた。国防予算は4倍に急増し、冷戦は完全に軍事化された 20。また、アメリカは共産主義の脅威から非共産主義世界を防衛するグローバルな軍事的役割を確固たるものにした。アメリカ国内では「忘れられた戦争」とも呼ばれるが、朝鮮戦争は、その後のアジアにおける限定戦争の先例となった 20。
影の戦争:秘密作戦と代理戦争
冷戦期のアメリカは、大規模な正規軍を投入する戦争と並行して、CIAを駆使した「影の戦争」を世界中で展開した。特に、自国の「裏庭」と見なしてきたラテンアメリカや、戦略的に重要な中東において、この手法は多用された。その目的は、ソ連寄りの政権を転覆させ、親米的な政権を樹立・維持することにあった。
代表的な例として、1953年にイランで民主的に選出されたモサッデク政権を転覆させ、親米的なシャー(皇帝)の権力を回復させたクーデターや、1954年にグアテマラで土地改革を進めていたアルベンス政権を武力で打倒した作戦が挙げられる 3。1961年には、キューバのカストロ政権転覆を狙った亡命キューバ人部隊によるピッグス湾侵攻を支援したが、これは惨憺たる失敗に終わった 3。
これらの介入は、アメリカの戦略的・地政学的な文脈認識に基づいていた。アジアは、中国やソ連といった主要な共産主義大国と直接対峙する最前線と見なされ、大規模な軍事力の投入が正当化された。一方、モンロー主義以来の伝統的な勢力圏であるラテンアメリカでは 1、より低コストで、国内の政治的反発を招きにくく、かつソ連との直接対決を避けられる秘密作戦が好まれた。この overt(公然)と covert(秘密)の二本立てのアプローチ、すなわち「介入の階層構造」は、冷戦期アメリカのグローバル戦略の根幹をなすものであった。
また、1979年にソ連がアフガニスタンに侵攻すると、アメリカはこれをベトナム戦争の二の舞にさせるべく、イスラム聖戦士(ムジャヒディン)に対して最新鋭のスティンガーミサイルを含む大規模な軍事支援を行った 14。これは代理戦争の典型例であり、ソ連に多大な消耗を強いて撤退に追い込むことに成功したが、その代償もまた大きかった(第5部で詳述)。
詳細分析:ベトナムの泥沼(1961年~1973年)
ベトナム戦争は、アメリカの軍事介入の歴史において最も長く、最も分裂的で、最もトラウマ的な経験となった。
- ドミノ理論と段階的拡大:アメリカの介入は、「ドミノ理論」というイデオロギー的な恐怖に突き動かされていた。これは、南ベトナムが共産化すれば、東南アジアの国々が次々とドミノ倒しのように共産主義の手に落ちるという信念である 22。この恐怖が、当初の軍事顧問団の派遣から、北ベトナムへの爆撃(北爆)、そして大規模な地上部隊の投入へと至る「段階的拡大(incremental escalation)」政策を正当化した 10。
- 嘘の上に築かれた戦争:アメリカが本格的な軍事介入に踏み切る直接の口実となったのが、1964年8月のトンキン湾事件であった。ジョンソン政権は、アメリカの駆逐艦が公海上で北ベトナム軍から2度にわたり「いわれなき攻撃」を受けたと主張した 24。この報告に基づき、議会は前述のトンキン湾決議を圧倒的多数で可決した 5。しかし、後に国防総省の秘密文書「ペンタゴン・ペーパーズ」などによって、2度目の攻撃(8月4日)は実際には存在せず、政権が戦争拡大の口実を得るために情報を捏造または誤認した可能性が極めて高いことが暴露された 7。
- 帰結と遺産:アメリカは、圧倒的な軍事力を持ちながら、ベトコンのゲリラ戦術と北ベトナムの不屈の抵抗を打ち破ることができなかった 23。戦争はアメリカ社会を深く分断し、激しい反戦運動を引き起こした 26。多大な犠牲と戦費を費やした末、1973年のパリ和平協定に基づき米軍は撤退し、その2年後の1975年、サイゴンが陥落して南ベトナムは崩壊、ベトナムは共産主義のもとに統一された 8。この敗北は、アメリカ国民の政府への信頼を著しく損ない、海外の紛争への軍事介入に対する強い躊躇、いわゆる「ベトナム・シンドローム」を生み出した 10。一方で、この戦争がソ連の資源を消耗させ、結果的に冷戦の勝利に貢献したという戦略的成功と見なす修正主義的な見解も存在する 27。この戦術的敗北と戦略的成功という二重の評価は、ベトナム戦争の複雑な遺産を物語っている。
第3部 ユニポーラ・モーメント(1991年~2001年):新世界秩序への介入
1991年のソビエト連邦の崩壊により、冷戦は終結し、アメリカは歴史上類を見ない唯一の超大国となった 13。この「ユニポーラ・モーメント(一極集中時代)」において、アメリカの軍事介入の動機は、共産主義の封じ込めから、新たな世界秩序の構築、人道的危機への対応、そしてアメリカの覇権の維持へと移行した。
覇権の誇示:第一次湾岸戦争(1990年~1991年)
1990年8月、イラクがクウェートに侵攻したことは、冷戦後の国際秩序にとって最初の大きな試金石となった。ジョージ・H・W・ブッシュ大統領は、この侵略を「新世界秩序(New World Order)」に対する挑戦と位置づけ、国連安全保障理事会の承認のもと、30カ国以上からなる多国籍軍を編成した 27。
「砂漠の嵐作戦」と名付けられた軍事作戦は、当時の統合参謀本部議長コリン・パウエルが提唱した「パウエル・ドクトリン」を体現するものであった。すなわち、明確な政治目標を設定し、それを達成するために圧倒的な軍事力を行使するというものである 10。約1ヶ月にわたる大規模な空爆と、それに続くわずか100時間の地上戦で、多国籍軍はイラク軍をクウェートから駆逐し、圧勝を収めた 27。この勝利は、ベトナム戦争の亡霊をアラビア半島の砂漠に葬り去ったと称賛され、アメリカの軍事的威信を回復させるとともに、「ベトナム・シンドローム」を克服した象徴的な出来事と見なされた 27。
人道主義の曖昧さ
冷戦のイデオロギー対立が終焉すると、民族紛争や国家の破綻に伴う人道的危機が国際社会の新たな課題として浮上した。アメリカは、人権擁護や民主主義の促進を名目に、いくつかの介入を行ったが、その姿勢は一貫性を欠き、政治的なジレンマを露呈した。
- ソマリア(1992年~1993年):当初は、飢饉に苦しむ人々を救うための人道支援任務「希望回復作戦」として始まり、食糧配給ルートの確保に成功した 29。しかし、任務は次第に現地の武装勢力の武装解除と国家再建(ネーション・ビルディング)へと拡大していった 10。1993年10月、モガディシュでの戦闘で米軍のヘリコプター「ブラックホーク」が撃墜され、18人の米兵が死亡する悲劇(「ブラックホーク・ダウン事件」)が発生すると、アメリカ国内の世論は一気に厭戦ムードに傾き、クリントン政権は軍の撤退を決定した 10。
- ハイチ(1994年):クーデターで追放されたアリスティド大統領を復権させるため、米軍が介入した。元大統領ジミー・カーターの土壇場での交渉により、米軍は無抵抗で上陸を果たし、クリントン政権はこの介入を「模範的な取り組み」と自賛した。しかし、その後のハイチの政治的・経済的混乱は続き、介入の長期的成果には疑問符が付けられた 10。
- バルカン半島(ボスニア 1995年、コソボ 1999年):「民族浄化」と呼ばれるセルビア人勢力による残虐行為を阻止するため、アメリカはNATOを主導して空爆を実施した 10。特に1999年のコソボ空爆は、国連安保理の明確な決議なしに行われたため、その国際法上の合法性を巡って激しい論争を巻き起こした 32。これらの介入は、地上部隊を派遣せず、空爆に終始した点に特徴がある。
ベトナム・シンドロームが「勝てない泥沼の戦争」への恐怖であったとすれば、ソマリアでの経験は、より具体的な「米兵の犠牲」に対する極度の恐怖、すなわち「ソマリア・シンドローム」を生み出した。この新しいシンドロームは、その後のアメリカの軍事政策に決定的な影響を与えた。モガディシュの悲劇に衝撃を受けたクリントン政権は、バルカン半島での介入において、地上部隊の派遣という選択肢を当初から排除した 10。その結果、高高度からの精密爆撃を中心とする「空爆オンリー」という新たな介入モデルが確立された。この方法は、米兵の犠牲を最小限に抑えることができる一方で、地上の残虐行為を直接阻止する能力に限界があり、誤爆による民間人の犠牲を多数出すなどの批判も浴びた 32。これは、世界の道徳的権威として行動したいという願望と、その役割に伴う人的コストやリスクを負いたくないという現実との間の、冷戦後アメリカが抱える根本的な緊張関係を浮き彫りにした。
第4部 対テロ戦争(2001年~現在):永続的紛争という新パラダイム
2001年9月11日の同時多発テロ事件は、アメリカの安全保障戦略を根底から覆した。この攻撃への対応として、ジョージ・W・ブッシュ政権は、国家だけでなくアルカイダのような非国家主体をも標的とする、国境を越えたグローバルな「対テロ戦争」を宣言した 13。この新たな脅威認識は、将来の脅威を未然に防ぐためには先制攻撃も辞さないとする「ブッシュ・ドクトリン」の形成へと繋がり、アメリカの軍事介入は新たな時代に突入した 13。
詳細分析:アフガニスタン、「永遠の戦争」(2001年~2021年)
- ミッション・クリープ(任務の肥大化):アフガニスタン戦争は、9.11テロの首謀者であるアルカイダを匿っていたタリバン政権を打倒するという、明確で国際的な支持を得た目的から始まった 36。しかし、この初期の軍事目標は、タリバン政権の崩壊後、急速に拡大していった。戦争は、安定した民主的なアフガニスタンを建設するという、20年間に及ぶ壮大な国家建設(ネーション・ビルディング)の試みへと変貌した 37。その過程で、戦争の目的は曖昧になり、達成不可能なものへと肥大化していった 39。
- 戦略的失敗:アメリカとその同盟国は、20年という歳月と2兆ドルを超える巨費を投じながら、自立可能なアフガニスタン政府や国軍を構築することに失敗した 38。2021年8月、バイデン政権が米軍の完全撤退を強行すると、アフガニスタン政府と国軍は雪だるま式に崩壊し、タリバンはわずか数週間で首都カブールを制圧、全土を掌握した 36。アメリカ史上最長の戦争は、衝撃的かつ混沌とした形で幕を閉じ、その結末は、かつてのソ連によるアフガニスタン介入の失敗を彷彿とさせるものであった 41。
詳細分析:イラク戦争、選択の戦争(2003年~2011年)
- 論争を呼んだ正当化理由:アフガニスタン戦争とは対照的に、イラク戦争は「選択の戦争」であった。ブッシュ政権は、サダム・フセイン政権が大量破壊兵器(WMD)を保有し、アルカイダと繋がりがあるという二つの主張を主な根拠として、イラクへの侵攻を正当化した。しかし、これらの主張は開戦前から国際的に多くの疑問が呈されており、戦後、いずれも事実ではなかったことが証明された 43。大量破壊兵器の脅威は、開戦を正当化するために捏造あるいは誇張された情報であったとの批判が根強く残っている 43。
- 国際法の崩壊:1991年の湾岸戦争が国連安保理の明確な承認を得ていたのに対し、2003年のイラク侵攻は、安保理の支持を得られないまま、アメリカ主導の「有志連合」によって強行された。このため、フランスやドイツ、ロシアなど多くの国々から、国連憲章に違反する違法な侵略戦争であるとの厳しい非難を浴びた 44。
- 長期的な帰結:戦争はサダム・フセイン政権を短期間で打倒することに成功したが、その後のイラクを深刻な宗派間内戦と長期にわたる反米武装闘争の渦に巻き込んだ。国家機構の解体によって生じた権力の真空と社会の不安定化は、アルカイダ系の過激派組織が勢力を拡大する格好の土壌を提供し、後に「イスラム国(ISIS)」の台頭を直接的に引き起こした 43。皮肉なことに、テロとの戦いを名目に始めた戦争が、より悪質で新たなテロの脅威を生み出し、その掃討のためにアメリカは再びこの地域への軍事介入を余儀なくされることになった。
進化する戦場
アフガニスタンとイラクでの泥沼の戦争は、アメリカの介入戦略にさらなる変化を促した。大規模な地上部隊を長期間駐留させることの人的・経済的コストの大きさ、そして政治的リスクの高さが明らかになるにつれ、オバマ政権以降のアメリカは、より低コストで、より目立たない介入形態へと軸足を移していった。その代表が、無人航空機(ドローン)による標的殺害作戦である。パキスタン、イエメン、ソマリアなど、公式な「戦場」ではない地域でも、テロリスト容疑者に対するドローン攻撃が常態化した 47。また、2011年のリビア内戦では、地上部隊を派遣せず、反体制派への限定的な航空支援に徹した。これらの手法は、大規模な軍事展開を避けつつ、アメリカのパワーを投射しようとする新たな戦略的志向を反映している。
第5部 包括的清算:アメリカの介入主義がもたらしたコストと帰結
第二次世界大戦後、アメリカが行ってきた数々の軍事介入は、世界に、そしてアメリカ自身に、計り知れない影響を及ぼしてきた。そのコストは、戦費や死傷者の数といった具体的な数値で測れるものから、国際法や国内社会への影響といった無形のものまで、多岐にわたる。この最終部では、これらのコストと帰結を包括的に検証する。
具体的な犠牲:戦争のコストの定量化
特に9.11以降の「対テロ戦争」に関しては、ブラウン大学の「戦争のコスト(Costs of War)」プロジェクトが、その人的・経済的コストに関する最も包括的かつ信頼性の高いデータを提供している 47。これらのデータは、アメリカの介入がもたらした破壊の規模を具体的に示している。
|
紛争地域 |
財政的コスト(米ドル) |
直接的死者数(合計) |
直接的死者数(米兵) |
直接的死者数(民間人) |
直接的死者数(敵対勢力) |
推定される間接的死者数 |
避難民・難民の総数 |
|
アフガニスタン/パキスタン、イラク、シリア/イエメン他 |
8兆ドル超 |
90万5,000人~94万人 |
7,014人以上 |
31万2,000人以上 |
25万人以上 |
360万人~380万人 |
3,800万人 |
出典:ブラウン大学「戦争のコスト」プロジェクトの2021年までの報告書に基づく統合データ 47
この表が示す数字は衝撃的である。財政的コストは、将来にわたる退役軍人への医療費を含めると8兆ドルを超え、アメリカの国家財政に重くのしかかっている 47。人的被害はさらに深刻である。直接的な戦闘による死者数は90万人を超えるが、その中で米兵の死者は1%にも満たない。犠牲者の大半は、介入対象国の人々であり、特に民間人の死者数は30万人を超える 51。
さらに重要なのは、この数字が氷山の一角に過ぎないという点である。報告書は、戦争によるインフラの破壊、医療システムの崩壊、食糧不足、水質の悪化などによって引き起こされる「間接的な死者」が、直接的な戦闘による死者数の4倍にものぼると推定している 47。つまり、これらの戦争がもたらした総死者数は、450万人を超える可能性がある。加えて、3,800万人もの人々が家を追われ、国内外で避難生活を余儀なくされている 47。これらの数字は、現代の戦争が戦闘員だけでなく、社会全体をいかに破壊するかを物語っている。
無形の遺産:国際秩序と国内社会への影響
- アメリカの介入主義と国際法:アメリカの軍事介入は、しばしば国際法の原則、特に国連憲章が定める武力行使の禁止(安全保障理事会の承認または自衛権の行使を除く)と緊張関係にあった 46。1983年のグレナダ侵攻は国連総会で非難され 11、1999年のコソボ空爆は安保理の承認を欠いていた 32。そして、2003年のイラク戦争は、多くの国際法学者から明白な侵略行為と見なされた 44。アメリカが自国の安全保障上の利益を国際的な法的規範よりも優先させる姿勢は、法の支配に基づく国際秩序を揺るがし、「人道的帝国主義」や「新植民地主義」といった批判を招く一因となった 53。
- ブローバック効果:アメリカの介入が、意図せざる、そしてしばしば否定的な長期的帰結を生み出す「ブローバック」という現象も顕著である。1980年代にCIAがアフガニスタンで支援したムジャヒディンの中から、後にアメリカを標的とするアルカイダが生まれた。2003年のイラク侵攻とそれに続く占領政策が、ISISの台頭を招く土壌を作り出したことは広く指摘されている 43。これらの事例は、短期的な目標を達成するための軍事介入が、長期的にはより深刻な安全保障上の脅威を生み出しかねないという、介入主義の危険なパラドックスを示している。
- 国内での戦争:絶え間ない戦争は、アメリカ国内にも深い爪痕を残している。9.11以降の戦争に従事した退役軍人の自殺率は、戦闘での死者数を上回るという悲劇的な報告もある 47。国家安全保障の名のもとに、愛国者法などに代表される市民的自由の制限が進んだ。そして、軍事関連支出(国防総省、退役軍人省、核兵器開発などを含む)が連邦予算の3分の2に迫るという現状は 51、教育、医療、インフラ整備といった国内の他の重要分野から資源を奪う、巨大な「機会費用」を生み出している。
結論:アメリカの権力の流砂
第二次世界大戦の終結から今日に至るまで、アメリカの軍事介入の歴史は、その動機、形態、そして帰結において、劇的な変遷を遂げてきた。本報告書で分析したように、その歴史は大きく三つの時代に区分できる。第一に、ソ連とのイデオロギー闘争が全ての政策を規定した冷戦期。この時代、介入は共産主義の「封じ込め」という明確な目的の下で行われた。第二に、ソ連崩壊後のユニポーラ・モーメント。アメリカは唯一の超大国として、より野心的で、しばしば人道主義的な名分を掲げた介入を試みたが、その結果は一貫性を欠いた。そして第三に、9.11以降の対テロ戦争の時代。国家ではない敵との、国境を越えた「永遠の戦争」という新たなパラダイムが生まれ、介入は泥沼化・長期化した。
この70年以上にわたる歴史を通じて、アメリカが関与した軍事行動は、その定義次第では数百回にものぼる。しかし、その結果は極めて複雑な様相を呈している。アメリカの圧倒的な軍事力は、敵国の軍隊を破壊し、政権を転覆させることには繰り返し成功してきた。しかし、より困難な課題である、安定した民主的な国家を外部から建設するという試みにおいては、ほとんどの場合、失敗に終わっている。
本報告書で明らかにしたように、その代償は計り知れない。数兆ドルにのぼる戦費、数百万人の命、そして数千万人の避難民という具体的なコストに加え、国際法への敬意の低下、意図せざる脅威の創出(ブローバック)、そしてアメリカ国内社会の疲弊といった無形のコストもまた甚大である。これらのコストは、アメリカの国力と国際的な信頼性を着実に蝕んできた。
現在、世界は中国の台頭などに見られるように、新たな大国間競争の時代へと移行しつつある 55。この新しい戦略的環境において、アメリカが過去の長く、そしてしばしば血塗られた介入の歴史からどのような教訓を学ぶのか。軍事力への過度の依存とその限界を認識し、より賢明で抑制的な外交政策へと舵を切ることができるのか。その選択が、21世紀におけるアメリカの、そして世界の未来を形作ることになるだろう。
引用文献
- アメリカの外交政策 – 世界史の窓, 10月 15, 2025にアクセス、
- 第2次大戦前におけるアメリカ孤立主義と宥和政策, 10月 15, 2025にアクセス、
- U.S. MILITARY INTERVENTIONS SINCE 1890: FROM WOUNDED …, 10月 15, 2025にアクセス、
- FROM WOUNDED KNEE TO IRAQ: A CENTURY OF U.S. MILITARY INTERVENTIONS – Veterans For Peace, 10月 15, 2025にアクセス、
- ja.wikipedia.org, 10月 15, 2025にアクセス、
- 「トンキン湾決議」の二の舞い?/対イラク戦争容認 米で議論起こる – 日本共産党, 10月 15, 2025にアクセス、
- 武器を使わない情報戦―プロパガンダ㉛ – note, 10月 15, 2025にアクセス、
- ベトナム戦争とは?背景や流れ、日本との関わりをわかりやすく!, 10月 15, 2025にアクセス、
- トンキン湾事件とは? わかりやすく解説 – Weblio辞書, 10月 15, 2025にアクセス、
- A Chronology Of U.s. Military Interventions | Give War A Chance …, 10月 15, 2025にアクセス、
- アメリカのグレナダ侵攻に関する質問主意書 – 衆議院, 10月 15, 2025にアクセス、
- United States Interventions | ReVista, 10月 15, 2025にアクセス、
- Foreign interventions by the United States – Wikipedia, 10月 15, 2025にアクセス、
- 30 Invasions, Interventions, and Regime Changes since World War II – Drexel University, 10月 15, 2025にアクセス、
- 朝鮮戦争とは?終わらない理由やいつまで休戦するのかを解説!きっかけや現在日本への影響を紹介 – スペースシップアース, 10月 15, 2025にアクセス、
- 朝鮮戦争 – 世界史の窓, 10月 15, 2025にアクセス、
- 朝鮮戦争 日本への衝撃と余波 – 防衛研究所, 10月 15, 2025にアクセス、
- 【高校世界史B】「米ソの代理戦争!朝鮮戦争の勃発!!」 | 映像授業のTry IT (トライイット), 10月 15, 2025にアクセス、
- アジ歴ニューズレター 第42号 – アジア歴史資料センター, 10月 15, 2025にアクセス、
- 朝鮮戦争とアメリカ−戦争と内政− – 防衛研究所, 10月 15, 2025にアクセス、
- モンロー・ドクトリンとアメリカ外交の二百年 ――多面的な外交理念の歴史的展開――, 10月 15, 2025にアクセス、
- ベトナム戦争 – 世界史の窓, 10月 15, 2025にアクセス、
- なぜ大国アメリカがベトナム戦争で負けたのか?歴史を振り返り調べてみました。, 10月 15, 2025にアクセス、
- トンキン湾事件 – Wikipedia, 10月 15, 2025にアクセス、
- トンキン湾事件(トンキンワンジケン)とは? 意味や使い方 – コトバンク, 10月 15, 2025にアクセス、
- 【高校世界史B】「ベトナム戦争の泥沼化…」 | 映像授業のTry IT (トライイット), 10月 15, 2025にアクセス、
- トラウマはどこへ行った? – ―米軍ベトナム撤退から40年をへて, 10月 15, 2025にアクセス、
- 冷戦後の戦略環境変化とクリントン政権 −東アジア・日本政策を中心として−, 10月 15, 2025にアクセス、
- 希望回復作戦 – Wikipedia, 10月 15, 2025にアクセス、
- ソマリアの悲劇と「人道的介入」 | FOREIGN AFFAIRS JAPAN, 10月 15, 2025にアクセス、
- 1993年のモガディシュの戦いに関するソマリア側の説明 : r/Somalia – Reddit, 10月 15, 2025にアクセス、
- NATOによるコソボ空爆の実態と人道的介入をめぐる議論, 10月 15, 2025にアクセス、
- コソボ問題と現代国際関係, 10月 15, 2025にアクセス、
- 【アメリカ】 オバマ政権による「国家安全保障戦略」報告の発表 – 国立国会図書館デジタルコレクション, 10月 15, 2025にアクセス、
- 【アメリカ】トランプ政権による「国家安全保障戦略」の公表 – 国立国会図書館デジタルコレクション, 10月 15, 2025にアクセス、
- アフガニスタン戦争とは?きっかけは?歴史やアメリカの戦死者数を紹介!現在もわかりやすく解説! – スペースシップアース, 10月 15, 2025にアクセス、
- 「世論に導かれた戦争は危ない」日本人がアフガニスタン戦争から学ぶべき教訓:三浦瑠麗 | 記事, 10月 15, 2025にアクセス、
- [要旨] 2001年の9・11攻撃を受け、米国はアフガニスタンに基地をもつ国際テロ組織「アル カ, 10月 15, 2025にアクセス、
- 米国はアフガニスタンで勝つはずがなかった。なぜなら「敵」を決められなかったから, 10月 15, 2025にアクセス、
- 2021.08.19 藤原帰一教授 朝日新聞(時事小言) 米軍のアフガニスタン撤退 介入による民主化の難しさ – 東京大学未来ビジョン研究センター, 10月 15, 2025にアクセス、
- 旧ソ連を震撼させたアフガニスタン 侵攻失敗、帰還兵はPTSD…そして国家崩壊, 10月 15, 2025にアクセス、
- アフガニスタン紛争 (1978年-1989年) – Wikipedia, 10月 15, 2025にアクセス、
- イラクの平和のために日本ができること – 北海道大学, 10月 15, 2025にアクセス、
- イラク戦争の法的正当化は可能か?, 10月 15, 2025にアクセス、
- イラク戦争 – Wikipedia, 10月 15, 2025にアクセス、
- 米国のシリア空爆と国際法, 10月 15, 2025にアクセス、
- Costs of War Project – Wikipedia, 10月 15, 2025にアクセス、
- costsofwar.watson.brown.edu, 10月 15, 2025にアクセス、
- Costs of War – Center for Human Rights and Humanitarian Studies – Brown University, 10月 15, 2025にアクセス、
- The Devastating Human & Economic Costs of Post-9/11 Wars, 10月 15, 2025にアクセス、
- The cost of the global war on terror: $6.4 trillion and 801,000 lives | Brown University, 10月 15, 2025にアクセス、
- 国 際 法 と 先 制 的 自 衛, 10月 15, 2025にアクセス、
- 「保護するべき人々を犠牲に供する」というアポリア – 南山大学, 10月 15, 2025にアクセス、
- 「国家の国際犯罪」としての侵略 (木原), 10月 15, 2025にアクセス、
- 米国と対中競争 – 防衛研究所, 10月 15, 2025にアクセス、

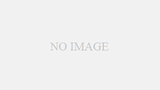
コメント